発達障害のあるお子さんに習い事をさせるべきか、どんな習い事が向いているのか、悩んでいるお母さんも多いですよね。
「うちの子に合う習い事って何?」「続けられるのかな?」と不安を感じるのは当然です。
発達障害の子どもにとって、習い事は 自己肯定感を高めたり、得意を伸ばしたりする大切な場 になります。
でも、無理に続けさせるのは逆効果になることも…。だからこそ、 お子さんに合った習い事を見極めることが大切 なんです。
今回は、発達障害の子どもに向いている習い事の種類や、選び方のポイントを詳しく解説します!
- 発達障害の子どもに習い事が必要な理由
- お子さんに合った習い事の選び方
- おすすめの習い事7選
発達障害の子どもに習い事は必要?メリットと選び方

発達障害のある子どもに習い事をさせることには、どんなメリットがあるのでしょうか?
「他の子と同じようにできるかな?」と不安に思うお母さんも多いですよね。
でも、実は 習い事が子どもの成長をサポートしてくれることもあるんです!
ここでは、発達障害の子どもが習い事をすることで得られるメリットや、選び方のポイントについてお話ししますね。
発達障害の子どもが習い事をするメリットとは?

発達障害の子どもにとって、習い事には 成長を促すたくさんのメリット があります!
たとえば…
- 自己肯定感が高まる 「できた!」という成功体験が増える
- 社会性が身につく 他の子どもや先生と関わることでコミュニケーション力が育つ
- 得意を伸ばせる 子どもの個性に合った習い事で能力を引き出せる
特に 発達障害の子どもは、自分の「得意」を活かすことで自信をつけやすい んです!
もちろん、無理にやらせるのは逆効果…。 子どもが楽しめるかどうかが一番大事 ですよ。
習い事を選ぶときのポイントと注意点



習い事を選ぶとき、 子どもの特性に合っているかどうか がとても重要です!
選ぶ際に気をつけたいポイントはこちらです。
- 子どもの興味を最優先 本人が「やりたい!」と思えることを選ぶ
- ストレスの少ない環境 人数が多すぎない、騒がしくないなど、子どもが安心できる環境かどうか
- 無理のないスケジュール 負担にならないペースで通えるかを確認
無理に「一般的に良い」とされる習い事を選ばないことが大切
お子さんにとって、 楽しく続けられることが最優先! 焦らずじっくり選んでいきましょうね。
習い事が子どもの成長に与える影響とは?



発達障害の子どもが習い事をすることで、さまざまな ポジティブな影響 が期待できます!
たとえば…
| 成功体験が増える | 「できた!」という経験が増えることで、自己肯定感が高まる |
| ルールを学べる | 集団行動を通して、社会的ルールを少しずつ理解できる |
| 得意を活かせる | 「好き!」を伸ばすことで、特技やスキルが身につく |
習い事を通じて、 子どもの可能性が広がることがたくさんあるんです!
でも、 「続けられるかどうか」は習い事の内容よりも環境が大事 。
無理なく、子どもが安心して取り組めるものを見つけてあげましょうね!
発達障害の子どもにおすすめの習い事7選


発達障害のあるお子さんにどんな習い事が向いているのか、迷いますよね。
「せっかく通わせても、すぐにやめてしまうかも…」と不安に思うのも当然です。
でも、お子さんの特性に合った習い事を選べば 楽しく続けることができ、成長につながる んですよ!
ここでは、発達障害の子どもにおすすめの習い事を 7つのカテゴリ に分けてご紹介します。
体を動かすスポーツ系の習い事



運動が得意な子もいれば、苦手な子もいますが、 スポーツ系の習い事にはたくさんのメリット があります!
たとえば…
- 体幹が鍛えられる 姿勢が安定しやすくなる
- エネルギーを発散できる 多動傾向のある子に最適
- ルールや順番を学べる 集団行動の練習にもなる
発達障害の子どもにおすすめのスポーツ系習い事には、以下のようなものがあります。
| 水泳 | 感覚統合のトレーニングに最適で、体力もつく |
| 体操 | バランス感覚や運動能力を向上させる |
| 武道(空手・柔道) | 礼儀や集中力を養うことができる |
お子さんの 得意な動き に合ったものを選ぶと、楽しく続けられますよ!
集中力が養える芸術系の習い事



芸術系の習い事は、 「創造力」や「自己表現力」を伸ばす のにぴったり!
特に 感覚過敏や不器用さがある子どもには、無理のない範囲で取り組めるものを選ぶことが大切 です。
おすすめの芸術系習い事はこちら!
- ピアノ・楽器 指先の運動になり、集中力アップにも効果的
- 絵画・造形教室 感覚統合トレーニングにもなり、自己表現の幅が広がる
- ダンス 体を動かしながらリズム感や表現力を育てる
芸術系の習い事は「楽しみながらできること」が一番大事!お子さんの 好きなものを尊重 してあげると、ぐんぐん成長しますよ。
創造力やコミュニケーション能力を伸ばす習い事



習い事の中には、 「創造力」や「コミュニケーション能力」を伸ばすもの もあります!
発達障害の子どもに特におすすめなのは、次のような習い事です。
| プログラミング教室 | 論理的思考を鍛えられ、自分のペースで学べる |
| レゴ・ロボット教室 | 手先を使いながら、創造力を伸ばせる |
| 英会話 | 遊びながら学べる環境なら、自然にコミュニケーション力が育つ |
特に プログラミングやレゴは、ルールが明確で自由に創作できるため、発達障害の子どもに向いている んです!
この章では、発達障害の子どもにおすすめの習い事を7つご紹介しました。
大切なのは、 お子さんが楽しみながら続けられるかどうか 。無理なくチャレンジできるものを選んでくださいね!
次は 「発達障害の子どもに合った習い事の見つけ方」 について詳しく解説します!
発達障害の子どもに合った習い事の見つけ方
「習い事をさせてみたいけど、うちの子に合うものが分からない…」
そんなお母さんの声をよく聞きますよね。
発達障害の子どもにとって、 習い事選びは「相性」がとても大切 なんです!
ここでは、 子どもにピッタリの習い事を見つけるためのポイント をお伝えしますね。
子どもの特性に合わせた習い事の選び方



発達障害の子どもは、一人ひとり違う特性を持っています。
例えば…
| 多動傾向がある | エネルギーを発散できる「水泳」「体操」などの運動系がおすすめ |
| こだわりが強い | 個人で取り組める「プログラミング」「ピアノ」などが向いている |
| 感覚過敏がある | 大人数ではなく、静かな環境でできる習い事がベスト |
「得意なこと」や「楽しくできること」を伸ばしてあげるのが大切 なんですよ!
失敗しないための親のサポート方法



せっかく始めた習い事を 途中でやめてしまうことは珍しくありません 。
でも、それは「失敗」ではなく、 子どもに合うものを見つける大切な過程 なんですよ!
続けやすい環境を整えるために、親ができるサポートはこちらです。
- 体験レッスンに参加する まずは気軽に試してみる
- 子どもの気持ちを大切にする 無理強いはせず、やりたくない理由を聞いてみる
- 成功体験を増やす 小さな「できた!」を積み重ねる
お母さんが「うちの子に合う習い事が見つかる!」と前向きな気持ちでいることが、何より大事 ですよ!
続けるための工夫とモチベーション維持のポイント



習い事を続けるためには、 「楽しさ」を保つ工夫 が大切です。
例えば、こんな方法がありますよ!
- 先生との相性をチェック 子どもが安心して通えるかが大事
- ごほうびシステムを取り入れる 楽しみながら頑張れる仕組みを作る
- 「嫌になった理由」を考える もしやめたくなったら、原因を整理してみる
習い事は「続けること」が目的ではなく、子どもが成長することが一番大切 です!
無理に続けるより、「次に合う習い事を探そう!」と前向きに考えましょうね。
この章では 「子どもに合った習い事の見つけ方」 についてお伝えしました!
次は 「発達障害の子どもが習い事でつまずく理由と対処法」 を解説していきます!
発達障害の子どもが習い事でつまずく理由と対処法
「せっかく習い事を始めたのに、子どもが嫌がる…」
「もう行きたくないって言われたけど、どうしたらいい?」
発達障害の子どもにとって、新しい環境に慣れるのは時間がかかるもの。
でも、 つまずく理由を知っておけば、適切な対処ができます!
ここでは、 習い事が続かない原因と、その対処法 を詳しくお伝えしますね。
習い事に馴染めない理由とは?



発達障害の子どもが習い事に馴染めないのには、いくつかの理由があります。
- 環境に慣れるのに時間がかかる 初めての場所や人に緊張してしまう
- ルールや指示が分かりにくい 曖昧な指示に戸惑い、混乱することも
- 思ったより難しくて自信をなくす 「できない」と感じると、やる気を失いやすい
「行きたくない」理由をしっかり聞いてあげることが大切!
子どもの気持ちに寄り添って、「何が嫌だったの?」と優しく聞いてみましょうね。
習い事を辞めるべき?続けるべき?



習い事を続けるか辞めるかを判断するポイントは 「本当に合わないのか」「一時的なものなのか」 です!
以下のように整理すると、判断しやすくなりますよ。
| 辞めるべき場合 | 先生やクラスメイトとの相性が悪い、環境がストレスになっている |
| 様子を見るべき場合 | 始めたばかりでまだ慣れていない、単なる気分の波 |
| 続けるべき場合 | 楽しんでいる時間もある、少しずつ成長している |
「やめる」ことは悪いことではなく、新しい道を見つけるチャンス!
「この習い事が合わなかっただけ」と前向きに考えましょうね!
習い事が合わないときの切り替え方



「この習い事は合わなかった」と分かったら、次の選択肢を探してみましょう!
習い事を切り替えるときに意識するポイントはこちらです。
- お試し体験を活用する いきなり始めず、体験レッスンで様子を見る
- 本人の意見を尊重する 「どんな習い事なら楽しめそう?」と聞いてみる
- 無理なく続けられるかを考える 通いやすさや負担の少なさも重要
子どもが「楽しそう!」と思えるものを見つけることが何より大事。
習い事は「続けること」よりも「子どもの成長」を優先しよう!
この章では 「習い事でつまずく理由と対処法」 についてお話しました。
次は 「発達障害の子どもと親の負担を減らす習い事の工夫」 について解説していきます!
発達障害の子どもと親の負担を減らす習い事の工夫
習い事は子どもだけでなく、お母さんにとっても負担がかかりますよね。
「送迎が大変…」「費用が高くて続けられない…」など、悩みは尽きません。
でも、 少しの工夫で親の負担を減らしながら、子どもが楽しく続けられる方法 があるんですよ!
ここでは、 親子の負担を軽減する習い事の工夫 を紹介しますね。
習い事の送迎や費用の負担を軽減する方法



送迎や費用が負担になっている場合、以下の方法を試してみてください!
- 近場の習い事を選ぶ 自宅から徒歩圏内や学校の近くなら負担が少ない
- 送迎サービス付きのスクールを利用 送迎バスやオンライン教室を活用する
- 自治体の補助を活用する 発達支援に関する助成金や割引制度がないか確認する
習い事は無理なく続けられる範囲で選ぶことが大切!
親の負担が少なければ、子どもも安心して通えますよ!
親子で楽しめる習い事の活用法



親子で一緒に楽しめる習い事なら、送迎の負担も減り、親子の時間も充実しますよ!
おすすめの「親子で楽しめる習い事」はこちら!
| 親子ヨガ | リラックスしながら体を動かせる |
| 親子クッキング | 食育にもなり、家庭での会話が増える |
| アート・工作教室 | 親子で創作する時間を楽しめる |
「親も楽しい」と感じる習い事なら、負担なく続けられる!
お子さんと一緒に成長できる習い事を選ぶのも良いですね!
オンライン習い事は発達障害の子どもに向いている?



最近は オンライン習い事 も増えてきましたよね!
発達障害の子どもにとって、オンラインの習い事は メリットもデメリットもある ので、特徴をよく知っておきましょう!
| メリット | 自宅で安心して受けられる、送迎が不要、自分のペースで学べる |
| デメリット | 対面でのコミュニケーションが少ない、集中が続きにくい |
特に プログラミングや英会話、アート系の習い事はオンラインでも学びやすい ですよ!
子どもの特性に合っていれば、オンライン習い事は便利な選択肢!
自宅で落ち着いて取り組めるなら、ぜひ活用してみてくださいね!
この章では 「親の負担を減らしながら続けられる習い事の工夫」 についてお伝えしました!
次は 「習い事を通じて得られる社会性と成功体験」 について解説していきます!
習い事を通じて得られる社会性と成功体験
発達障害の子どもにとって、 社会性を身につけることや成功体験を積むこと はとても大切ですよね。
でも、「うちの子はコミュニケーションが苦手…」と心配するお母さんも多いはず。
実は、 習い事は「楽しみながら社会性を学ぶ場」としても役立つ んですよ!
ここでは、 習い事を通じて得られる大切な力 についてお話ししますね。
習い事が子どもの自己肯定感を高める理由



発達障害の子どもは、「できないこと」に注目されがち。
でも、 「できた!」を積み重ねることで、自信がつく んですよ!
たとえば…
- 得意なことを見つけられる 「これは自分の特技!」と思えるものができる
- 小さな成功を積み重ねる 「やればできる!」という感覚を育てる
- 親からのポジティブな声かけ 「頑張ったね!」と褒められる経験が増える
「できた!」という経験を積むことが、自己肯定感を高めるカギ!
小さな成功をたくさん積み重ねられる習い事を選ぶのがポイントですよ!
仲間との関わり方を学ぶ機会としての習い事



習い事は、 自然な形で仲間と関わる練習ができる場 なんです!
特に、こんな習い事は コミュニケーションの機会を増やすのにぴったり ですよ!
| チームスポーツ | みんなと協力しながら楽しめる(サッカー、バスケットなど) |
| 演劇・ミュージカル | 役になりきることで自然に会話が増える |
| 習字・アート教室 | 個人作業もできつつ、友達との交流もある |
「みんなと協力する楽しさ」を経験できる習い事を選ぶと、社会性が育ちやすい!
「無理に関わらせる」のではなく、自然と会話が生まれる環境を作るのがコツですよ!
習い事がもたらす長期的なメリットとは?



習い事は 単なる趣味ではなく、子どもの未来にもつながる んです!
長期的に見て、習い事が子どもにもたらすメリットをまとめました!
- 将来の「好きなこと・得意なこと」につながる 習い事が職業や専門分野のきっかけになる
- 人と関わる力が自然に育つ 習い事を通じて協調性や自己表現が学べる
- 成功体験が自信につながる 「頑張ればできる!」という意識が将来の挑戦を後押しする
「好き」が見つかれば、子どもの未来はもっと広がる!
今の習い事が 将来の夢につながる可能性 もあるので、大切にしたいですね!
この章では 「習い事を通じて得られる社会性と成功体験」 についてお話しました。
次は 「発達障害の子どもが楽しく続けられる習い事の工夫」 について解説していきます!
発達障害の子どもが楽しく続けられる習い事の工夫
「習い事を始めたけど、すぐに飽きてしまう…」
「うちの子、最後まで続けられるか心配…」
そんな悩みを持つお母さんも多いですよね。
でも、 ちょっとした工夫で習い事がもっと楽しく、続けやすくなる んですよ!
ここでは、 発達障害の子どもが楽しく習い事を続けるためのポイント をお伝えしますね。
習い事が楽しくなる環境づくり



習い事が 「楽しい」と感じられるかどうか は、環境によって大きく変わります!
楽しく続けるために意識したいポイントはこちらです!
- プレッシャーをかけすぎない 「頑張らなきゃ!」ではなく、「楽しいから続ける」にする
- リラックスできる環境を作る 緊張しやすい子には、慣れ親しんだ場所で習えるオンライン教室もおすすめ
- 「楽しさ」を言葉で伝える 「今日は○○ができたね!」と、ポジティブな言葉をかける
「楽しさ」を大切にすることで、習い事が長続きする!
子どもが 「また行きたい!」と思える環境 を整えてあげましょうね!
指導者や先生との相性を見極めるコツ



発達障害の子どもにとって、 指導者や先生との相性はとても重要!
良い先生を見極めるためのポイントをまとめました!
| 子どもの特性を理解してくれる | 「この子に合った教え方」を工夫してくれる先生 |
| 怒らず、優しく指導する | ミスしても責めず、前向きな声かけをしてくれる |
| 子どものペースを尊重する | 「もっと早く!」ではなく、「ゆっくりでもOK」と見守ってくれる |
「子どもが安心できる先生」なら、習い事も長く続けやすい!
お試しレッスンなどで、先生の雰囲気をチェックするのがおすすめですよ!
失敗を前向きにとらえるマインドセット



習い事では「うまくできないこと」もありますよね。
でも、それを 「成長のチャンス」としてとらえること が大事なんです!
習い事での「失敗」を前向きにするための工夫はこちら!
- 「失敗も学び」と伝える 「できなかった」ではなく、「次はどうしよう?」と考える習慣をつける
- 「できたこと」に目を向ける 失敗よりも、小さな成長をたくさん褒める
- 「完璧じゃなくていい」と伝える 「楽しくできればOK!」のスタンスを持つ
「失敗」は「成長のチャンス」と考えれば、前向きになれる!
お母さんも「できた部分」に目を向けて、一緒に成長を楽しみましょうね!
この章では 「発達障害の子どもが楽しく続けられる習い事の工夫」 についてお話しました!
次は 「まとめ:発達障害の子どもに習い事を通じて得られる成長とは?」 です!
まとめ:発達障害の子どもに習い事を通じて得られる成長とは?
ここまで、発達障害の子どもにぴったりの習い事について詳しくお話ししてきました。
習い事は 「スキルを学ぶ場」だけでなく、「子どもが成長する場」 でもあります!
大切なのは、 お子さんが楽しみながら、自信をつけていける環境を作ること ですよね。
最後に、この記事のポイントを振り返ってみましょう!
- 子どもに合った習い事を選ぶことが大切
- 楽しみながら続けられる環境づくりが成功のカギ
- 習い事は自己肯定感や社会性を育む大切な場
子どもにとって「合う・合わない」はあるもの。
もし習い事が続かなくても、それは「失敗」ではなく 「もっとぴったりのものを探すチャンス」 です!
お母さんも焦らず、お子さんのペースで 「楽しく学べる環境」 を一緒に作っていきましょうね!
最後までお読みいただき、ありがとうございました!

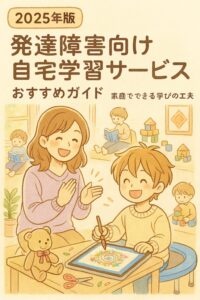
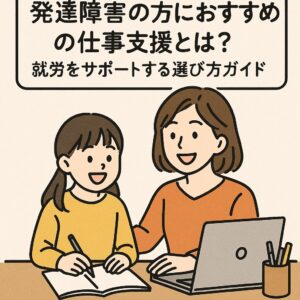


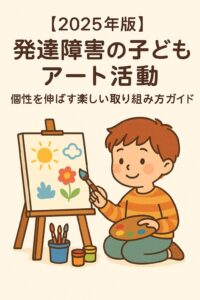



コメント