「発達障害がある子って、どうやって得意を伸ばしてあげればいいんだろう?」
そんなふうに悩んだこと、ありませんか?
子どもにはひとりひとり違った魅力や可能性があって、その「得意」を見つけてあげることができたら、それは子どもにとって一生の宝物になります。
とはいえ、得意をどう見つけて、どう伸ばしていくかって意外と難しいもの。でも大丈夫。この記事では、親としての関わり方や家庭での工夫、支援の活用法まで、すぐに取り入れられるヒントをたっぷりお伝えしますね。
どんな小さな得意も、大きな未来につながっていきます。一緒に、お子さんの「好き」や「得意」を見つけていきましょう!
- 発達障害の子どもの得意を見つけて伸ばす方法がわかる
- 親ができる声かけ・環境づくり・関わり方が具体的にわかる
- 支援機関や専門家とのつながり方・活用法がわかる
発達障害の子どもの「得意」に注目する大切さ

発達障害のある子どもたちは、苦手なことに目が向けられがちですよね。 でも実は、得意なことをうまく伸ばしていくことで、自信を持ったり、毎日が生きやすくなったりするんです。
特性ゆえに独自の感性や視点を持っていることも多く、その「得意」は大きな可能性を秘めています。「どうしてできないの?」ではなく、「何が好き?」「何が得意?」という視点で関わってみませんか?
ここでは、まず「得意」に注目する意義や、親がどう向き合えばよいかを考えていきますよ。
得意を伸ばすことが子どもの自己肯定感を育てる
自己肯定感って、子育ての中でもとても大切なキーワードですよね。 特に発達障害のある子は、できないことが周囲と比べて目立ってしまうことも多く、自信を失いやすい傾向があります。

たとえば、絵を描くことが大好きで集中力がある子。それを「すごいね!」「もっと描いてみようか!」と認めてあげるだけで、子どもはイキイキしていきます。
「得意」は自己肯定感を育て、子どもが前向きに生きる土台になります。
もちろん、すぐに得意が見つかるとは限りません。でも、日々の中で「何が好きか」「何に夢中になっているか」に目を向けてみると、きっとヒントが見えてきますよ。
「苦手の克服」より「得意を伸ばす」が優先の理由
親としては、「できないことをなんとかしてあげたい」って思いますよね。 でも実は、「苦手なことを頑張って克服する」よりも、「得意なことをぐんと伸ばす」ほうが、子どもにとっては自然で無理のない成長なんです。



もちろん、生活に支障があるような苦手は少しずつ慣れていく必要がありますが、最優先は「できる」「楽しい」と感じられる体験です。
たとえば、数字に強い子であれば、買い物でのお金の計算を任せてみる。文章を読むのが苦手でも、イラストや図で理解するのが得意なら、そっちを活かしてみる。
得意を起点にすることで、苦手へのアプローチも優しく、前向きなものに変わります。
周囲の大人が得意を見つける視点を持つには
子どもの得意を見つけるって、簡単なようでなかなか難しいものです。 でも、ちょっとした視点を変えるだけで、見えてくる世界がありますよ。



得意を見つけるためには、以下のようなポイントを意識してみてください。
- 繰り返し夢中になっていることゲームや絵、工作などに没頭している様子は、得意のサインかも
- 自然とできてしまうこと他の子が苦戦してもスムーズにこなせることは、才能の一つ
- 褒められたときの反応嬉しそうにしていたら、その活動に価値を感じている証拠
「これって、もしかしてこの子の得意かも?」というアンテナを日々の中で立てておくと、見逃さずにすみますよ。また、家族だけでなく、先生や支援員の方の視点も参考になります。
発達障害の子どもの得意を見つける方法


「うちの子、いったい何が得意なんだろう…?」って、ふと思うことありますよね。 でも、子どもの得意って、実は日常の中にたくさん隠れているんですよ。
ちょっとした行動や言葉にヒントがあるので、それをどうキャッチしていくかがカギになります。ここでは、親が今日からできる「得意の見つけ方」をご紹介していきます。
日常生活や遊びの中からヒントを見つけよう
得意を見つけるって、特別な検査をしないといけないわけじゃありません。 むしろ、毎日の中にこそヒントが詰まっているんですよ。



たとえば、ブロック遊びを延々とやってる子。それって、空間認識や創造力が優れているサインです。歌を何度も繰り返し聞いて覚えていたら、音感や記憶力が得意かもしれません。
日常の「好き」「夢中」「得意そうかも」を見逃さないことが大切です。
また、親子の会話の中でもヒントがあります。「楽しかったこと」「またやりたいこと」を聞いてみてください。その中に、得意のタネがきっと見つかりますよ。
チェックリストで得意傾向を整理してみよう
感覚だけで「得意かな?」と判断するのはちょっと不安…。 そんなときは、チェックリストで傾向を整理してみるのがおすすめです。



以下のような項目を、当てはまるかチェックしてみてください。
- 好きなことには長時間集中できる夢中になって取り組む姿がよく見られる
- パターンやルールに強い数字や順番、地図、スケジュールが得意
- 五感が鋭い音や匂いに敏感、色彩感覚が優れている
- 人とのやりとりが得意会話が好き、人に教えるのが上手
いくつか当てはまった項目があれば、それがその子の得意の入り口かもしれません。このチェックは、親だけでなく学校の先生や支援者と一緒にやるのも効果的ですよ。
他の子との比較ではなく「その子らしさ」を見る
つい、他の子と比べてしまう…それ、親なら誰でもありますよね。 でも、発達障害のある子は特に「その子らしさ」が大事なんです。



得意は「その子の個性」なので、比べる必要はないんです。むしろ、「うちの子にはこういういいところがある」って発見することが、親子の関係にも良い影響を与えます。
たとえば、人見知りであまり話さない子でも、じっくり考えてから意見を言う慎重さがあるかもしれません。落ち着きがないように見えても、好奇心旺盛で観察力が高いのかもしれません。
「他と違う=ダメ」ではなく、「その子らしい=素晴らしい」と捉えることが大切です。
親がその視点で見ることで、子ども自身も「このままでいいんだ」と安心できるんですよ。
具体的な「得意の例」と伸ばし方の実践アイデア


「得意を伸ばそう!」って言われても、実際にどう関わればいいの?って思っちゃいますよね。でも大丈夫。 子どもの「好き」や「得意」に合わせた関わり方って、ちょっとした工夫でできるんですよ。
ここでは、よく見られる得意のタイプ別に、関わり方や伸ばし方のアイデアを紹介していきます。きっと「これ、うちの子にぴったりかも!」って思えるヒントが見つかるはずです。
絵が得意な子のサポート法
絵を描くのが好きな子っていますよね。 紙と鉛筆があればずっと夢中…そんな姿を見ると、親としても嬉しくなりますよね。



絵が得意な子には、以下のような関わり方が効果的です。
- 画材をいろいろ用意してみるクレヨン、水彩、色鉛筆など、表現の幅が広がると楽しくなります
- 作品を飾ってあげる「認められてる」と実感できることで、描く意欲がどんどん高まります
- テーマを決めて一緒に描くお題を出すと新しい表現に挑戦できて、創造力も伸びます
また、美術館に連れて行ったり、他の人の作品に触れる機会を作るのもおすすめです。「自分にもできるかも!」って感じる体験が、次のステップにつながっていきます。
数字・論理が得意な子の伸ばし方
数字やパターンに強い子もいますよね。 電車の時刻表を覚えたり、パズルをスラスラ解いたり。 これって立派な「得意」なんです。



このタイプの子には、論理的な思考力を活かせるような関わり方がおすすめです。
- ボードゲームや数字系パズルを一緒にやってみる遊びながら論理的思考力を育てられます
- ルールを自分で作らせてみる「オリジナルゲーム作ってみようか!」なんて声かけが効果的です
- 生活に数字を取り入れる買い物の合計を計算してもらうなど、実生活との結びつきが理解を深めます
「なんでそうなるの?」と聞いて、考えを説明させることも思考力を育てるコツです。その子なりのロジックを大事にしてあげてくださいね。
人との関わりが得意な子の活かし方
「この子、ほんとにおしゃべり好きだな~」なんて思うこと、ありませんか? 実はそれ、人との関わりに才能がある証拠かもしれません。



そんな子には、人との関わりを楽しめる機会を意識的に作ってあげましょう。
- 係活動や役割を任せる責任感を持って取り組むことで自信が育ちます
- 小さな子と関わる場を作る自然とリーダーシップや思いやりが育ちます
- お話しの舞台を作る発表会ごっこや司会体験などで、「伝える力」を伸ばせます
人と関わることが好きな子は、社会での適応力が高くなる傾向があります。その得意を、日常の中でたくさん使わせてあげたいですね。
環境づくりが子どもの才能を引き出すカギ
「得意を伸ばしたい」と思ったとき、大人の声かけや接し方ももちろん大切ですが、実は環境もとっても重要なんですよ。 子どもが安心して自分を出せる環境があると、それだけで伸び方がまるで変わってきます。
おうちの中、園や学校、そして周囲の人たちとの関係。ちょっとした工夫で、子どもが自分らしさを発揮できる空間になりますよ。
家庭でできる環境づくりの工夫
「うちで何かできることってあるかな?」と思いますよね。 実は、家庭は子どもにとって一番安心できる場所だからこそ、ちょっとした変化が大きな影響をもたらすんです。



以下のような工夫を取り入れてみるといいですよ。
- 得意を表現できるスペースを作るお絵描きコーナーや工作棚など、自由に使える場所を用意する
- スケジュールを可視化する見通しが立つと安心し、集中しやすくなる
- 静かに過ごせる時間帯をつくる感覚過敏の子には特に、静かな環境が力を発揮するカギに
また、「できたね」「すごいね」などの肯定的な言葉をかけてあげるだけでも、子どもの気持ちはグッと前向きになりますよ。
学校や園との連携をスムーズにするには
家庭だけでなく、学校や園での過ごし方も得意を伸ばすには大事な要素です。 ただ、家庭と教育現場では情報共有がうまくいかないこともありますよね。



以下のような連携の工夫が効果的です。
- 連絡帳や面談で具体的に共有「家ではこういうことに夢中です」などの具体例を伝える
- 無理に合わせさせない「みんなと同じように」ではなく、その子らしく過ごせる環境を希望する
- 先生との信頼関係を築くまずは「いつもありがとうございます」と感謝の気持ちを伝えるところから
先生も親の協力があると、支援がしやすくなります。お互いの理解が深まれば、子どもも安心して過ごせますよ。
発達障害の特性に配慮した空間・時間設計
発達障害のある子は、音や光、人の声などに敏感だったり、同じ動作を繰り返したりする傾向がありますよね。 そんな子どもが「得意」を発揮するには、周囲の環境がとっても大きな影響を与えるんです。



環境を工夫するポイントを以下にまとめました。
- 照明の明るさや音の大きさを調整落ち着ける空間づくりが集中力を高める
- リズムあるスケジュール同じ時間に同じ行動をすると安心して動ける
- 一人になれる時間・場所を用意刺激が強くなったときの「逃げ場」があると安心
特性に合わせた空間や時間のデザインが、「落ち着いて力を発揮できる」状況を生み出してくれるんです。これも立派な支援のひとつですね。
得意を伸ばすための親の関わり方とは?
発達障害の子どもにとって「得意」を伸ばすには、やっぱり親の関わりがとっても大切なんです。 子どもが安心して「自分らしさ」を発揮できるように、親の声かけや姿勢が大きく影響してきますよね。
でも、特別なことをする必要はありません。ちょっとした工夫や意識で、毎日の関わりの中に変化が生まれますよ。
子どもの気づきを引き出す声かけのコツ
子どもに「これが得意なんだよ!」って教えてあげるのも大事ですが、 自分自身で「これ好きかも」「やってみたいな」と気づけたら、もっと自信になりますよね。



そのための声かけのコツをいくつかご紹介します。
- 「どうしてそれが好きなの?」と聞いてみる好きな理由を言語化することで、自覚が深まります
- 「今のすごく上手だったね」と具体的に褒める何が良かったのかを伝えると、自信に直結します
- 「他にもやってみたいことある?」と広げる得意をきっかけに新しい世界に目を向けるきっかけになります
大事なのは、正解を教えるよりも、子ども自身が考えるきっかけを作ることなんです。そうすることで、自発的な「伸びたい」という気持ちが芽生えていきますよ。
褒め方・認め方で子どもは変わる
褒め方ひとつで、子どもってガラッと変わりますよね。 特に発達障害のある子は、自分に自信が持てず不安になりやすいからこそ、褒めること・認めることがとても重要なんです。



褒めるときのポイントは以下の通りです。
- 行動を具体的に褒める「最後までやったね」「静かに聞けたね」など、できた行動を明確に伝える
- 努力のプロセスに注目する「昨日より丁寧だったね」など、結果だけでなく頑張った過程を評価する
- 本人のペースを尊重する「ゆっくりでいいよ」「あなただけのやり方があるんだね」と伝える
認められる経験が増えると、子どもは自分からチャレンジするようになります。「またやってみよう!」と思えるような関わり方を意識したいですね。
親自身の「気づき」を深めるには
「この子にとって何が得意なんだろう?」「どう関わったらいいんだろう?」 悩んだり、迷ったりすることもありますよね。 でも実は、親が自分自身の気づきを深めていくことも、子どもにとってとっても大事なんです。



親自身が気づきを得るための方法はこちらです。
- 子育て日記をつけてみる小さな変化や気づきを文字にすることで、自分の思考が整理されます
- 他の親と交流してみる同じ悩みを持つ人の話を聞くだけでも、気づきや安心感につながります
- 一人の時間を大切にする自分の気持ちと向き合う時間があると、冷静に子どもと接することができます
「子どものために」と思ってがんばる親ほど、自分のケアを忘れがちです。まずは自分自身を大切にすることから、始めてみてくださいね。
失敗やつまずきも「成長のヒント」に変える
得意を伸ばす中で、うまくいかないことやつまずくことも、もちろんありますよね。 でも、それって実は成長のチャンスでもあるんです。
子どもにとって失敗は「ダメなこと」じゃなくて、「次につながるヒント」。そんなふうに捉えてあげることで、子どもはどんどん前に進めるようになりますよ。
子どもが壁にぶつかったときの対応法
どんな子でも、夢中になっていたことがうまくいかなくなる瞬間ってありますよね。 そんなとき、どんな言葉をかけて、どう関わってあげるかがとっても大事なんです。



まず大切なのは、感情を否定しないことです。「そうか、悔しかったんだね」「うまくいかなくて悲しかったんだね」と、まずは気持ちを受け止めてあげましょう。
その上で、以下のような対応が効果的です。
- 「どうすればよかったかな?」と一緒に考える失敗を振り返る力が自然と育ちます
- 「チャレンジしたことがすごいよ」と伝える結果よりも挑戦した姿勢を認めることで、前向きな気持ちが持てます
- 次の機会を明確に示す「また来週やってみようね」と伝えることで希望が生まれます
失敗の経験も、関わり方ひとつで「成長のきっかけ」に変わります。
うまくいかなかった経験を活かす視点
「せっかく得意を伸ばそうとしてるのに、うまくいかない…」と落ち込むこともありますよね。 でも、実はその経験の中にこそ、次のヒントが隠れているんです。



たとえば、発表の練習をがんばっていたのに、当日緊張して声が出なかった…そんなときも、
「練習していたことはすごいね」「緊張しても舞台に立ったことがすごい」と視点を変えて伝えてあげましょう。
また、「どうしてうまくいかなかったのか」を一緒に整理してみると、次につながる気づきが生まれます。
- 振り返りの時間を持つ「あのときどう感じた?」とゆっくり話すことで、気持ちを整理できます
- 本人の気づきを尊重する「ママはこう思うけど、あなたはどう思った?」と問いかけることが大事
- 小さな改善を一緒に考える「次は準備をちょっと早くしてみようか」など、できそうなことから始める
「失敗しても大丈夫」って思える環境が、挑戦する気持ちを育てます。
一緒に悩み、寄り添うことの価値
「親なんだから、しっかりしなくちゃ」「正しいアドバイスをしなくちゃ」って思いがちですが、 実はそれよりも大切なのは、子どもと一緒に悩む姿勢なんです。



寄り添い方のポイントは以下のとおりです。
- 完璧な答えを出そうとしない一緒に考える時間そのものが、子どもの安心につながります
- 「どう感じてる?」と気持ちを尋ねる気持ちを言葉にすることで、自分自身を理解する力が育ちます
- 「ママも前にこういうことがあったよ」と経験をシェアする自分だけじゃないと知ることで、子どもは前を向けます
子どもと一緒に悩んでくれる親がいることが、何よりの安心材料になります。寄り添う気持ちこそ、最高のサポートなんですね。
支援機関や専門家とつながるメリット
「家庭だけで頑張るのはちょっと大変…」そう感じること、ありませんか? 実は、得意を伸ばすサポートって、親だけじゃなく支援機関や専門家の力を借りることで、グッと効果が上がるんですよ。
「ちょっと相談してみようかな?」と気軽に頼れる場所を知っておくことは、親にとっても子どもにとっても安心につながります。ここでは、頼れる人や場所とのつながり方をご紹介していきますね。
専門家に相談するタイミングと方法
「これって相談していいのかな?」って迷っちゃうこと、ありますよね。 でも、ちょっとした不安や違和感こそ、相談のサインなんです。



相談していいタイミングはこんなときです。
- 得意や苦手のバランスが極端なとき家庭だけでは対応しきれないと感じたとき
- 親子でストレスがたまっているときイライラや不安が続くようなら、気持ちの整理にプロの力を
- 進学や進路の悩みが出てきたとき「この子に合う選択肢は何だろう」と迷ったら専門家と一緒に考えましょう
相談先としては、以下のようなところがあります。
| 児童発達支援センター | 発達の相談・支援をしてくれる場所。発達検査なども受けられることが多いです |
| 療育機関 | 子どもに合わせた支援プログラムで、得意や特性を伸ばす関わりをしてくれます |
| 発達相談員・臨床心理士 | 気軽に話を聞いてもらえる相談相手として、とても心強い存在です |
支援施設・サービスの活用法
「支援って、なんか特別な感じがして…」と思っていませんか? でも実際は、とっても身近で使いやすいサービスがたくさんあるんですよ。



たとえば、放課後等デイサービスや児童発達支援などは、遊びや学びの中で得意を伸ばす活動を行っている場所です。支援施設を使うと、こんなメリットがあります。
- 専門的な視点で子どもを見てもらえる親では気づけない「得意」に気づいてもらえることも
- 安心して過ごせる場所が増える家以外にも「自分らしくいられる場所」があるのはとても大切
- 他の子との関わりが経験できる集団の中での振る舞いや社会性を育てるチャンスになります
利用の際は、まず市区町村の障害福祉課などに問い合わせるとスムーズですよ。
同じ悩みをもつ親との交流も力になる
「こんなふうに思ってるの、私だけ?」 そう思い込んでしまうこと、ありますよね。 でも、同じように悩んでいる親と話すことで、驚くほど心が軽くなるんです。



親同士のつながりには、こんな良いことがあります。
- 「うちもそうだったよ」と共感してもらえる一人じゃないと思えることで気持ちがラクに
- 実際に役立つ情報が手に入る病院やサービスの情報、具体的な対処法などのシェアができます
- 気軽に話せる場所ができるちょっとした愚痴や不安を言える場があるだけでも救われます
地域の親の会や、SNSでのグループなど、探してみると意外と近くに仲間がいるかもしれませんよ。
まとめ:子どもの得意は未来へのギフト
発達障害があるからこそ、子どもたちはユニークで魅力的な得意を持っていることが多いんです。 それを見つけて、伸ばしてあげられるのは、やっぱり一番そばにいるお母さんやお父さんなんですよね。
「苦手なことにどう向き合うか」も大切ですが、まずは「この子が好きなこと」「楽しそうにしてること」「夢中になってること」に目を向けてみませんか?



そのギフトを一緒に見つけて、一緒に育てていく。そんな日々が、子どもだけじゃなく、親にとっても幸せな時間になるはずです。
焦らず、比べず、その子らしいペースで。今日からまた、少しずつ、前に進んでいきましょうね。
- 子どもの得意を伸ばすことは、自己肯定感の土台をつくることにつながる
- 親の関わり方や環境づくりで、得意がもっと輝き出す
- 支援機関や仲間とのつながりも、親子の力強い味方になる




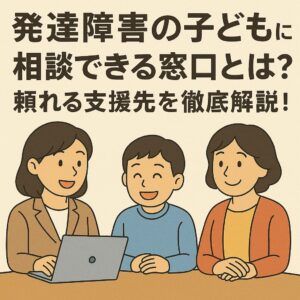

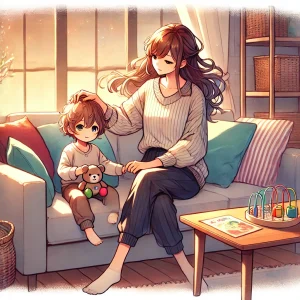

コメント