発達障害を持つお子さんにとって、習い事は自己肯定感や社会性を育む大事な機会ですよね。
でも、「うちの子に合う習い事ってなんだろう?」「続けられるか心配…」と不安になることもあるのではないでしょうか。
そんなママたちに向けて、この記事では発達障害の特性に配慮しながら、子どもにぴったりの習い事を選ぶコツや、おすすめの習い事を具体的に紹介していきます。
無理なく楽しく続けられる習い事を見つけて、お子さんの笑顔を増やしてあげましょう。
- 発達障害の子どもに合う習い事の選び方が分かる
- 特性別におすすめの習い事を詳しく紹介
- 無理なく続けるための工夫も解説
1. 発達障害の子どもに習い事を選ぶときのポイント

発達障害のある子どもにとって、習い事はスキルアップだけでなく、自己肯定感を育てる大切な場になりますよね。
ですが、お子さんの特性に合わない習い事を選んでしまうと、かえってストレスや不安の原因になることもあります。
ここでは、発達障害のあるお子さんにぴったりの習い事を選ぶために大切なポイントを解説します。
1-1. 子どもの特性や興味をよく観察する
お子さんの「得意」「苦手」や「好きなこと」「こだわり」などを、日々の生活の中でじっくり観察することが第一歩です。
たとえば、落ち着いてじっとしているのが苦手なお子さんには、じっと座って学ぶ習い事よりも、体を動かす活動が合っているかもしれません。
また、音に敏感なお子さんには、静かな環境でできる習い事のほうがストレスが少なくなりますよ。
子どもが興味を持って楽しめるかどうかが続けられるかのカギになります。

1-2. 指導者の理解や教室の柔軟さもチェック
発達障害の子どもにとって、先生との相性や教室の雰囲気もとっても大事です。
発達障害に対する理解がある指導者のもとでは、お子さんが安心して取り組むことができます。
一方で、決まりきったやり方を押しつける教室だと、戸惑いや不安で通えなくなってしまうことも。
体験教室や見学を通して、先生の雰囲気やお子さんの反応をしっかり見てから決めるのがおすすめです。
「うちの子に合わせてくれる」教室かどうか、しっかり見極めましょう。



2. 発達障害の子どもにおすすめの習い事


ここからは、発達障害のある子どもたちにおすすめの習い事を具体的にご紹介していきますね。
習い事の種類によって、得られる効果も異なります。
大切なのは、「子どもが興味を持てるかどうか」と「無理なく続けられる環境かどうか」です。
それぞれの習い事の特徴や、どんな子に向いているのかも合わせてお伝えします。
2-1. 音楽系(ピアノ・ドラム・リトミックなど)
音楽は、発達障害の子どもにとって「自分を表現する手段」にもなりますよね。
ピアノやドラムなどの楽器は、集中力や手先の協調運動を育てるのにもピッタリです。
また、リズムに合わせて体を動かすリトミックは、言葉の発達や身体感覚にも良い影響があるとされています。
先生との一対一のレッスンなら、他の子を気にせず自分のペースで取り組めるのも魅力です。
音楽に触れることで、自己肯定感や集中力を育てられるんですよ。



2-2. スポーツ系(水泳・体操・ダンスなど)
体を動かす習い事は、エネルギーが有り余っているタイプのお子さんには特におすすめです。
水泳は浮力が働くので、感覚過敏のある子どもでもリラックスしやすいと言われています。
体操やダンスは、身体のバランス感覚やリズム感を養うだけでなく、ルールや順番を覚える練習にもなりますよ。
「失敗してもOK」という雰囲気のある教室を選ぶと、子どももチャレンジしやすくなります。
楽しく体を動かすことで、気分の安定や社会性の育成にもつながります。



3. 習い事を続けるための工夫


習い事を始めても、「続けられるかどうか」がやっぱり一番心配なポイントですよね。
特に発達障害のある子どもは、環境の変化や疲れやすさなどの影響を受けやすいので、ちょっとした工夫が長続きのカギになります。
ここでは、習い事を無理なく続けるためのコツをお伝えします。
3-1. 目標は小さく、できたら褒める!
習い事を続けるには、「できた!」という実感を積み重ねることが大切です。
最初から「完璧にやる」のではなく、「5分座っていられた」「今日は泣かずに教室に入れた」など、小さな成功体験を目標にするといいですよ。
その都度、「よく頑張ったね」「ママ嬉しいよ」って、たっぷり褒めてあげてください。
できたことに注目することで、子どものやる気がどんどん育っていきます。



3-2. 習い事の前後はゆったりとした時間を
習い事の直前や直後に予定が詰まっていると、子どもにとっては大きな負担になります。
移動中に疲れてしまったり、焦って準備したりすると、習い事どころではなくなっちゃいますよね。
時間に余裕を持って、ゆったりとした気持ちで通えるようにスケジュールを調整してあげましょう。
「無理せず、焦らず」も習い事を長く続けるための大事なポイントです。



4. 習い事に向いている時期と始めどき
習い事を始めるタイミングって、いつがいいのか悩みますよね。
特に発達障害のあるお子さんの場合、早く始めすぎてもついていけなかったり、本人にとってストレスになったりすることもあります。
焦らず、その子の「準備ができたサイン」を見逃さないことが何より大切なんですよ。
4-1. 子どもが「やってみたい」と言ったとき
いちばんのベストタイミングは、やっぱりお子さんが自分から「やってみたい!」と言ってきたときです。
このときは興味や関心が高まっているので、取り組む意欲も大きくなっています。
無理にやらせるよりも、本人の「やってみたい」という気持ちを尊重してあげるのが長続きのコツです。
また、言葉でうまく伝えられなくても、チラシを見て興味を示したり、兄弟姉妹の習い事を羨ましがったりする様子があれば、それも立派なサインですよ。
本人の「やってみたい」が出たときが、始めどきなんです。



4-2. 環境が落ち着いているタイミングを選ぶ
もうひとつ大事なのが、子どもの生活環境が安定しているときに始めることです。
たとえば、引っ越しや転校、入学・進級など、大きな変化のある時期は避けた方が安心です。
お子さんが不安定になっている時期に新しい習い事を始めると、慣れるのに時間がかかったり、拒否感が強く出てしまったりすることもあります。
普段の生活リズムが安定していて、体調も良く、気持ちも落ち着いているタイミングを選んであげましょう。
子どもの心が落ち着いているときに始めると、スムーズに慣れていけますよ。



5. 習い事選びでやってはいけないNG行動
「よかれと思ってやったのに、うまくいかなかった…」という経験、ありませんか?
発達障害のある子どもの場合、習い事選びを間違えると、本人が傷ついたり、自信を失ってしまうことにもなりかねません。
ここでは、やりがちなNG行動を知って、後悔しない習い事選びをしていきましょう。
5-1. 「周りの子がやってるから」と無理に選ぶ
「お友達がピアノ習ってるから」「みんながサッカーしてるから」といった理由だけで習い事を決めてしまうのは、実はちょっと危険なんです。
その子に合っていないと、ストレスになってしまい、結局続かなくなることもあります。
何より、子ども自身が「比べられている」と感じてしまうこともあるので注意が必要です。
「うちの子に合っているかどうか」を最優先に考えてあげましょう。



5-2. 子どもが嫌がっているのに無理に通わせる
習い事を嫌がる子どもに無理やり行かせるのは、逆効果になることが多いです。
「怒られる」「できない自分がつらい」と感じてしまうと、習い事そのものが嫌いになってしまいます。
まずは、なぜ嫌がっているのかをよく聞いてみてください。理由がわかれば、解決できることも多いんですよ。
子どもの気持ちに耳を傾けて、一緒に解決策を探すことが大切です。



6. 習い事を選ぶ際に保護者ができるサポート
習い事を選ぶとき、やっぱり保護者の関わり方がとっても大切ですよね。
発達障害のあるお子さんは、自分の気持ちをうまく言葉にできなかったり、新しいことへの不安が強かったりします。
そんなときに、おうちの方がそばで寄り添ってサポートしてくれると、子どもは安心して挑戦できます。
6-1. 体験レッスンを一緒に楽しんでみる
どんな習い事が合っているのか分からないときは、まずは体験レッスンを受けてみましょう。
実際に体験することで、子どもがどんな表情をするのか、どんな反応をするのかが分かります。
「どうだった?」「楽しかった?」と聞くだけでなく、ママ自身も一緒に楽しむ気持ちで参加してみてくださいね。
体験レッスンは、子どもの「好き」と「無理」を見極めるチャンスです。



6-2. 習い事後のフォローで気持ちを支える
習い事から帰ってきたあとは、子どもの気持ちにしっかり寄り添ってあげましょう。
うまくできた日は思いっきり褒めてあげて、うまくいかなかった日は「よく頑張ったね」と受け止めてあげてください。
また、レッスン内容を一緒に振り返るのもおすすめです。
「今日は何やったの?」「面白かったところはどこ?」と聞いてあげることで、子ども自身も気持ちを整理しやすくなりますよ。
習い事のあとにかける一言で、子どものやる気はぐんと変わります。



7. 発達障害の特性別・おすすめの習い事まとめ
ここでは、発達障害の特性ごとに、どんな習い事が向いているのかをまとめてみました。
子どものタイプに合わせて、習い事選びの参考にしてみてくださいね。
7-1. ADHDタイプの子におすすめ
ADHDタイプのお子さんは、じっとしているのが苦手だったり、衝動的な行動が目立ったりしますよね。
そんなお子さんには、体を動かせる習い事や、短時間で区切りがつく活動がおすすめです。
- 体操・ダンスリズムに合わせて自由に動ける
- 水泳全身を使って運動でき、集中力もUP
- 絵画教室思いつくままに自由に表現できる
動きながら学べるスタイルが、ADHDの子にはピッタリなんですよ。



7-2. ASDタイプの子におすすめ
ASD(自閉スペクトラム症)の子は、感覚の敏感さやこだわりの強さがある反面、集中力が高いという特徴もあります。
そんな特性を活かせるような、静かで一人で集中できる習い事が向いています。
- ピアノ・バイオリン繰り返し練習でき、成果が見えやすい
- 書道・習字静かな環境で集中して取り組める
- パズルやロボット教室論理的思考や手順の理解を活かせる
「ひとりで集中できる環境」を用意してあげるのがポイントです。



8. まとめ
発達障害を持つお子さんにとって、習い事はただの「習い事」ではなく、自己肯定感を育てたり、社会とのつながりを築いたりする大切な機会ですよね。
とはいえ、習い事の選び方や続け方には悩むことも多いと思います。
この記事でご紹介したように、子どもの特性や「好き」の気持ちを大切にしながら、無理のないスタートを切ることが大切です。
そして、何よりもお子さんが「楽しい!」と感じてくれることが、一番の成功のカギになります。
焦らず、比べず、子どもと一緒に成長していく気持ちで、習い事ライフを楽しんでくださいね。
- 習い事は子どもの特性と興味を最優先に選ぶのがポイント
- 保護者のサポートや声かけが、やる気と継続のカギ
- 失敗しても大丈夫。子どもと一緒に試していく姿勢が大切




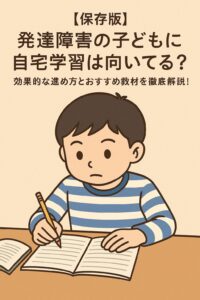


コメント