「うちの子、ゲームや動画は大好きなんだけど…勉強や集団行動がちょっと苦手で…」なんて思ったこと、ありませんか?
発達障害の子どもたちは、個性や感性がとても豊かですよね。
でも、その特性が学校や習い事でうまく活かされないと、親としても悩むことが増えてしまいます。
そんな中で注目されているのが「YouTube編集」という学び方。
自分のペースで進められて、好きなことを形にできる——そんな魅力がたくさん詰まっているんです。
今回は、発達障害の子にYouTube編集がおすすめな理由や、はじめ方、注意点などを詳しくご紹介します。
- 発達障害の子どもがYouTube編集に向いている理由がわかる
- どんなスキルが身につくのかが見えてくる
- はじめやすい環境や注意点も理解できる
1. 発達障害の子どもとYouTube編集の相性は?

発達障害の子どもたちは、得意・不得意の差が大きく、学校や習い事の場面で困りごとが出てくることも多いですよね。
でも、その「得意」をうまく活かせるのが、実はYouTube編集なんです。
自分のペースで取り組めて、好きなことを形にできるこの活動は、発達障害の子にとって「向いている」ポイントがたくさん詰まっています。
ここでは、YouTube編集と発達障害の子どもの特性がどのようにマッチするのか、わかりやすく解説していきますね。
1-1. なぜ今「YouTube編集」なのか?
今やYouTubeは、子どもたちが日常的に触れているメディアですよね。
「見る」だけでなく、「自分も作ってみたい!」と思う子が増えているのも納得です。
そしてその「作る」部分こそが、実は発達障害の子の才能を引き出すチャンスなんです。
- 自分のペースで進められる周囲に合わせる必要がなく、集中しやすい
- 好きなテーマで作れるゲーム・工作・ペットなど興味に直結した動画が作れる
- 完成したときの達成感が大きい「できた!」という体験が自信につながる
YouTube編集は、「好きなこと」をきっかけにスキルが自然と育つ学びなんです。

1-2. 発達障害の子どもに見られる特性とは
発達障害とひとことで言っても、ASD(自閉スペクトラム症)やADHD(注意欠如・多動症)など、子どもによって特性はさまざま。
共通して見られる特徴としては、次のようなものがあります。
- 感覚に敏感大きな音や強い光にストレスを感じやすい
- 集中と分散の差が大きい好きなことには没頭するが、苦手はスルーしがち
- マイペース周囲のスピードに合わせることが苦手な傾向
学校や集団行動ではつまずくこともあるけれど、これらの特性が活かされる場面もちゃんとあるんですよ。



1-3. YouTube編集が得意とする特性とのマッチング
YouTube編集は、まさに「自分の世界」に入り込める作業。
発達障害の子どもが持つ「集中力」や「こだわり」を存分に活かすことができます。
たとえば、音や映像に敏感な子は、「ここはもっと静かに」「この色は落ち着く」といった感覚を編集に反映できますし、細かい部分へのこだわりも強みに変わります。
また、完成した動画が「自分の作品」として形に残ることは、大きな達成感につながるんです。
評価や比較ではなく、「自分らしさ」を表現できる環境だからこそ、自己肯定感も育ちやすいんですよ。



2. YouTube編集で身につくスキルとは?


「好きなことだから続けられる」って、習い事選びではとても大事な視点ですよね。
YouTube編集は、ただ楽しいだけじゃなくて、将来に役立つスキルもしっかり身につくんです。
今回は、編集を通して子どもが自然に育てていける力についてご紹介します。
2-1. 集中力や持続力が育つ理由
YouTube編集の作業って、意外と根気がいるんです。
カット、並び替え、BGMの挿入、テロップづけなど、やることはたくさんあります。
でも、好きな内容の編集であれば、子どもたちは夢中になって取り組めるんですよね。
「うちの子、落ち着きがないのに、動画編集だと2時間集中してた」なんて話もよく聞きます。
- 好きな作業だから没頭できる義務感ではなく、自発的に集中が続く
- 達成感が次への意欲になる完成したときの満足感が次のチャレンジへ
- 作業の流れを覚えるルーティン化することで安定した集中が可能に
「集中できた経験」が、ほかのことにも活きてくるのが嬉しいですよね。



2-2. 構成力・表現力が自然と身につく
動画編集では、「どう見せたら伝わるか?」を考える力が必要になります。
「ここで文字を出そう」「この場面で音を変えよう」など、工夫を重ねながら動画を組み立てていくので、自然と構成力が養われるんです。
また、「自分の伝えたいことを、どう伝えるか?」という視点が育ち、表現力にもつながります。
- 論理的に流れを考える力「順序立てて組み立てる」思考が身につく
- 視聴者を意識する感覚「どう見えるか」を考える力が伸びる
- 自己表現の方法が増える言葉以外でも自分を伝える手段が持てる



2-3. 人と関わらずに達成感を味わえる環境
発達障害の子どもにとって、「人と一緒に」や「人前で発表する」って大きなハードルだったりしますよね。
でも、YouTube編集なら、自分ひとりで完結できる作業だから、安心して取り組めるんです。
そして出来上がった作品は、ネット上に公開することで人からの反応が得られるというごほうびもついてきます。
誰かと競ったり、無理して話したりする必要がない環境は、発達障害の子にとってとても貴重なんです。
「自分のペースでできる」って、ほんとうに大きな強みなんですね。



3. YouTube編集がもたらす将来の可能性


「どうせ遊びでしょ?」と思われがちなYouTube編集ですが、実は将来を見据えた「立派なスキル」でもあるんですよ。
発達障害の子どもたちにとって、将来の選択肢を広げておくことはとても大切です。
ここでは、YouTube編集が将来どんなふうに役立つかについてお話ししていきますね。
3-1. 将来的な仕事の選択肢が広がる
動画編集は今、需要が高まっている分野のひとつです。
企業のPR動画やSNS用の短編動画、教育系コンテンツなど、編集のスキルを必要としているところはたくさんあるんですよ。
将来的に、「動画編集者」「コンテンツクリエイター」として活躍できる道が見えてきます。
発達障害の子が自分の強みを活かして働ける未来を作るきっかけにもなるんです。
- スキルとしての価値が高い動画編集は社会的にも需要が高い技術
- 実績として残しやすいポートフォリオとして動画をそのまま使える
- 発達特性に合った働き方も可能人との関わりを最小限にしながら仕事ができる
「好き」から始めたことが、「職業」になる可能性があるって、すごく素敵なことですよね。



3-2. 在宅ワークやフリーランスという働き方も
発達障害のある子が将来、働きづらさを感じることって、やっぱりありますよね。
そんなとき、時間や場所に縛られない「在宅ワーク」や「フリーランス」という働き方は、心強い選択肢になります。
YouTube編集は、パソコンとネット環境さえあれば自宅で完結できる仕事。
通勤や人間関係のストレスを避けながら、自分のスタイルで働けるのが魅力なんです。
- 自分のペースで働ける無理のないスケジュールで仕事ができる
- 人と直接関わらなくてもOKコミュニケーションが苦手でも安心
- 体調や気分に合わせて調整可能自分のリズムで働く環境が整いやすい



3-3. 「好き」を仕事にできる未来へ
発達障害の子どもたちが、自分の「好き」を認めてもらい、それが「仕事」になるって、本当に素敵なことだと思いませんか?
動画編集を通じて、「伝える」「表現する」楽しさを知ることで、「好き」から始まった学びが、やがて「自分の武器」に変わっていくんです。
何より、子どもが自分の力で何かを生み出し、それが誰かに届くという経験は、かけがえのない成長になります。
「自分の好きが誰かの役に立つ」——そんな未来を目指せる学びなんですね。



4. どんな編集内容から始めるのがいい?
YouTube編集って、「難しそう」と感じるかもしれませんが、最初からすごい動画を作る必要はないんですよ。
大事なのは、「できた!」という成功体験を積み重ねていくこと。
ここでは、発達障害の子どもが無理なく楽しく取り組める編集のステップをご紹介していきますね。
4-1. 簡単なカット・つなぎからスタート
まず最初のステップは、「不要な部分を切って、つなげる」ことです。
たとえば、自分で撮った動画の冒頭や終わりの「いらない部分」をカットして、スムーズにつなぐだけでも立派な編集なんですよ。
この作業は、操作もシンプルなので、編集初心者の子どもでもすぐに取り組めます。
また、好きな動画の中から「面白い場面」だけを集めるなど、遊び感覚でできるのも魅力です。
- 短時間で結果が出る成功体験がすぐ得られてやる気アップ
- 操作が簡単カットと並べ替えだけで完成する
- 目的が明確「面白いところだけ残す」という編集意図を体験できる
まずは簡単な操作で「やってみたい!」を引き出すことが大切なんですね。



4-2. 音楽・効果音の追加で楽しさ倍増
編集がちょっと慣れてきたら、BGMや効果音を入れてみましょう。
音の力で動画の印象ががらりと変わるので、子どもも「編集って楽しい!」と感じやすくなります。
効果音をつけることで、「この場面は驚き」「ここは笑い」など、感情を表現する工夫も学べますよ。
感覚的に選べる作業なので、直感で動くタイプの子にもぴったりです。
- 感情表現がしやすい音によって場面の雰囲気が作れる
- 子どもが楽しみやすい面白い効果音で遊び感覚に
- 達成感がアップする「プロっぽくなった!」という手ごたえが出る



4-3. 字幕・テロップで伝える力を伸ばす
最後におすすめなのが、「字幕(テロップ)」の追加です。
言葉でうまく伝えるのが苦手な子でも、画面に文字を入れることで自分の思いや内容をしっかり伝えられるようになります。
特に、発達障害の子どもは視覚情報の方が理解しやすいことが多いため、「テロップ=伝える力」の練習になるんですよ。
また、文字の色やサイズを変えることで、デザインセンスや構成力も自然と磨かれていきます。
- 言葉に頼らず伝えられる声に出さなくても内容を補足できる
- 視覚的に理解しやすい見るだけで内容が伝わる工夫を学べる
- デザインの楽しさも学べる文字の色や配置で表現力が広がる
「書く」「見せる」力が自然と育つのも、編集のいいところですね。



5. 実際に始めるにはどうすればいい?
「YouTube編集、うちの子にも合いそう!」と思っても、いざ始めようと思うと「何からやればいいの?」と迷ってしまいますよね。
でもご安心ください。
今は初心者でも安心して始められる環境やサービスがたくさんあるんです。
この章では、編集を始めるためのステップやおすすめの方法をご紹介していきますね。
5-1. 初心者向けの無料編集ソフトから
最初は、難しいソフトや有料サービスを使う必要はありません。
無料で使える初心者向けの編集ソフトから始めるのが安心ですよ。
スマホやタブレットに対応したアプリも多く、直感的な操作で編集ができるので、子どもでも楽しんで使えます。
以下はおすすめの無料編集ツールです。
| CapCut | スマホ・タブレット対応。操作が簡単で、効果音やスタンプも豊富。 |
| iMovie | Apple製品向け。シンプルで初心者に最適。ナレーション挿入も可能。 |
| Canva動画編集 | テンプレートが豊富で、デザインセンスも一緒に伸ばせる。 |
「操作がシンプル」「結果がすぐ見える」ことが、子どものやる気につながるんです。



5-2. 習い事として学べるオンライン教室も
「自宅だとサポートが難しい…」という場合は、オンラインで学べる動画編集教室を活用するのもおすすめです。
最近では、発達障害の子どもに対応した個別指導型の教室も増えてきています。
画面共有でやり方を丁寧に教えてもらえたり、わからないところを質問しやすい環境が整っているんです。
以下のような特徴の教室を選ぶと安心ですよ。
- 発達特性に配慮したカリキュラム感覚過敏や注意力に合わせた進行
- 個別対応が可能「わからない」をその場で聞ける環境
- 成功体験を重視小さな「できた」を積み重ねて自信に



5-3. 家庭でのサポート方法とは
親御さんとしては、「どこまで関わったらいいの?」と悩むこともあるかもしれませんね。
最初は「一緒にやってみる」ことが大事。
操作が分かるようになるまでは、そばで見守りながら、「ここをこうするとできるよ」と声をかけてあげましょう。
ポイントは、「手伝いすぎず、自信を持たせる」サポートです。
以下のような関わり方を意識すると、子どもも安心して取り組めますよ。
- 操作を教えるときは一緒に「やってあげる」のではなく「やってみせる」
- 作品を褒めてあげる「ここがよかったね」と具体的に認めてあげる
- うまくいかないときは休憩を提案焦らず、ゆっくり進めることを大切に
「できた!」という実感を積み重ねて、自信と笑顔を引き出していきましょう。



6. 保護者が感じる不安とその解消法
「動画編集って楽しそうだけど…」「うちの子、大丈夫かな?」と、不安に思うのは当然のことですよね。
特に発達障害の子どもを育てていると、ネットの危険や身体面への影響、生活リズムなど、気になることがたくさんあると思います。
この章では、実際によくある不安と、その解消法についてまとめてお伝えしますね。
6-1. 「ネット依存」への不安をどう対処する?
「編集をきっかけに、ずっと画面を見てしまうんじゃ…」という不安、よく分かります。
でも、目的を持った活動として取り組ませれば、単なる“ネット漬け”にはなりません。
大切なのは、親子で「ルール」を決めて取り組むことです。
たとえば、「〇分やったら休憩」「編集は週〇回まで」といったルールを最初に共有しておくと安心です。
また、作業時間をタイマーで区切るなど、視覚的に管理できる方法も効果的ですよ。
- 時間を区切るタイマーやスケジュール表で見える化
- 作業の目的を共有する「何のためにやるか」を一緒に考える
- メリハリをつける「編集の後は体を動かす」などバランスを意識
「遊び」と「学び」を切り替える仕組みを作ることが大切ですね。



6-2. 「視力」「姿勢」など身体面のケア
長時間パソコンやタブレットに向かっていると、やっぱり気になるのが視力や姿勢への影響ですよね。
でもこちらも、少し意識するだけで防げるポイントはたくさんあるんです。
まずは、環境の見直しが大切。
画面からの距離や椅子・机の高さ、照明の明るさなどをチェックしてみてください。
あとは30〜45分に一度は立ち上がって、ストレッチや水分補給をするなど、習慣化してあげましょう。
- 正しい姿勢を意識する椅子の高さや画面の位置を調整
- 目の休憩時間を設ける30分に1回は目を休ませるルールを
- ブルーライト対策をするフィルターやメガネで負担を軽減



6-3. 時間管理や目標設定の工夫
「いつの間にか、ずっと編集してる!」という状態になることもあるかもしれませんね。
そんなときは、時間や目的を「見える化」するのが効果的です。
たとえば、「今日は10分間だけテロップ作業をする」「日曜日までに5分の動画を1本作る」など、小さな目標を立ててあげるといいですよ。
また、カレンダーやホワイトボードを使って、今週の予定や進捗を記録するのもおすすめです。
子ども自身が「やった!」と確認できる工夫が、継続につながります。
- 作業に時間のゴールを設けるダラダラを防ぐために明確な終わりを設定
- 達成感を「見える化」カレンダーやスタンプで目に見える成果を
- 親子で一緒に確認する「どこまでできた?」を一緒に話す時間を持つ
「編集の習慣化」には、親子のコミュニケーションがカギですよ。



7. 発達障害の子に合う編集スタイルとは?
編集作業って、やり方はひとつじゃないんです。
特に発達障害の子どもたちは、それぞれに感覚やこだわりが違うので、「この子に合うスタイル」を見つけてあげることが大切。
無理に型にはめるのではなく、得意や興味を伸ばす方向で考えていきましょう。
この章では、発達特性に合わせた編集スタイルの工夫をご紹介します。
7-1. 感覚過敏・こだわりの活かし方
発達障害の子どもには、感覚過敏や強いこだわりを持つ子が多いですよね。
でもそれは、「細部に気づける才能」でもあるんです。
たとえば、音のちょっとした違いに気づける子なら、「ここは静かにしよう」「この音は耳にやさしいね」といった工夫ができます。
また、「ここだけはこうしたい!」というこだわりは、作品の個性として活かせますよ。
- 感覚の違いを強みに音や色への敏感さが編集のセンスにつながる
- こだわりが作品の個性に自分だけのスタイルが動画に表現される
- 細かい作業が得意カットやタイミング合わせなどで力を発揮
「気にしすぎ」ではなく「気づける力」として活かすのがポイントです。



7-2. テンポや色合いに配慮した演出方法
編集には「テンポ」や「色」の使い方が大事ですよね。
でも発達障害の子の中には、テンポの速い映像や、強い色彩の変化に疲れてしまう子もいます。
だからこそ、「自分にとって心地よいテンポ」「落ち着く色合い」で動画を作っていくことで、ストレスなく続けられるようになるんです。
演出の自由度が高いYouTube編集なら、自分に合ったスタイルを追求する楽しさもありますよ。
- テンポをゆっくりにする視聴者にとっても見やすくなる効果も
- 色を落ち着いたトーンに背景やテロップの色選びも自分らしく
- 音量や音質も調整心地よさを重視した編集ができる



7-3. 本人の興味に合った企画作りが鍵
どんなに良いツールや環境があっても、やっぱり「本人が楽しいと思えること」じゃないと続きませんよね。
動画のテーマは、子どもが夢中になっていることに合わせるのがいちばんです。
ゲーム実況、ぬいぐるみ紹介、工作動画、イラストメイキング……なんでもOK!
「これを見せたい」「これを伝えたい」という気持ちが、動画編集のエネルギーになります。
- 興味を最優先に好きなテーマならモチベーションが続く
- 「見せたいもの」を主役に自分の世界観を動画で表現
- 自由な発想を尊重「普通じゃない」が個性になる
「これがうちの子らしいね」って思える動画作りが、いちばんの目標ですよね。



8. まとめ|「好き」を活かせば、未来が拓ける
発達障害のある子どもたちは、「みんなと同じ」が難しいこともあるけれど、「自分だけの得意」を持っている子がとても多いですよね。
YouTube編集は、その「得意」や「好き」を活かしながら、自分らしく成長できる手段のひとつです。
しかも、学びながら将来の選択肢を広げられるのも大きな魅力。
子どもが楽しそうに取り組む姿を見て、「この子の未来、ちょっと明るく見えてきたかも」と思えたら、それが何よりのスタートです。
焦らず、比べず、ひとつずつ「できた!」を増やしていきましょう。
編集は「スキル」でもあり、「自己表現」でもあり、「成長の記録」でもある——だからこそ、発達障害の子にとってピッタリな習い事なんです。



- YouTube編集は、発達障害の子どもの「好き」と「得意」を活かせる学びの場
- 将来につながるスキルや自信を自然に育める
- 始めやすく、親子で楽しめる環境も整っている

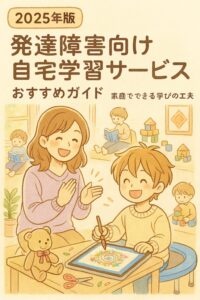
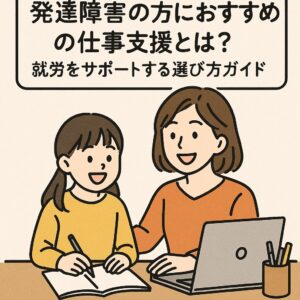


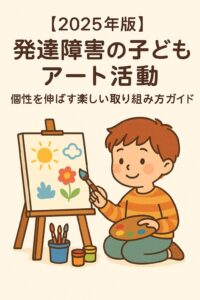



コメント