「勉強が苦手で続かない…」「どうしても集中が続かない…」そんな悩み、ありますよね。
でも、発達障害の特性を活かせば、ゲームを使った学習がぴったりなんです。
最近は、発達障害の子ども向けに開発された知育ゲームやアプリがたくさん登場しています。
この記事では、ゲーム学習のメリットから選び方、おすすめのツールまで、分かりやすくお伝えしますね。
お子さんの「できた!」を増やすために、ぜひ参考にしてください。
- 発達障害の子にゲーム学習が向いている理由
- 学べる内容やジャンルの具体例
- おすすめのゲーム・アプリ紹介
1. 発達障害の子どもにゲーム学習が向いている理由

発達障害のあるお子さんは、学習スタイルに個性があります。
ゲームはその個性にフィットしやすいツールなんですよ。
特に、視覚的・聴覚的な刺激が多く、楽しみながら繰り返し学べるのが特徴です。
集中力の持続が難しい子でも、ゲームなら取り組みやすいんです。
1-1. ゲームの中で成功体験を積める

ゲームでは、クリアしたりポイントを獲得したりと、小さな「できた!」を積み重ねることができます。
発達障害の子どもにとって、こうした達成感は非常に重要なんです。
何度でも挑戦できることが、自己肯定感アップに直結します。
学校や宿題では「できない」と感じやすい子でも、ゲームでは「できた!」という感覚を得やすいんですよ。
1-2. 感覚的な学びに強い子どもにマッチ



発達障害の中には、視覚優位・聴覚優位など、情報の受け取り方に特性があります。
ゲームは音・色・動きなど、多様な刺激があるので、感覚的な学びにぴったりなんです。
特に、タッチや操作で体感的に理解できる点は、文字や音声だけの学習より効果的なこともあります。
1-3. 自分のペースで進められる



集団授業では周囲のペースに合わせる必要がありますが、ゲームなら「自分のリズム」で進められます。
わからないまま先に進むこともないし、得意なところはどんどん伸ばせます。
タイムプレッシャーがない設計のゲームも多く、焦りや不安を感じにくいのも魅力です。
2. ゲーム学習で身につく力とは?


「ゲームで本当に学習効果があるの?」って、ちょっと不安になりますよね。
でも、実際にはゲームで学べることって、思った以上にたくさんあるんですよ。
発達障害の子どもたちが苦手としやすい「集中」「記憶」「言語理解」などの力も、ゲームを通して自然と育つことがあるんです。
楽しみながら、しっかり学べるのがゲーム学習の魅力ですね。
2-1. 認知力や記憶力が伸びる



たとえばパズルや迷路などのゲームは、状況を見て判断する力や、覚えた情報を使う力が求められます。
このときに使われるのが「ワーキングメモリ(作業記憶)」です。
遊びの中で自然に記憶力や認知力が育まれるというのは、ゲームならではの強みですよね。
間違えてもすぐに再チャレンジできるので、「失敗=学び」になりやすいのも大きなメリットです。
2-2. 読み書きや数の感覚も育つ



文字をなぞる、絵と文字をマッチさせる、数を数えてアイテムを集める——そんなゲームはたくさんあります。
視覚・聴覚を使って覚えることができるので、文字や数に苦手意識がある子どもにもぴったりです。
また、楽しみながら繰り返せることで、知らないうちに語彙力や算数的思考力が育っていきます。
「わかった!」という瞬間が、学ぶ意欲につながるんです。
2-3. 感情のコントロールや社会性もサポート



ゲームでは、「順番を待つ」「失敗しても落ち着く」「相手を思いやる」といった行動も求められます。
とくに協力プレイ型のゲームでは、相手と息を合わせることが必要になるので、社会性や対人スキルが育ちやすいんです。
楽しみながら感情のコントロール力や対人感覚を養えるって、すごくありがたいですよね。
もちろん、使う時間や内容には配慮が必要ですが、うまく取り入れれば心の成長にもつながります。
3. おすすめのゲーム学習ジャンルとは?


発達障害のあるお子さんに合ったゲーム学習って、どんなジャンルがいいの?と悩みますよね。
でも大丈夫。
いろいろなジャンルの中から、お子さんの得意や興味に合ったものを選べばいいんです。
ここでは、特におすすめの3つのジャンルを紹介しますね。
それぞれの特徴を知って、学習への第一歩につなげていきましょう。
3-1. パズル・迷路系ゲーム



このジャンルは、視覚的なヒントをもとに考える力が必要になるので、空間認知や論理的思考を鍛えるのに向いています。
形を揃えたり、道順を考えたりといったルールの中で、集中力を保ちつつ達成感も得られやすいんですよ。
何度も挑戦しているうちに、「工夫する力」や「順序立てて考える力」も自然と育っていきます。
成功体験の積み重ねで自己肯定感もアップしますし、「あとちょっと!」と粘る姿勢も身についてきます。
迷路や図形合わせゲームは、未就学のお子さんにもおすすめですよ。
3-2. 文字・数あそび系ゲーム



このジャンルは、ひらがな・カタカナ・数字などの基本的な学習を、遊びの中で自然に取り入れられるのが魅力です。
たとえば、キャラクターと一緒に文字をなぞったり、音声つきで言葉を覚えたり。
かず遊びでは、ものを数えたり、簡単な足し算をゲーム感覚で学べたりもします。
「学ぶ=楽しい」という意識を育てる入り口としてとても有効です。
「うちの子、文字に興味ないんだけど…」という時こそ、試してみてくださいね。
3-3. 生活スキル・ルール系ゲーム



生活スキルやルールの理解が苦手なお子さんにも、ゲームは大きな助けになります。
たとえば「おはよう」「ありがとう」といったあいさつを選んだり、食事のマナーや身支度を学べる内容もあるんですよ。
ゲームの中で「どう行動するか」を疑似体験できるので、実際の生活でもイメージしやすくなります。
繰り返し遊びながら自然と行動パターンを学べるのが、このジャンルの大きな魅力です。
また、感情を表すキャラクターや、選択式のやり取りなどを通じて、気持ちの表現や他者理解のきっかけにもなります。
親子で一緒にプレイすることで、「やってみようね」と現実につなげやすくなりますよ。
無理に「覚えさせよう」としないで、「遊びの中で自然に慣れる」くらいの気持ちがちょうどいいですね。
4. ゲーム学習の効果を高めるコツ
ゲームは楽しいけれど、ただ遊ぶだけではもったいないですよね。
せっかくなら「学び」につながるように、親としてできる工夫を取り入れていきたいところです。
ここでは、お子さんの成長につながるようにゲーム学習を活用するためのコツをご紹介します。
ほんの少し関わり方を変えるだけで、ぐんと効果がアップしますよ。
4-1. 子どもの興味・得意に合わせて選ぶ



子どもが楽しく続けられるかどうかは、興味のある内容かどうかにかかっています。
たとえば、動物が好きな子には動物が出てくるパズル、乗り物が好きなら電車を使った数あそびなど。
「できた!」という成功体験が積み重なるゲームを選ぶことが大事なんです。
得意な分野をうまく活かすことで、苦手なことにもチャレンジしやすくなりますよ。
4-2. 一緒にプレイして「学び」に気づかせる



子どもがゲームに夢中になっているとき、一緒に見てあげるだけでも効果は変わってきます。
「ここで文字を読んだね!」「今、かずを数えたね!」と声をかけてあげると、本人も「学んでる」という実感を持ちやすいんです。
また、感情のやりとりやルールの理解が必要なゲームでは、大人がモデルになってあげることも重要です。
「ひとり遊び」にしないだけで、学びが何倍にも広がりますよ。
4-3. 時間と環境を決めてメリハリをつける



ゲームに集中できるのは良いことですが、だらだらと長時間続けてしまうのは避けたいですよね。
あらかじめ「今日は15分だけ」「このステージが終わったら終わり」と区切りをつけておくと、切り替えの練習にもなります。
また、静かな場所や学習に適した時間帯にプレイすることで、集中力を最大限に引き出すことができます。
「学習のひとつ」として位置づけることで、ゲームが習慣化しやすくなります。
タイマーや「やることリスト」なども併用して、スムーズな生活リズムにつなげましょう。
5. 発達障害の子におすすめのゲーム・アプリ5選
どんなゲームを選べばいいのか、たくさんあって迷いますよね。
ここでは、発達障害のあるお子さんに特に人気があり、学びやすさに定評のあるアプリ・ゲームを5つご紹介します。
「学べる」「使いやすい」「続けやすい」をポイントにピックアップしました。
親子で一緒に選んで、楽しみながら取り入れてみてくださいね。
5-1. トドさんすう(数あそび)



対象年齢:3〜8歳
算数の基礎をゲーム形式で学べるアプリです。
キャラクターが登場して数を数えたり、形を見分けたりしながら進めていくので、小さなお子さんでも取り組みやすいですよ。
視覚的に理解しやすい工夫がされていて、数字に苦手意識がある子にもおすすめです。
集中力を切らさずに遊び感覚で算数が学べるのが魅力です。
5-2. もじあそび かなカナ(文字学習)



対象年齢:3〜7歳
ひらがな・カタカナを楽しく学べるアプリです。
なぞり書きや読み上げ機能がついているので、視覚・聴覚を同時に使って学ぶことができます。
言葉を覚えるゲームやパズルも含まれており、遊びながら語彙力アップにもつながります。
「読む・書く」ことの楽しさを自然と体感できます。
5-3. すくすくプラス(生活スキル支援)



対象年齢:3歳以上
あいさつ・歯みがき・おかたづけなど、生活の基本をゲーム形式で学べるアプリです。
キャラクターと一緒にお手本を見たり、順番通りに行動を選んだりして進めていくことで、自然と生活習慣が身についていきます。
特にASD傾向のある子どもにとって、視覚的に「やること」を理解できるのは大きなポイントです。
ゲームで覚えるから、日常生活にも応用しやすいんですよ。
6. ゲーム学習を取り入れる際の注意点
ゲーム学習にはたくさんのメリットがありますが、やっぱり気をつけたい点もありますよね。
「楽しい」だけで終わってしまわないように、家庭でのルールや声かけがとても大切です。
ここでは、ゲーム学習をうまく活用するために知っておきたい注意点を3つご紹介します。
お子さんにとって「学びの時間」になるよう、ちょっとした工夫でグッと効果が変わってきますよ。
6-1. ゲームの時間を決めてメリハリをつける



ゲームは夢中になりやすいからこそ、「今日は15分」「1ステージだけ」など、時間や内容の区切りを最初に決めておくことが大切です。
あいまいにしてしまうと、子どもはどこで終わっていいかわからなくなってしまうこともあります。
タイマーやスケジュール表を活用して、視覚的に「おしまいの時間」がわかるようにするとスムーズです。
ルールを守ること自体も、社会性のトレーニングになりますよ。
6-2. 内容をよく確認し、年齢や特性に合ったものを選ぶ



一見よさそうなアプリでも、刺激が強すぎたり、ルールが複雑だったりすると逆効果になることもあります。
発達特性によって、音や光に敏感なお子さんもいますので、内容・難易度・操作方法を事前にしっかり確認しましょう。
また、学習系アプリでも「課金」が発生するものもあるので、安心して使えるよう保護者がコントロールできる環境を整えることも大事です。
「安全で」「やさしくて」「本人が楽しめる」ものを選ぶことが第一です。
6-3. 「学び」の意識を持たせる声かけを意識する



ただ画面を見ているだけに見えても、実はすごく考えていたり、記憶を使っていたりします。
それを見逃さず、「さっきのひらがな、ちゃんと読めたね!」「考えてゴールできたね!」と声をかけることで、「自分は学んでいる」という自覚が生まれます。
この「気づかせる声かけ」が、次の意欲につながっていくんですよ。
学びを「見える化」してあげるのが親のサポートのコツですね。
7. ゲーム学習と他の学びをどう組み合わせる?
ゲーム学習だけでも楽しく学べますが、他の学びと組み合わせることで、より効果的にスキルを伸ばせるんですよ。
「遊びながら学ぶ」だけで終わらせず、家庭学習や体験活動ともバランスよく取り入れていくのが理想です。
ここでは、ゲーム学習と他の学びをどうつなげていけばいいのか、3つの視点で解説しますね。
7-1. 家庭学習とリンクさせて「復習ツール」として活用



ゲームで学んだひらがなや数を、紙の教材や家庭での会話にリンクさせると、定着度がぐんとアップします。
たとえば、アプリで覚えた言葉をカードで使ってみたり、算数ゲームの内容を一緒にお買い物で試してみたり。
「ゲームの中で知ったことを現実で使う」ことが学びの深まりにつながります。
「今日ゲームで〇〇ってやってたね!」と話題にするだけでも効果的ですよ。
7-2. 外遊びや実体験と組み合わせて五感を刺激



たとえば、「野菜を収穫するゲーム」をやったあとに実際にスーパーに行く、「動物の名前」を覚えたら動物園へ行く、というように、実体験とリンクさせてみましょう。
五感を使った体験は記憶に残りやすく、「なるほど!」と感覚的に理解できるきっかけにもなります。
ゲームで得た知識をリアルな場で「体験化」するのがコツです。
また、外遊びで発散したあとにゲームをすると、集中しやすくなる子も多いんですよ。
7-3. ごほうび・モチベーションの道具として活用



勉強やお手伝いが苦手な子にとって、ゲームが「やる気スイッチ」になることも。
「プリントがんばったら、5分だけゲームしよう」と約束をすると、自分で行動をコントロールする練習にもなります。
ただし、「ゲームが目的になりすぎないように」することが大切です。
モチベーションアップの手段として、うまく活用するよう意識しましょう。
うまくいった日は「自分でルール守れたね」と褒めてあげると、自己肯定感もアップしますよ。
8. まとめ|ゲーム学習は「楽しい」から始めよう
発達障害のあるお子さんにとって、「学ぶって楽しい!」と感じられることはとても大切ですよね。
ゲーム学習は、その「楽しい」の気持ちを引き出す最高の入り口になるんです。
しかも、ただ遊んでいるように見えて、実は「集中力」「記憶力」「社会性」など、将来に必要な力をたっぷり育ててくれます。
大事なのは、ただゲームをさせるのではなく、「お子さんに合ったゲームを」「適切なかたちで」取り入れること。
ご家庭でのちょっとした工夫とサポートがあれば、ゲーム学習は確実にお子さんの味方になりますよ。
無理なく、楽しく、続けられる「学びの時間」を、今日から一歩ずつ始めてみませんか?
- ゲーム学習は発達障害の特性に合った学び方
- ジャンルや使い方で効果が大きく変わる
- 親の声かけと関わりで学びが深まる
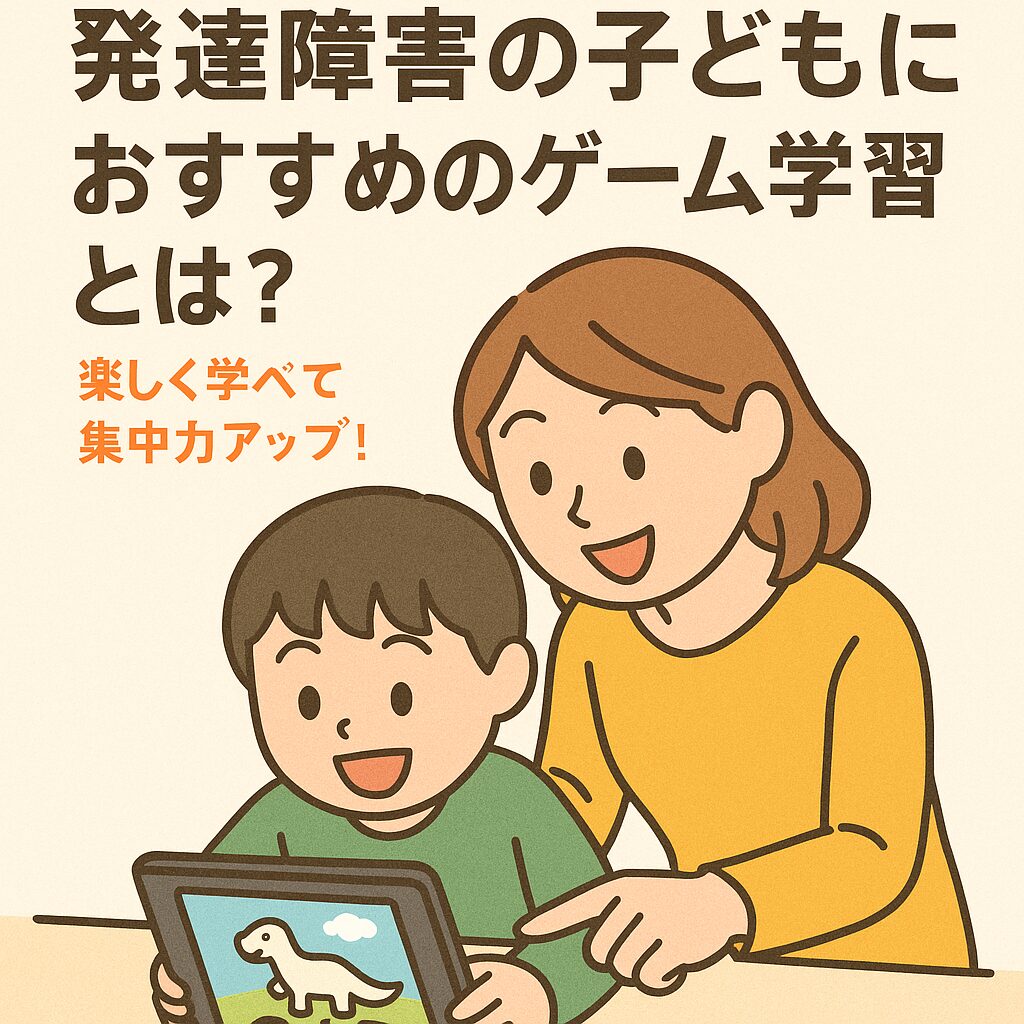


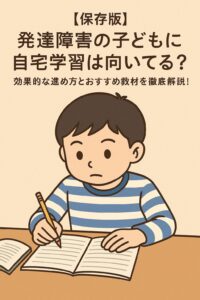



コメント