お子さんの「好き」を伸ばしてあげたい――そんな思い、ありますよね。
発達障害のあるお子さんにとって、「ものづくり」は自己表現のひとつであり、成功体験を積みやすい手段でもあるんです。
でも、どんな教室を選んだらいいの?オンラインと通室、どっちが合う?親としてどう関わればいい?…そんな疑問もありますよね。
この記事では、発達障害を持つお子さんに向いた「ものづくり教室」の選び方や特徴、自宅でもできる工夫まで、実例を交えてわかりやすくお伝えします。
- 発達特性に合った教室の選び方がわかる
- ものづくりがもたらす効果が理解できる
- 家庭でも試せる具体的な方法が見つかる
1. 教室選びのポイントとは
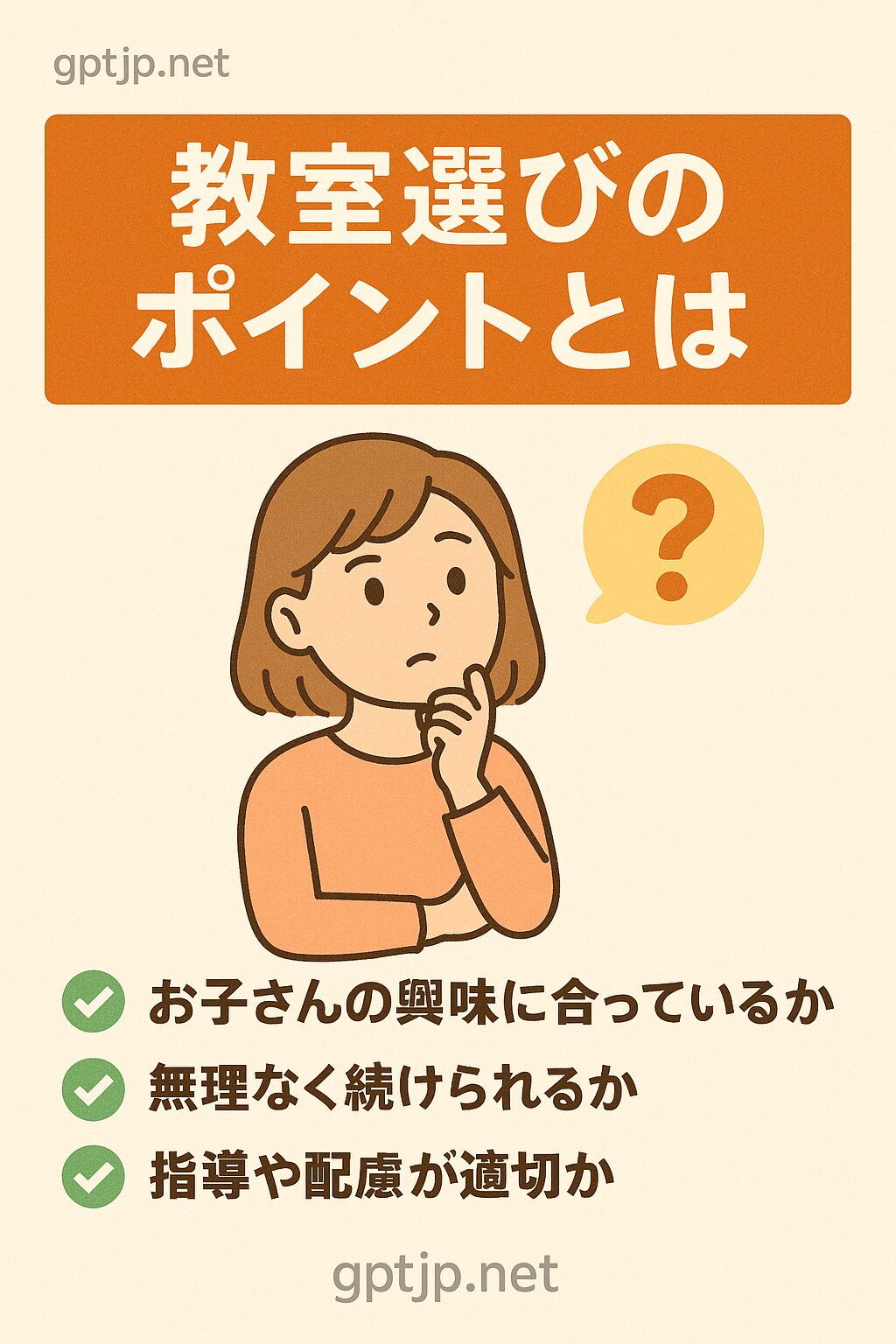
「この教室で大丈夫かな?」って、教室を探すときに一番気になりますよね。
発達障害のあるお子さんにとって、ものづくりの教室はとても魅力的な場所です。
でも、だからこそ「本人に合った環境かどうか」を見極めるのが大事なんですよね。
この章では、教室選びで気をつけたい3つのポイントをお伝えしますね。
1‑1. 発達特性に合ったものづくりとは
まず大切なのは、「その子に合ったものづくり」かどうかを見ることですよね。
発達障害のお子さんは、それぞれに違う特性や得意・不得意があります。
たとえば、細かい作業が得意な子もいれば、大きなものを使って表現するのが好きな子もいますよね。
だから、ロボットづくりでもプログラミングでも、一斉に同じことをやる教室より、個別にカスタマイズできる教室が安心なんです。
「本人の興味を活かした指導」こそが、学びを深めるカギなんですよね。
たとえば、言葉での説明が苦手な子には、視覚的にわかりやすい図やイラストを使った教材がピッタリ。
絵で見て理解できると、安心して学びに取り組めます。
教室選びのときには「体験会」で実際に教材や先生の雰囲気を見てみるのがおすすめですよ。

1‑2. 通室スタイルの違い(オンラインor対面)
今は、教室に行かなくても学べる時代ですよね。
オンライン型と通室型、どちらもメリットがあるので、お子さんの性格や生活リズムに合わせて選ぶと良いですよ。
たとえば、家だと安心して集中できる子にはオンラインが向いていますし、人との交流が好きな子には対面型が合っています。
オンラインなら送迎の負担もないですし、慣れた環境でのびのび学べるのがいいところ。
一方で対面型なら、実際の道具を使って作品を作ったり、先生やお友達との関わりもできますよね。
どちらが正解というより、「うちの子にはどっちが心地よいか?」が選ぶ基準なんです。
最近では、ハイブリッド型の教室(通室+オンライン併用)も増えているので、柔軟に選べるといいですね。



1‑3. 教材・コースの内容の見極め方
ものづくり教室って、本当にいろんなコースがありますよね。
プログラミング、電子工作、絵画、工作、3Dプリント…どれも魅力的ですが、選び方を間違えると「楽しくない」と感じてしまうことも。
だからこそ、「子どもの興味」や「できること」に合った内容かどうかがとても大切です。
Scratchなどのビジュアル型プログラミングは、文字の読解が苦手なお子さんにもやさしいですよね。
逆に、手先を動かすのが得意なら、模型作りやクラフト系の教室もおすすめです。
体験授業のときには、子どもの反応をじっくり見て、「夢中になれるか」「やりたがるか」をチェックしましょう。
教材は難しすぎず、成功体験を積ませてくれるレベルがベストです。



2. 発達障害児に向く“ものづくり”の理由


発達障害のお子さんにとって、「ものづくり」はただの遊びじゃないんですよね。
実は、創造する力や集中力、そして自信を育てるのにとっても向いている活動なんです。
この章では、ものづくりが発達障害のあるお子さんにもたらす良い効果についてお話ししますね。
2‑1. 自己表現と集中力の関係
発達障害があると、言葉で気持ちを伝えるのが難しかったり、周りにうまく合わせられなかったりすることってありますよね。
でも、絵を描いたりロボットを作ったりする「ものづくり」って、自分の思いやアイデアを“カタチ”にできる自己表現の手段なんです。
そうやって作っていると、自然と集中して取り組む時間が増えていきます。
「集中して静かに作ってる!」なんて場面が、ぐっと増えるんですよね。
また、自分の作品を「すごいね!」と認めてもらえることで、自己肯定感も少しずつ育っていきます。



2‑2. 試行錯誤を通じた自己肯定感
ものづくりでは、はじめからうまくいくことって少ないんですよね。
だからこそ、「何度か失敗して直す」「試行錯誤して完成させる」っていう経験がとっても大事なんです。
発達障害のお子さんは、普段「失敗しないように」と慎重になりすぎてしまうこともありますよね。
でも、ものづくりでは「間違えてもいい」「直せばもっとよくなる」って体験ができるから、気持ちが前向きになるんです。
「できた!」という達成感が、自己肯定感の大きな土台になるんですよね。
繰り返し成功を体験することで、「次もやってみたい!」という気持ちも育っていきます。



2‑3. 実際に見られる変化と成長
「ものづくり教室に通い始めて、うちの子が変わったんです」
そんな声、実際によく聞くんですよね。
最初は落ち着いて座っているのも大変だったお子さんが、好きなものを作ることで30分、1時間と集中できるようになることもあるんです。
また、プログラミングでキャラクターを動かす、工作で仕掛けのあるおもちゃを作るなど、「自分で考えて動く」経験を通じて、想像力や問題解決力も少しずつ育っていきます。
教室の先生や他の子との会話の中で、自然と社会性や協調性が育つことも。
小さな成功体験の積み重ねが、お子さんの心に大きな自信を与えるんですよね。
ご家庭でも「今日はこんなの作ったよ!」と楽しそうに話してくれることが増えたりして、親子の会話のきっかけにもなります。



3. おすすめ事例の紹介
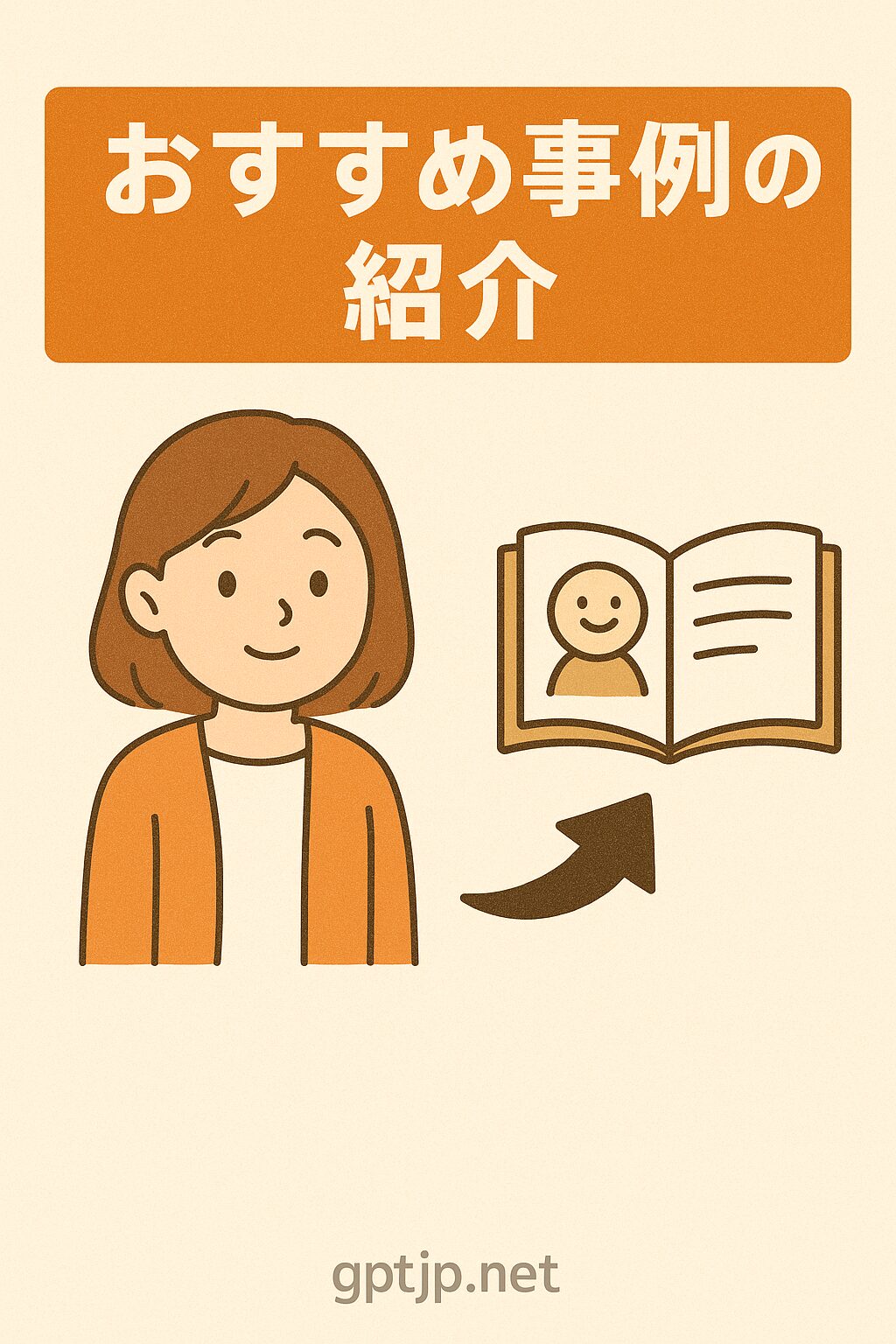
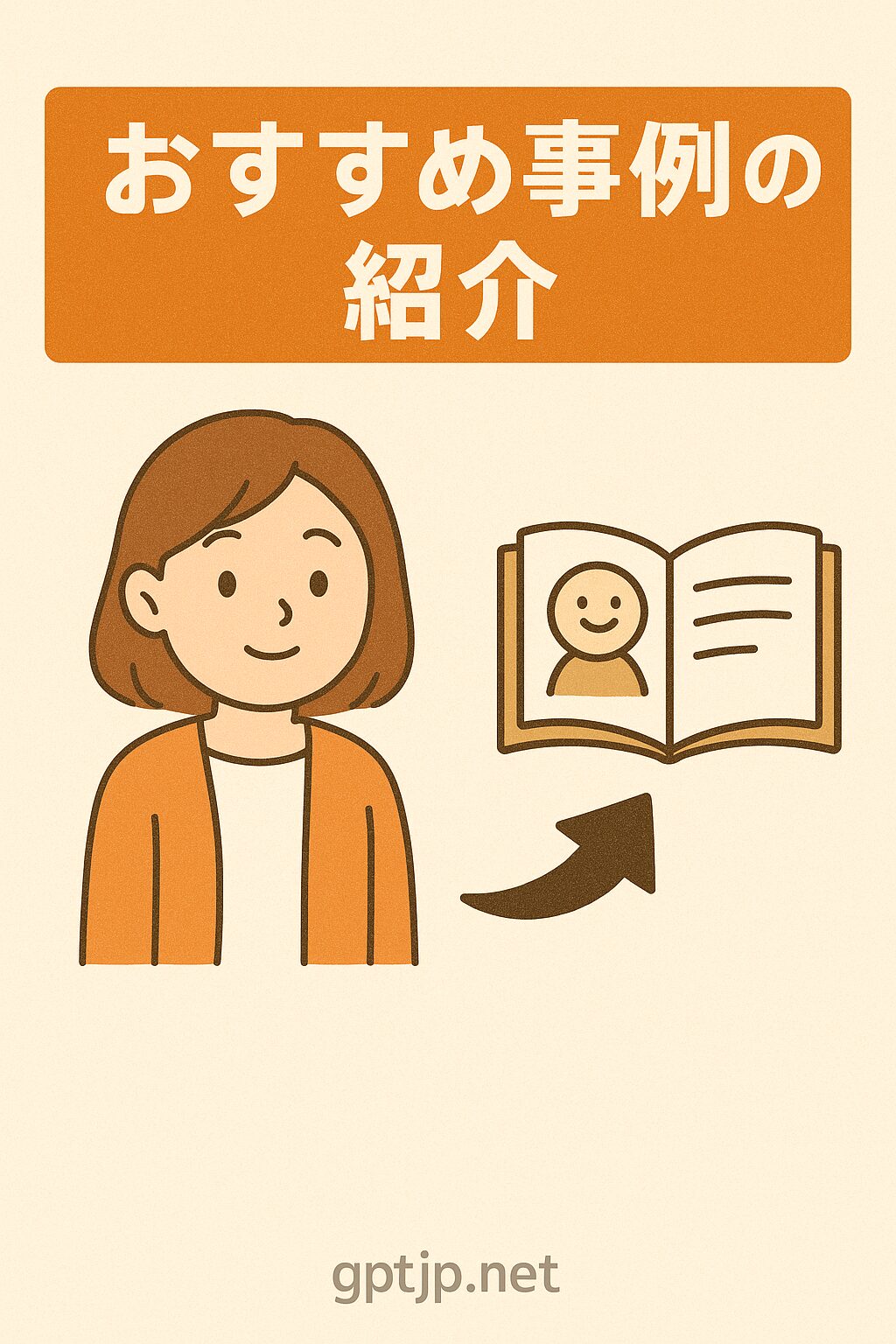
どんな教室がいいのか調べると、たくさんあって迷ってしまいますよね。
ここでは、発達障害のあるお子さんにも安心して通える、実績ある「ものづくり教室」を3つご紹介しますね。
それぞれ特色が違うので、お子さんに合いそうなタイプを見つけるヒントにしてください。
3‑1. LITALICOワンダーの特徴
LITALICOワンダーは、発達障害のある子を含めた多様な子どもたちを対象にした“創造型の教室”です。
プログラミングやロボット、3Dプリントなど、テクノロジーを使ったものづくりが体験できる教室なんですよね。
この教室のいいところは、子どもの特性や興味に合わせて“完全個別カリキュラム”を組んでくれるところなんです。
「大勢の中で同じことをするのが苦手」というお子さんでも、無理なく楽しめる工夫がされています。
また、先生たちも発達支援の専門研修を受けているので、安心感がありますよね。
子ども自身が「学びを楽しむ」ことを大切にしている教室です。



3‑2. STEAM教材「すてむぼっくす」活用例
「すてむぼっくす」は、STEAM(科学・技術・工学・アート・数学)をベースにした学習教材です。
これ、家庭でも使える教材としても人気なんですが、療育施設や放課後等デイサービスでも導入されているんですよ。
毎月届く教材は、工作やプログラミング、科学実験などバリエーション豊かで、発達特性のあるお子さんでも興味を持ちやすい内容になっているんです。
特に手を動かす作業が中心なので、言葉より動きで学ぶことが得意なお子さんにはピッタリですね。
作ったものはそのままおうちに飾ったり、家族と一緒に遊んだりもできます。
家庭学習にも使える、取り組みやすさが魅力です。



3‑3. 絵画・工作系教室の一例
創作系の教室も、お子さんによってはとても合うことがありますよね。
たとえば「アトリエ系」の絵画・工作教室では、自由に素材を使って表現したり、季節のテーマで作品をつくったりと、子どもの個性を伸ばすアプローチがされています。
絵を描く、粘土をこねる、紙を切って貼る――こういった作業は、視覚・触覚・空間認識などの感覚統合にも効果的なんです。
また、言葉が苦手な子でも「作品」で想いを表現できるのが魅力ですよね。
結果よりも過程を楽しむことが大切にされるので、安心して参加できます。



4. 自宅で実践できる“ちょこっとものづくり”
教室に通わせるのが難しいときって、ありますよね。
そんなときでも、「ちょこっとものづくり」はおうちでも気軽にできるんです。
ここでは、家庭で試しやすい教材や、親子で楽しめるアイデアをお届けしますね。
4‑1. 簡単キットの紹介
最近は、市販のキットでもとても優秀なものがたくさんあるんですよね。
たとえば、「レゴ®エデュケーション」や「KOOV」「すてむぼっくす」などは、発達障害のお子さんにも取り組みやすく設計されている教材なんです。
特におすすめなのが、以下のような特徴を持ったキットです。
- ビジュアル重視イラストや色で理解しやすく、手順が視覚的にわかる
- 段階式初級→中級→上級と、レベルアップしながら成長できる
- 成功体験が得られる完成しやすく「できた!」が実感できる
家電量販店やAmazonでも手に入りますし、「定期便」で毎月届くタイプも手軽ですよね。



4‑2. 家庭で遊びながら学ぶヒント
家の中でも、遊びながら学べる工夫って実はたくさんあるんですよ。
たとえば、空き箱やペットボトルを使っておもちゃを作ったり、レジ袋でパラシュートを作って落とす実験をしたり――そういう身近な素材での遊びも立派な「ものづくり学習」なんです。
さらに、以下のような家庭アイデアもおすすめです。
- クッキングホットケーキやゼリー作りで「順序」と「分量」を学ぶ
- ぬり絵・切り貼り手先を使って集中力アップ
- 廃材アート牛乳パックやトイレットペーパー芯で自由制作
「うまくできた」より「楽しかった」が大事なんですよね。



4‑3. 親子で「作品ギャラリー」をつくろう
作ったものを飾っておくって、それだけでも子どもにとっては大きな喜びですよね。
壁や棚の一角に、**「おうちギャラリー」をつくってみませんか?
完成した作品や絵を飾るだけで、「認めてもらえた」「がんばった自分が誇らしい」**という気持ちが育ちます。
フォトフレームに入れたり、名前や日付をつけたりすれば、成長の記録にもなります。
作品ごとに「どこが工夫できたかな?」「ここが面白いね」って声をかけると、さらにやる気が伸びるんです。
親子の絆も深まる素敵な習慣になりますよね。



5. 専門家の視点:療育とものづくりの融合
「療育」と「ものづくり」って、別物に感じてしまうかもしれませんよね。
でも、実はこの2つはとても相性が良くて、現場でもたくさん活用されているんです。
この章では、療育の場でどんな風にものづくりが取り入れられているかをご紹介しますね。
5‑1. 支援センターや療育機関での指導例
発達支援センターや療育施設では、手先を使った活動が多く取り入れられているんですよね。
その理由は、作業療法(OT)や感覚統合の視点から「手を使う=脳を育てる」ことに繋がっているからなんです。
たとえば、以下のような活動がよく行われています。
- ハサミ・のり・折り紙手先の器用さと視覚の協応性を養う
- 粘土や絵の具触覚や力加減の調整力を育てる
- 簡単な工作順序立てて考える練習になる
特に、自由度のある「制作活動」は、子ども自身の意欲や表現力を自然に引き出せるので、療育でもとても重視されています。



5‑2. 多職種連携が支える学び
実は、療育の現場では「作業療法士」「言語聴覚士」「心理士」「保育士」など、さまざまな専門職が連携して支援をしてくれているんです。
この多職種の連携があるからこそ、お子さんに必要な刺激や課題を「遊び」の中に取り入れられるんですね。
たとえば、ある子が「言葉のやりとりが苦手」でも、「工作の中で材料をもらう→ありがとうと言う」練習ができたりします。
また、絵を描く・作るという活動は、気持ちの安定や自己調整にもつながっていきます。
こうした細やかなサポートが、「ものづくりを通じた成長」の土台を支えているんです。
療育に通いながら、家庭や教室でも一貫した支援ができると、お子さんの変化もより早く、安心して育まれていきますよね。



5‑3. 教室と療育の“いいとこ取り”活用法
療育は“支援の場”、教室は“学びや楽しみの場”。どちらも大事だけど、両立できるの?って思いますよね。
実は、「教室」と「療育」はそれぞれ役割が違うからこそ、組み合わせることでより効果的になるんです。
たとえば、療育では「できるようになるための支援」を受けながら、教室では「楽しみながら学ぶ経験」を積むという流れがとても自然なんです。
こんな使い分けがおすすめです:
- 療育:苦手克服指示理解・手先の訓練・情緒の安定
- 教室:興味を伸ばす好きな分野で創作意欲や集中力を伸ばす
- 家庭:安定した見守り無理なく気分よく取り組めるサポート役に
療育と教室、両方の“いいとこ取り”が、お子さんの可能性を広げるカギになるんですよね。
通うタイミングや頻度は無理のない範囲で、まずはお子さんの「行きたい」「やってみたい」を大切にしてみてくださいね。



6. 保護者の心構えと見守り方
子どもが何かに挑戦するとき、親として「ちゃんとできるかな?」って心配になりますよね。
でも実は、親の関わり方ひとつで、子どもの意欲や自信がぐんと伸びるんです。
この章では、無理なく「寄り添って見守る」ためのコツをお伝えしますね。
6‑1. “できた!”を見逃さない工夫
小さな「できた!」の瞬間って、見逃しがちなんですよね。
でも、発達障害のあるお子さんにとって、その一歩はとても大きな成長だったりするんです。
たとえば、「ひとりでハサミを使えた」「道具を片づけられた」そんな瞬間を見つけたら、すぐに言葉で褒めてあげることが大切です。
「〇〇ができたね!」「頑張ってたね!」と肯定する声かけが、自己肯定感につながるんですよね。
できたことに注目する習慣がつくと、親もポジティブになれて、子どもの挑戦を応援しやすくなりますよ。



6‑2. ペースに合わせた声かけ
子どものペースって、大人とはまったく違いますよね。
焦って「早くやって!」と言ってしまいがちですが、お子さんの“今のペース”を尊重することがとても大事なんです。
たとえば、ゆっくり準備しているとき、「準備できたら教えてね」と一声かけるだけで、安心して動ける子も多いです。
また、「一緒にやってみようか?」と手を差し伸べることで、プレッシャーではなく支えとして受け取ってもらえます。
「見守る勇気」も親の大切な役割なんですよね。



6‑3. 気分の波も「そのまま受け止める」
発達障害のあるお子さんには、どうしても「気分の波」がありますよね。
やる気がない日や集中できない時間があっても、それは自然なこと。無理に引き出そうとすると、かえって逆効果になることも。
そんなときは、「今日はゆっくりしようか」「またやりたくなったら教えてね」と声をかけて、本人のリズムを大切にしてあげてください。
「やらない日があっても大丈夫」そんな安心感が、次へのやる気につながるんです。
気持ちが落ち着いたときにまたチャレンジできれば、それでOK。大事なのは、親子で焦らず、前向きに続けることですよね。



7. 教室選びQ&A
「実際どの教室がいいの?」「費用はどのくらい?」…って、通わせる前にいろいろ不安になりますよね。
この章では、よくある質問をQ&A形式でわかりやすくご紹介しますね。
安心して一歩踏み出すためのヒントになればうれしいです。
7‑1. よくある疑問と回答
Q:発達障害の診断がないと通えない?
→ いいえ、多くの教室は「診断の有無」にかかわらず受け入れています。
発達特性に理解のある教室なら、診断がなくても配慮してくれることが多いですよ。
Q:ついていけなかったらどうしよう?
→ 個別対応やマンツーマン形式の教室もありますし、最初は「体験レッスン」から始めるのがおすすめです。
子どもの様子を見て、ゆっくり慣れていけば大丈夫です。
Q:親は教室に付き添う必要がある?
→ 年齢や教室の方針によって異なりますが、最初は付き添い可のところも多いです。
少しずつ自立に向けて移行していく流れも自然ですよ。



7‑2. 実際の利用者の声
通っている保護者の方々の声も、とても参考になりますよね。
以下は実際の声をまとめたものです。
- 「最初は不安だったけど…」「本人が楽しそうにしていて、今では自信がついてきました」
- 「兄弟も一緒に通えて助かる」「同じ場で違うコースがあるので、家族みんなで通えるのが便利です」
- 「何かに夢中になれる経験ができた」「ゲームばかりだった子が、ロボット作りに夢中になりました」
親子ともに「通ってよかった」という声がとても多いんですよね。



7‑3. 料金や体験の問い合わせポイント
教室によって料金やシステムは本当にさまざまですよね。
月謝はおおよそ5,000円〜15,000円程度が多く、教材費や入会金が別途かかる場合もあるので、事前にしっかり確認しておくのが安心です。
問い合わせの際には、以下のポイントをおさえて聞いてみましょう。
| 体験レッスンの有無 | 無料・有料どちらか、内容や所要時間も確認 |
| 対応可能な発達特性 | 特性に応じた配慮や個別対応ができるか |
| 振替や休会制度 | 急な体調変化にも柔軟に対応してもらえるか |



8. まとめ “できた!”が増える毎日へ――親子で始める、発達障害の子のものづくり
発達障害のあるお子さんにとって、「ものづくり」は学びと自己表現の両方を叶えてくれる、大切な活動なんですよね。
教室選びにはちょっとしたコツが必要ですが、お子さんに合った場所を見つけられれば、毎日の中に“できた!”がどんどん増えていくはずです。
まずは、気になる教室の「体験レッスン」に参加してみたり、おうちで気軽にものづくりを楽しんでみることから始めてみませんか?
「楽しい」「できた」「またやりたい」――この繰り返しが、お子さんの自信を育ててくれるんです。
焦らず、親子のペースでゆっくり進んでいきましょうね。
- 発達特性に合った教室や教材を選ぶことが成功のカギ
- ものづくりは集中力・表現力・自己肯定感を育てる
- 家庭でもできる工夫と、親の見守りが成長を後押し
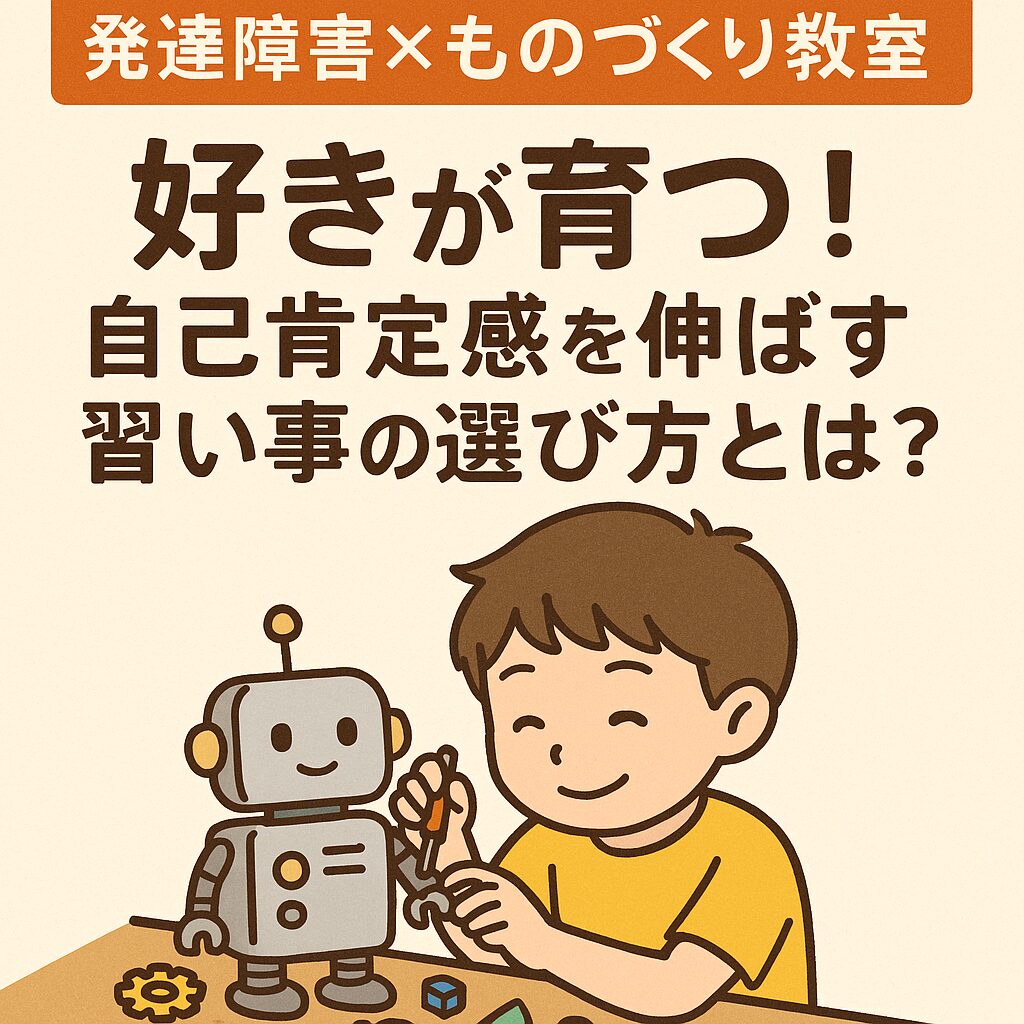
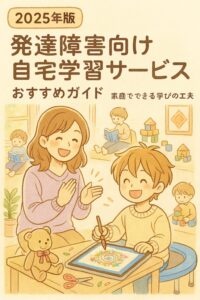
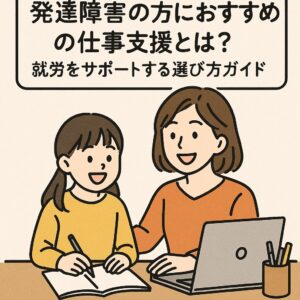

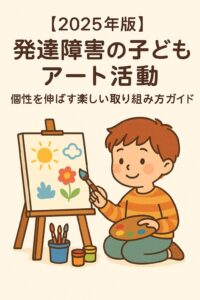




コメント