発達障害の子どもにとって、習い事選びって本当に悩ましいですよね。
周囲の子と比べて焦ったり、「続けられるかな?」と不安になったり。
でも実は、習い事は発達障害のある子どもの強みや個性を伸ばすチャンスなんです。
「合う」習い事を選べば、自己肯定感もぐっと育ちますよ。
この記事では、習い事の選び方のポイントから、ジャンル別の向き・不向き、親としての関わり方まで、わかりやすく解説していきます。
- 発達障害の子に合う習い事の見極め方がわかる
- 子どもの得意や特性を活かす考え方が学べる
- 親としてどうサポートすればよいかが明確になる
1. 発達障害の子どもにとっての「習い事」とは?

発達障害の子どもにとって、習い事は単なる「スキル習得の場」ではありません。
それ以上に、自己肯定感を育てる大切なチャンスになります。
できた!という達成感を積み重ねることで、自信が生まれます。
また、先生や仲間との関わりを通して、コミュニケーション力も育ちます。
「ただ通わせればよい」という考えではなく、その子の特性に合った環境を選ぶことが大切なんです。
親の期待よりも、「その子らしさ」を大事にしたいですね。
ここではまず、習い事を通して得られるメリットや、見方のポイントについてお話ししていきます。
1-1. 習い事で得られる3つのメリット

習い事というと、スキルを身につけることに目がいきがちですが、実はそれだけではありません。
特に発達障害のある子にとっては、内面的な成長にもつながる大きなチャンスになるんです。
- 自己肯定感の向上:成功体験を積むことで「できた!」という自信が育ちます。
- コミュニケーション力の向上:先生や仲間とのやりとりを通して、人と関わる力が養われます。
- 得意を見つける:色々な体験の中で、子どもが興味を持てることや得意なことが見つかります。
発達障害の子どもにとって、「できた!」という体験はとても大きな意味を持ちます。
たとえ小さなステップでも、それをしっかりと感じさせてくれる習い事こそ、価値があるんですよ。
1-2. 他の子と比べない姿勢が大切



つい、他の子と比べてしまうことってありますよね。
でも、発達障害のある子は、特性や成長のペースがひとりひとり違うものです。
「できる・できない」で判断するのではなく、その子がどこで楽しさを感じているかに目を向けてあげましょう。
比べることで親も子も苦しくなってしまうことがあります。
「昨日より少しできた」「笑顔で取り組めた」など、小さな変化を大切にする姿勢が、子どもの安心感につながります。
習い事を通して大切なのは、子どもの「今」をしっかり見つめることなんです。
1-3. 習い事の「目的」を決めると選びやすい



「どんな習い事が向いているのか分からない…」という方も多いと思います。
そんなときは、まず習い事をする「目的」を明確にしてみましょう。
楽しんで続けてほしいのか、得意を伸ばしてほしいのか、社会性を身につけてほしいのか——。
目的が定まると、選ぶ習い事の方向性も見えてきます。
例えば、「人とのやりとりを学んでほしい」なら、集団活動のある教室がおすすめですし、「集中力を高めたい」なら、ものづくり系の教室もいいかもしれません。
迷ったときこそ、「何のために通わせたいのか?」という視点を大切にしてくださいね。
2. 習い事を選ぶときの基本的な考え方とは?


習い事選びで迷ったとき、何を基準にすればいいか分からなくなってしまいますよね。
特に発達障害のある子どもの場合、「好きそうだから」「みんなやっているから」という理由だけでは合わないこともあります。
そんなときは、「本人の特性」や「楽しめるかどうか」を第一に考えてみてください。
親の期待や周囲の評価よりも、子どものペースに合わせてあげることが一番の近道なんですよ。
ここでは、習い事を選ぶ際に押さえておきたい基本的な考え方をご紹介します。
2-1. 興味のあること・楽しめそうなことを優先する



まず一番大事なのは、「その子が興味を持てるかどうか」です。
やらされる習い事は、すぐに飽きてしまったり、苦手意識を強くしてしまったりすることがあります。
発達障害のある子どもは、得意・不得意がはっきりしていることも多く、好きなことに対しては驚くほど集中力を発揮することもあります。
たとえば、音楽が好きならピアノやリトミック、ものづくりが好きなら工作教室など、その子の「好き」に寄り添った習い事が良いですね。
一度体験してみて、「楽しかった」「もっとやりたい」という気持ちがあれば、それは続ける力になるはずです。
2-2. 子どもの特性に合ったスタイルを見極める



発達障害といっても、特性はさまざまです。
集団が苦手な子、こだわりが強い子、じっとしているのが苦手な子——。
その子に合ったレッスンスタイルかどうかを見極めることが大切です。
マンツーマン指導が合う子もいれば、少人数のグループが安心する子もいます。
また、静かな空間で集中できる子もいれば、にぎやかな雰囲気のほうが楽しく参加できる子もいます。
見学や体験レッスンで、先生の雰囲気や教室のルール、子どもへの声かけなどをよく観察してみましょう。
合わない環境に無理やり通わせても、子どもにとってはストレスになるだけですからね。
2-3. 「できる・できない」より「楽しめるかどうか」で判断する



習い事に通わせると、どうしても「上手くなってほしい」「成果を出してほしい」と思いがちです。
でも、発達障害のある子にとっては、楽しみながら続けられることのほうが何倍も大切なんです。
「上手にできないから意味がない」と考える必要はありません。
むしろ、失敗しても怒られない環境、自分のペースで進められる教室であれば、子どもは安心して取り組めます。
先生が子どもにどう関わるか、努力や工夫をどう受け止めてくれるかも、大きなポイントになります。
できる・できないで判断するのではなく、「この教室で、この子が笑顔でいられるか?」という視点を大切にしてくださいね。
3. 発達障害のタイプ別・向いている習い事とは?


発達障害といっても、その特性は本当にさまざまですよね。
「どの習い事が合うのか」は、子どもの発達特性によって大きく変わってきます。
ADHDの子、ASDの子、学習障害(LD)の子など、それぞれに向いている環境や活動内容が異なるんです。
ここでは、代表的な発達障害のタイプごとに、相性の良い習い事を具体的にご紹介しますね。
「うちの子にはどれが合いそうかな?」と、ぜひ照らし合わせながら読んでみてください。
3-1. ADHDの子に向いている習い事



ADHDの子は、衝動的な行動や不注意、集中力の持続が難しい傾向がありますよね。
でもその反面、エネルギーが豊富で行動力があるという強みも持っています。
このタイプの子には、体を動かす習い事や、動きのある活動が向いています。
- 運動系(サッカー、体操、スイミング):集中力が切れても体を動かしてリフレッシュできます。
- ダンス・リトミック:テンポのある音楽で自然と体が動き、飽きにくいです。
- アート系:自由に表現できるので、自分のペースで楽しめます。
途中で飽きてしまっても、「またやりたい!」と思えるような楽しさ重視の教室がおすすめです。
3-2. ASD(自閉スペクトラム症)の子に向いている習い事



ASDの子は、感覚が敏感だったり、こだわりが強かったりする一方で、興味のあることに対しては深く集中できるという特徴もあります。
このタイプの子には、静かで落ち着いた環境や、ルールが明確な習い事が向いています。
- ピアノ・絵画教室:ひとりで集中できる活動で、自己表現の場にもなります。
- プログラミング:論理的思考が得意な子には、非常に相性がいいです。
- レゴ・ロボット制作教室:パターン化や組み立てが好きな子にぴったりです。
また、事前に予定が分かっているなど、見通しの立てやすい教室だと、より安心して取り組めますよ。
3-3. 学習障害(LD)の子に向いている習い事



学習障害(LD)のある子は、「読む」「書く」「計算する」といった特定の分野に困難があることが多いです。
でも、それ以外の分野ではとても優れた力を持っていることも多いんですよ。
このタイプの子には、学習に関係のないジャンルや、五感を使って取り組める習い事が相性◎です。
- 音楽・ダンス:耳や体で覚えるタイプの子に合いやすいです。
- スポーツ系:感覚的に学べる活動で、成功体験も積みやすいです。
- アート・手芸:手を使った表現活動に夢中になれる子もいます。
「勉強が苦手でも、こんなことが得意なんだ!」という発見が、子どもの自信につながります。
4. 習い事の継続で気をつけたいこととは?
習い事を始めるのは比較的スムーズでも、続けていくとなると悩みが出てきますよね。
「飽きてきたみたい」「嫌がる日が増えた」なんてこともあるかもしれません。
でも、続けることがすべて正解とは限らないんです。
子どもの様子や気持ちを見ながら、柔軟に対応していくことが、長続きのコツなんですよ。
ここでは、習い事を継続していく上で、親として知っておきたいポイントをまとめていきます。
4-1. 続けることをゴールにしない



つい「せっかく始めたんだから続けさせたい」と思ってしまいませんか?
でも、続けること自体が目的になってしまうと、親子ともに苦しくなってしまいます。
習い事はあくまで、「子どもが成長するための手段」。
楽しさや成長が感じられなくなってきたら、一度立ち止まって見直してみることも大事です。
「今日は行きたくない」と言ったときに、「どうしてそう思ったのか」を聞いてあげるだけでも、子どもは安心します。
無理に続けさせるのではなく、やめるという選択肢もあっていいと、親が受け止めてあげることが大切です。
4-2. 小さな成長を見つけてほめる



継続のカギは、子ども自身が「できた」「うれしい」と感じることです。
だからこそ、小さな成長を見逃さず、しっかり言葉にして伝えてあげましょう。
たとえば、「今日は先生の話をちゃんと聞けたね」「自分から道具を片づけられたね」など、技術面だけでなく、行動や気持ちの変化にも注目してあげると良いですよ。
子どもは親のまなざしをすごくよく見ています。
だからこそ、がんばったことを認められると、「また行ってみよう」と思える力になるんです。
一緒に振り返る時間をつくって、子ども自身に「今日はどうだった?」と聞いてみるのもおすすめです。
4-3. 無理に通わせると逆効果になることも



子どもが「行きたくない」と感じる日が続いていたら、それは無理をしているサインかもしれません。
親が「もったいないから行こう」「休むと遅れちゃうよ」と声をかけてしまう気持ちも、よくわかります。
でも、子どもの中で「習い事=しんどいもの」になってしまうと、本来の良さや楽しさが失われてしまいます。
一時的に距離を置く、回数を減らす、別の教室を検討するなど、柔軟に対応することが大切です。
子ども自身が「またやってみたいな」と思える余白を残しておくことが、長い目で見て良い結果につながることもあるんですよ。
5. 習い事選びで親ができるサポートとは?
「どの習い事がいいんだろう?」と迷うのは当然のこと。
でも、習い事選びは決して「正解」を探す作業ではありません。
大切なのは、子どもと一緒に考えて、一緒に進んでいくことなんです。
親の声かけや関わり方ひとつで、子どもの安心感やモチベーションは大きく変わります。
この章では、習い事選びや継続の場面で、親ができる具体的なサポート方法をご紹介しますね。
5-1. 子どもの気持ちを丁寧に聞き取る



「楽しい?」「続けたい?」と聞いても、「うん」や「わかんない」としか答えてくれないこともありますよね。
でも、それでもいいんです。
大事なのは、子どもが言葉にできない気持ちを、親が汲み取ってあげることです。
表情、体の動き、帰ってきたあとの様子など、小さなサインを見逃さないようにしましょう。
「今日はどうだった?」「あのとき楽しかった?」「あれイヤだった?」と、ゆっくり問いかけることで、少しずつ子どもの本音が見えてくるかもしれません。
言葉にならない思いを受け止めてもらえると、子どもも安心して次の一歩を踏み出せるようになりますよ。
5-2. 一緒に体験して「楽しいね」と共有する



体験レッスンには、ぜひ親も同行しましょう。
できれば子どもと一緒に参加したり、見学しながらリアルな様子を感じてみるのがおすすめです。
「楽しそうだったね」「あのとき集中してたね」と、一緒に振り返ることで、子どもは「ちゃんと見てもらえている」と実感できます。
また、「あれ上手だったね」と具体的に褒めることで、自信にもつながります。
親がポジティブに楽しんでいる姿は、子どもにとって安心材料にもなるんですよ。
「習い事は親が一緒に楽しむ時間」と考えて、親子での関わりを大切にしていきましょう。
5-3. 習い事の「目的」を忘れずに見守る



最初に「習い事をする目的」を決めたつもりでも、続けていく中で「上達してほしい」「他の子みたいにできてほしい」と思ってしまうこと、ありませんか?
でも、それって悪いことではないんです。
ただ、迷ったときはいつでも、最初の目的に立ち返ることを忘れずにいましょう。
・この習い事で子どもが笑顔になれているか?
・安心して通えているか?
・少しでも成長や変化を感じられているか?
答えがYESであれば、それだけで充分なんです。
親は、「子どもが自分らしく学べる場を見守る」ことが、いちばんのサポートになりますよ。
6. 習い事の見学・体験で見るべきポイントとは?
体験や見学は、習い事選びの中でとても重要なステップです。
パンフレットやホームページの情報だけでは分からないことも、現場に行ってみると一目瞭然なんですよね。
特に発達障害のある子どもの場合、環境の雰囲気や先生との相性が続けられるかどうかのカギになります。
ここでは、体験や見学をする際に注目したいポイントを3つご紹介します。
6-1. 先生の対応や声かけをチェックする



体験時には、先生がどんなふうに子どもに接しているかをよく見てみましょう。
特に注目したいのは、言葉の選び方やトーン、失敗したときの対応の仕方です。
子どもの困りごとにすぐ気づいてくれるか、やさしく声をかけてくれるかはとても大事なポイントです。
「できたね!」「がんばってるね!」という前向きな声かけが多い教室は、子どものやる気も自然と引き出してくれます。
逆に、注意が多すぎたり、子どもが萎縮してしまっているような場面があれば、慎重に検討してもいいかもしれません。
6-2. 教室の環境や雰囲気を見てみる



子どもがリラックスして過ごせる環境かどうかは、すごく重要なポイントです。
室内の明るさや広さ、音の大きさ、整理整頓の状態など、感覚的な過ごしやすさをチェックしましょう。
発達障害のある子の中には、感覚過敏がある子もいます。
光や音、におい、人の距離感など、教室の「感じ方」も子どもによってさまざまです。
見学時には、子どもの表情や動きに注目しながら、「ここ、落ち着くかな?」「集中できそうかな?」という視点で見てみてください。
教室内の掲示物や作品などから、先生の方針や雰囲気も伝わってくることがありますよ。
6-3. 子どもの反応をしっかり観察する



見学や体験のあと、子どもがどう感じたかを聞いてみることも大切です。
「楽しかった?」「どんなところが気に入った?」といった質問をしてみましょう。
もし「よくわかんない」と言われた場合でも、体験中の表情・様子・動きをよく覚えておくことがヒントになります。
笑顔だったか、集中していたか、困っている様子はなかったか。
何気ないしぐさやつぶやきが、子どもなりの感想を表している場合も多いんです。
帰宅後に「また行きたい」と口にしたら、きっとその教室が合っている証拠。
迷ったときは、子どものリアルな反応を一番の判断材料にしてあげてくださいね。
7. 習い事に向いていないと感じたときの対処法とは?
始めたばかりの習い事でも、「あれ?なんだか合ってないかも…」と感じること、ありますよね。
特に発達障害のある子は、環境のちょっとした違いにも敏感なので、合わないと感じる場面が出てきても不思議ではありません。
でも、それは失敗ではありません。
むしろ、「合わないものが分かった」こと自体が大事な気づきなんです。
この章では、習い事が「向いていないかも」と思ったときの考え方と、親としてできる対応のヒントをご紹介します。
7-1. まずは「続けたい気持ち」があるかどうかを確認する



「やりたくない」「行きたくない」と子どもが言ったとき、親としては戸惑ってしまいますよね。
でも、まずはその気持ちの奥にある「本音」に耳を傾けてみてください。
・最初からあまり乗り気じゃなかったのか
・何か嫌なことがあったのか
・他に興味が移ったのか
原因が分かれば、それに応じた対応ができます。
「続けたい」という気持ちがあるかどうかが、一番大切な判断材料になります。
無理に続けさせるよりも、気持ちに寄り添って「他に合うものを探してみようか」と提案することで、前向きな切り替えができますよ。
7-2. 「やめる」=「あきらめる」ではないと伝える



「やめる」と聞くと、「続かなかった」「失敗した」と思いがちですが、そうではありません。
子どもにも親にも必要なのは、「合わないと気づけたのは大きな成長だよ」と伝えることです。
その子にとって、今はその習い事のタイミングではなかっただけかもしれませんし、教室の雰囲気が合わなかっただけかもしれません。
「やめてもいい」と言ってもらえることで、子どもは安心します。
また、次に向けてのチャレンジにも前向きになれるんですよ。
7-3. 新しい可能性に目を向けるきっかけにする



「合わなかったから終わり」ではなく、「じゃあ次はどんなことに興味があるのかな?」と問いかけてみてください。
子どもにとっても、親にとっても、新しい世界を知るチャンスになることがあるんです。
例えば、スポーツ系が合わなかった子が、ものづくりにハマることもありますし、集団が苦手な子がマンツーマンで輝き出すこともあります。
「やってみて、ちょっと違った」を繰り返す中で、ピッタリの居場所が見えてくることも多いんですよ。
一緒に探す時間も、親子にとってはとても大切な経験になります。
焦らず、ゆっくり、その子に合った道を見つけていきましょう。
8. まとめ:発達障害の子どもにぴったりな習い事選びは“寄り添い”から始まる
発達障害の子どもにとって、習い事は「得意を見つける場所」であると同時に、「自信を育てる場所」でもあります。
だからこそ、親が焦らず、子どもの気持ちや特性に寄り添って選んでいくことが大切なんですよね。
合うかどうかは、実際にやってみないと分からないこともありますし、途中で「やっぱり違ったな」と思うことだってあります。
でも、そのすべてが、子どもの“これから”につながる経験になります。
うまくいかなかったことも、きっと親子の絆を深める大切な一歩になります。
焦らず、比べず、子どもと一緒に歩んでいけたら、それがいちばん素敵な「習い事選び」になると思いますよ。
- 発達障害の子には「楽しめるかどうか」が習い事選びのカギ
- 特性に合った環境や先生の対応が続ける力になる
- 親子で一緒に迷いながら、気づきを大切にしていこう
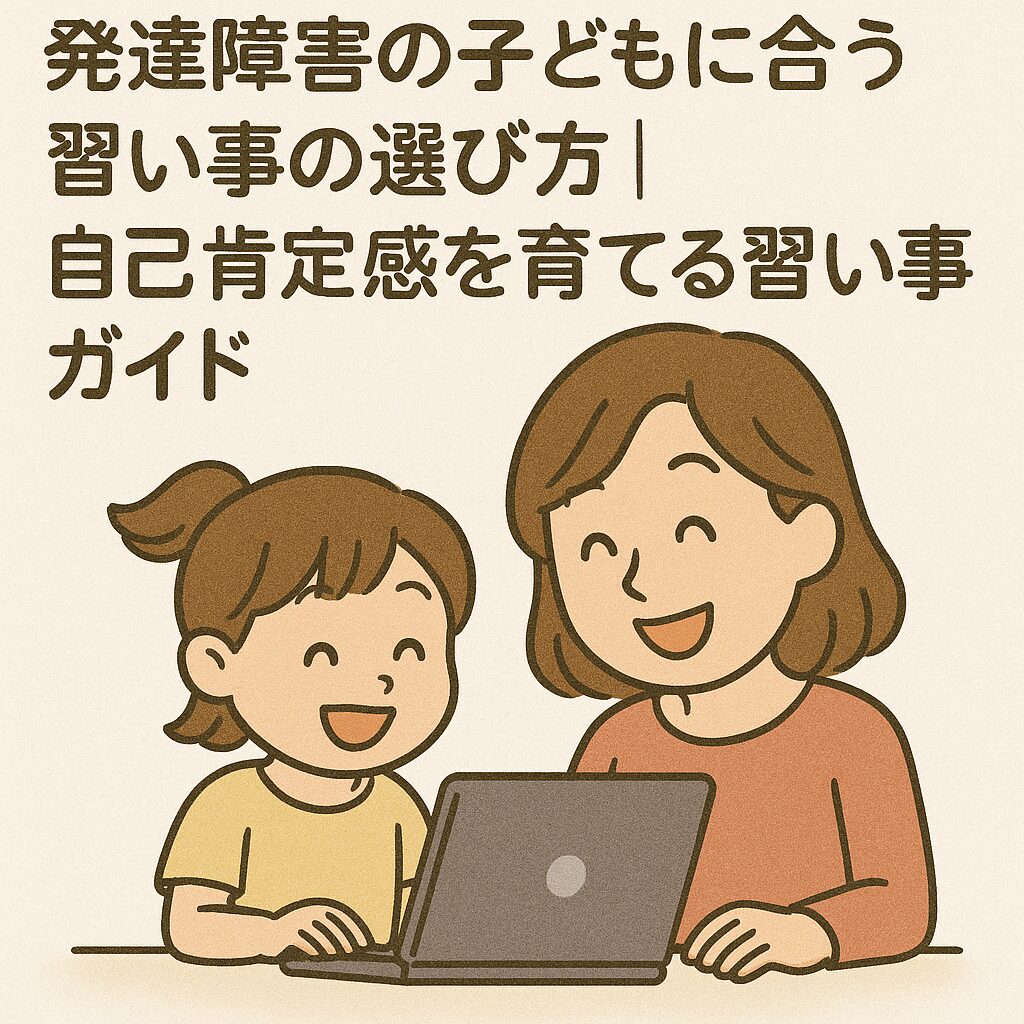
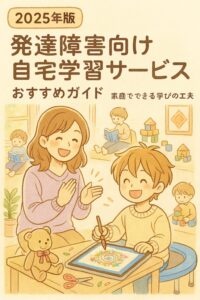
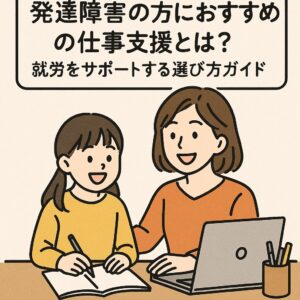

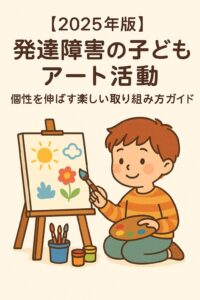




コメント