発達障害がある方が、働くことに不安を感じるのって当たり前なんですよね。
「うちの子に合う仕事ってあるの?」「就職しても続けられるか不安…」そんな声をよく聞きます。
でも、今は発達障害の特性を理解したうえでサポートしてくれる仕事支援サービスがたくさんあるんです。
支援を活用すれば、本人に合った職場や働き方を見つけることができますよ。
この記事では、発達障害のある方に向けたおすすめの仕事支援について、わかりやすく解説していきますね。
- 発達障害のある人向けの仕事支援の種類がわかる
- 就労移行支援・A型・B型の違いが理解できる
- 自分(子ども)に合った支援の選び方が見つかる
1. 発達障害のある方にとって仕事支援が大切な理由

発達障害のある方にとって、「働く」ってすごくエネルギーのいることですよね。
職場の人間関係や仕事内容、環境のちょっとした変化にも敏感に反応してしまうことがあります。
でも、それって本人の努力不足ではなくて、環境が合っていないだけのことも多いんです。
だからこそ、仕事に取り組むうえで「支援」があるかないかで、その後の生活や自信が大きく変わってくるんですよ。
ここでは、発達障害のある人が仕事に向き合うときに、なぜ支援が大切なのかを詳しく見ていきましょう。
1-1. 働くことに不安を感じる人が多い
発達障害のある方の中には、周囲とのコミュニケーションがうまく取れなかったり、注意力が散漫になりやすかったりと、職場での困りごとが多くなる傾向があります。
「指示されたことが理解しづらい」「マルチタスクになると混乱してしまう」といった悩みもよく聞きますよね。
それに加えて、同じミスを繰り返してしまうと自信をなくして、「もう働くのが怖い…」という気持ちになってしまう方も少なくありません。

働くことに不安を感じるのは、本人のせいではなく、支援や環境が整っていなかっただけかもしれません。
1-2. 支援があれば「働く力」が引き出せる
「支援」があると、働くうえでの不安や困りごとを相談できたり、職場に配慮をお願いしたりと、サポート体制が整います。
例えば、就労移行支援ではビジネスマナーの練習ができたり、実際の職場での体験ができたりと、実践的なサポートが受けられます。
また、本人の特性に合わせて「この作業は得意そう」「この環境なら集中できそう」といったマッチングも行ってくれるので、無理なく働ける可能性がぐっと広がります。



1-3. 自立への第一歩を踏み出すために
仕事をすることで、収入を得られるのはもちろんですが、それ以上に大切なのが「自信」なんです。
「できた!」「役に立てた!」という小さな達成感の積み重ねが、自己肯定感につながっていきます。
そのためにも、無理のない支援のある環境で、本人の力を活かせることが何より大切です。



「働くこと=怖い」ではなく、「働くこと=できるかも!」に変える第一歩が、仕事支援の役割です。
2. 発達障害の方向けの主な仕事支援サービス


「支援があるといい」といっても、実際にどんな仕事支援があるのか、わかりづらいですよね。
でも、大丈夫。
発達障害のある方をサポートする制度は、国の福祉サービスとして整ってきていますし、内容もどんどん充実しています。
ここでは、「就労移行支援」「就労継続支援A型」「就労継続支援B型」という代表的な3つの支援制度を、それぞれわかりやすくご紹介していきますね。
2-1. 就労移行支援とは?
就労移行支援は、一般企業への就職を目指す方のための支援サービスです。
障害福祉サービスの一つで、18歳から65歳未満の方が利用できます。
主な支援内容は以下の通りです。
- ビジネスマナーの習得挨拶、報連相、電話対応などを練習
- 職場体験や実習実際の職場に出て、業務にチャレンジ
- 就職活動のサポート履歴書の書き方や面接練習など
利用期間は原則2年間で、その間に自分に合った職場や働き方を一緒に探していけるんです。



2-2. 就労継続支援A型の特徴
A型支援は、すでにある程度の働く力がある方が、支援付きの職場で「雇用契約」を結びながら働く形です。
最低賃金が保証されるので、収入を得ながらスキルアップしていけるのが大きな魅力ですね。
A型事業所では、こんなお仕事が行われています。
- 軽作業商品の袋詰めや組み立てなど
- 清掃業務施設内や公共スペースの清掃
- パソコン作業データ入力や印刷など
事業所によっては、就職に向けた訓練も行っているので、ステップアップも可能です。



2-3. 就労継続支援B型の特徴
B型支援は、体調やスキルにまだ不安がある方でも、無理なく働く経験ができる支援です。
A型と違って雇用契約はなく、日々の活動に参加する形になります。
そのぶん、スケジュールや作業内容もかなり柔軟で、「週2日だけ」「午前中だけ」などの利用も可能なんです。
B型の主な特徴はこちら。
| 雇用契約の有無 | なし(工賃という形で支給) |
| 主な作業内容 | 内職・軽作業・農作業など |
| 対象者 | 就職がすぐには難しい方・体調に不安がある方 |



無理なく、自分のペースで「働く経験」が積めるのがB型の良さです。
3. どんな人にどの支援が合うの?


支援の種類がいろいろあるのは分かったけれど、「結局どれが合ってるの?」と悩んじゃいますよね。
本人の特性や生活の状況によって、合う支援も変わってくるんです。
ここでは、タイプ別にどの支援が向いているかを解説していきますね。
「これならうちの子に合いそう」と感じるヒントが見つかるかもしれませんよ。
3-1. 一般就職を目指したい人は就労移行支援
「できれば企業で働いてみたい」「正社員やパートとして就職したい」
そんな希望があるなら、就労移行支援がぴったりです。
就職に必要なスキルを段階的に学べるので、職場で必要な力をしっかり身につけられます。
また、ハローワークや企業と連携して求人情報を紹介してくれるところもあるので、就職活動もスムーズです。
本人の「働きたい気持ち」を育てるステップとして最適なんです。



3-2. 収入を得ながら支援を受けたいならA型
「いきなり一般就労は不安だけど、ある程度働ける力はある」
「収入を得ながら経験を積んでいきたい」
そんな方には、就労継続支援A型がおすすめです。
作業内容も比較的安定していることが多く、支援員さんの見守りがある中で働けるのが特徴です。
また、勤怠や体調管理の面でもしっかりサポートしてもらえるので、就労習慣を身につけたい方にも向いています。



3-3. 生活リズムを整えたい人はB型から
「まずは毎日外に出るところから始めたい」
「体調や気分の波があって、安定して働けないかも」
そんな方には、就労継続支援B型がぴったりです。
工賃(収入)は少なめですが、自分のペースで通えるのが最大のメリット。
いきなり「働くぞ!」というよりも、「まずは慣らしながら」生活リズムを整えることからスタートできます。



「働くこと=怖い」から「働くこと=楽しい」に変えるきっかけになる支援です。
4. 支援を受けるにはどうすればいい?
「うちの子に支援が合いそう!」と思っても、実際にどうやって申し込めばいいのか迷ってしまいますよね。
でも大丈夫です。
流れさえ分かっていれば、専門機関がしっかりサポートしてくれます。
ここでは、就労支援を受けるための基本的な流れと、知っておくと安心なポイントをまとめました。
4-1. まずは相談窓口に連絡してみよう
仕事支援を受けるには、まず「相談」からスタートします。
地域の福祉課、ハローワーク、障害者就業・生活支援センターなどが窓口になっています。
不安なことや困りごとを話すと、どの支援が合っているかを一緒に考えてくれます。
予約が必要な場合もあるので、事前に電話やメールで確認しておくと安心です。



4-2. 受給者証の申請が必要になることも
福祉サービスである「就労移行支援」「A型」「B型」などを利用するには、多くの場合「障害福祉サービス受給者証」が必要になります。
この申請は、お住まいの市区町村の役所(障害福祉窓口など)で行います。
主な手続きの流れは以下の通りです。
- 申請書を提出市区町村の窓口で手続きを行います
- サービス等利用計画の作成相談支援専門員がサポートしてくれます
- 審査・交付受給者証が発行されます



4-3. 体験利用で雰囲気を見てみよう
どの支援サービスも、いきなり通い始めるのではなく「見学」や「体験利用」ができます。
「実際の雰囲気に合いそうか」「本人が安心して通えるか」を見極めるためにも、体験はとても大切です。
事業所ごとに対応は違いますが、多くの場合、見学~数日の体験利用ができるようになっています。
保護者の付き添いもOKなところが多いので、ぜひ一緒に見てあげてくださいね。



支援は「受けてみようかな」と思ったときが、始めどきです。
5. 支援を選ぶときのチェックポイント
いざ支援を利用しようと思っても、どこの事業所を選べばいいか迷ってしまいますよね。
同じ「就労移行支援」や「A型」でも、場所によって雰囲気や対応は大きく違うんです。
だからこそ、見学や体験のときに「ここなら安心して通えそう」と思えるかどうかをしっかり確認することが大切。
この章では、支援先を選ぶときに見ておきたいポイントを3つにまとめてご紹介します。
5-1. スタッフの対応や雰囲気は安心できる?
まずは、支援スタッフの雰囲気をチェックしましょう。
親しみやすくて、話しかけやすいスタッフがいるかどうかはとても大事なポイントです。
特に発達障害のある方は、人の表情や言葉に敏感なことが多いので、「なんとなく怖いな」と感じる人がいると、通うのが難しくなってしまいます。



安心できる人がいる環境が、「通い続けたい」気持ちにつながります。
5-2. 作業内容は本人に合っているか?
事業所ごとに取り組んでいる作業内容は異なります。
軽作業が中心のところ、パソコン作業が多いところ、接客系の業務があるところなどさまざまです。
本人が「これならできそう」「やってみたい」と思える内容かどうかを、しっかり体験で確認してみましょう。
無理なく始められて、続けられる内容であることが、通所継続のカギになります。



5-3. 通いやすさや生活リズムとの相性も大事
忘れがちなのが「通いやすさ」や「生活リズムとのバランス」です。
せっかく良い支援先でも、毎回1時間以上かかってしまうと、それだけで通うのが負担になりますよね。
また、朝が苦手なお子さんや体調に波がある方の場合は、「午後からスタートできるか」なども大切なチェック項目です。



「内容」だけじゃなく「続けやすさ」も、支援選びの大切なポイントです。
6. 利用者の体験談から学ぶ成功のヒント
実際に支援サービスを利用した方たちの声を聞くと、「そんなふうに進めていけばいいんだ!」と気づくことって多いですよね。
うまくいった事例には、ちゃんと共通点や工夫があるんです。
ここでは、実際に仕事支援を受けた発達障害のある方やご家族の体験談を交えながら、成功のヒントを一緒に見ていきましょう。
6-1. 「就職できるなんて思ってなかった」Aさんの場合
20代のAさんは、学生時代から人との関わりが苦手で、卒業後も引きこもり気味の生活が続いていました。
お母さんのすすめで就労移行支援に通い始めたものの、最初は「無理だと思う」の一点張りだったそうです。
それでもスタッフの方の根気強いサポートで、少しずつ外出の機会が増え、半年後には企業実習にも参加。
そしてなんと、1年後には地元の企業に就職が決まりました。



「無理」だと思っても、環境が変わると未来も変わるんです。
6-2. 「無理のないペースで続けられた」Bさんのケース
B型支援を利用した30代のBさんは、体調の波が激しく、一般就労は難しい状態でした。
でも「毎日決まった時間に通うのは大変」という自分の特性を受け入れてくれる事業所に出会い、週2回・午前中だけの利用からスタートしました。
通い続けるうちに生活リズムが整い、笑顔が増えていき、2年後にはA型へのステップアップも叶いました。



ペースに合わせて支援してもらえるって、安心感がありますよね。
6-3. 「体験して初めてわかったことがいっぱい」Cさんの声
Cさんは、就労支援の説明を聞いただけではピンとこなかったそうですが、いざ体験してみると「自分にもできる作業がある」と感じたそうです。
事業所での作業は、黙々と集中できる軽作業が中心だったため、過度な人付き合いに悩まされることもなく、毎日気持ちよく通えるように。
最終的には、得意なパソコン作業を活かして、事務系の職場への就職にもつながりました。



7. 親としてできるサポートとは?
子どもが発達障害と診断され、「将来ちゃんと働けるのかな…」と不安になったこと、一度や二度じゃないですよね。
でも、実は親の関わり方次第で、子どもの自信や意欲がグッと変わってくるんです。
「支援はプロに任せる」と思いがちですが、家庭でのちょっとしたサポートが、本人の安心感につながります。
ここでは、親としてできる大切なサポートについて、具体的にお伝えしていきます。
7-1. 否定せずに、まずは受け止める
子どもが「働くのが怖い」「自信がない」と言ったとき、「そんなこと言わないで」と否定してしまうと、本人はますます殻にこもってしまいます。
大切なのは、「そう思ってるんだね」とまずは気持ちを受け止めてあげること。
本人が話してくれること自体が大きな一歩なので、受け止めるだけでも大きな意味があります。



共感は、どんな支援よりも心の支えになることがあります。
7-2. 一緒に情報を集めてみる
「就労移行って何?」「A型とB型ってどう違うの?」
こういった情報を、親が一緒に調べてくれると、本人も「自分のことを考えてくれてる」と感じて前向きになりやすいです。
インターネットで調べたり、見学先を一緒に選んだりと、手を取り合って進む感覚が本人の不安を和らげてくれますよ。



親も学びながら、一緒に伴走する姿勢が大切です。
7-3. 成功体験をたくさん褒めてあげる
「今日は時間通りに起きられた」「事業所に行けた」
そんな小さな成功も、しっかり認めてあげることが大切です。
特に発達障害のある子は自己肯定感が低くなりがちなので、できたことを褒めていくことで「自分にもできる」と少しずつ自信を育んでいけます。



親の言葉は、子どもにとって一番のエネルギー源になります。
8. まとめ|仕事支援を上手に活用して、自分らしい働き方を見つけよう
発達障害のある方にとって、「働く」ということは簡単なことではないかもしれません。
でも、だからこそ無理なく、自分に合った環境やサポートを受けることがとても大切なんですよね。
就労移行支援やA型・B型のような制度を活用すれば、焦らず少しずつ社会との接点を持ちながら、自信をつけていくことができます。
そして、親としても「見守り」「共感し」「寄り添う」ことが、何よりの支えになるのだと感じます。
どんな道を選ぶとしても、その子なりの“働き方”を一緒に見つけていけるといいですね。
- 発達障害の方には、自分に合った就労支援を選ぶことが大切
- 支援は「働きたい気持ち」を育て、自立への第一歩になる
- 親のサポートと共感が、子どもにとって最大の安心になる
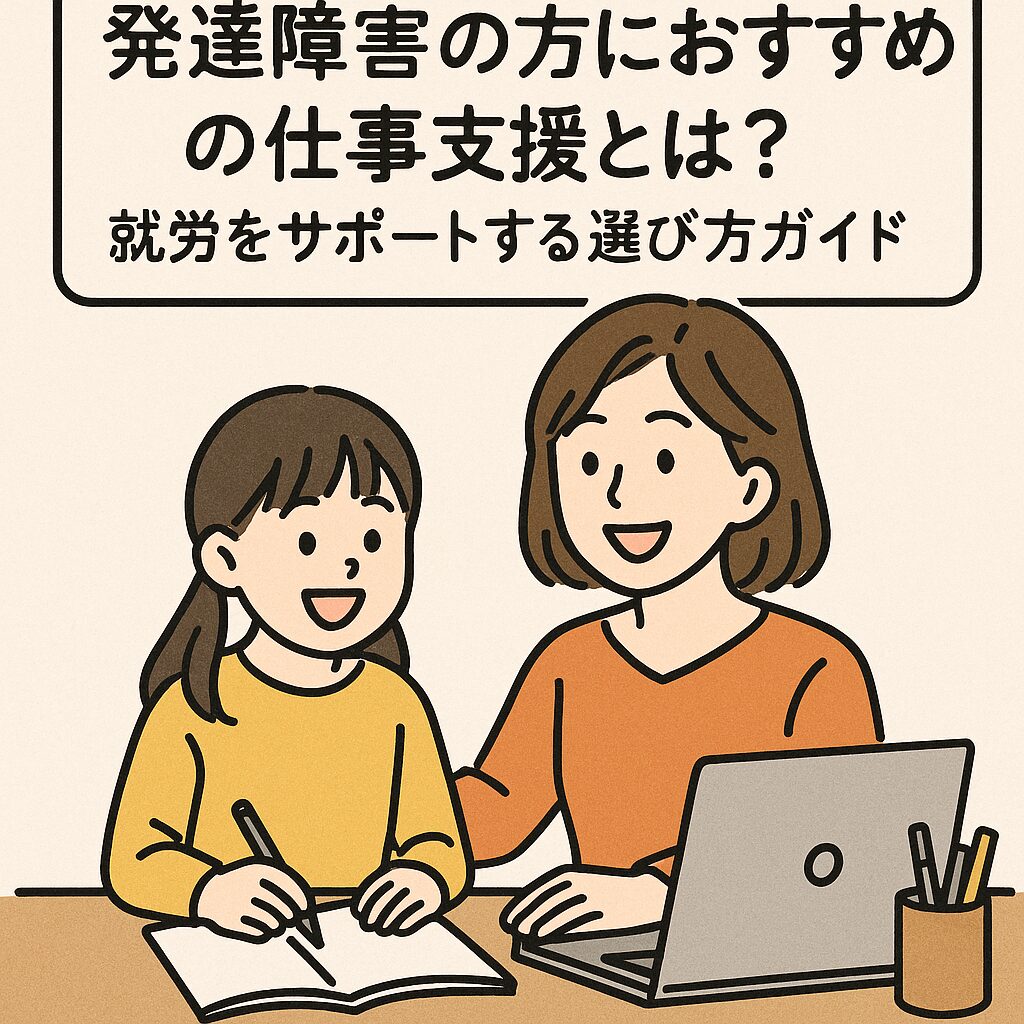
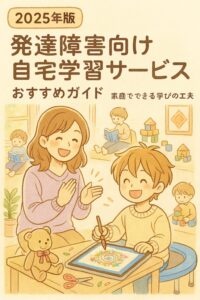


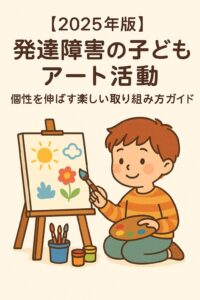




コメント