「何度も同じことを注意してしまう…」
「周りの子と比べてしまい、不安になる…」
「親として頑張りたいけれど、疲れてしまう…」
そんな風に感じることはありませんか?
発達障害の子育ては、予測できない行動や感情の爆発、周囲の理解不足 など、さまざまなストレスが重なります。
でも、ちょっとした工夫や考え方を変えることで、「親も子どももラクになる子育て」 ができるんです!
この記事では、発達障害の子育てで感じる ストレスの原因 や 具体的な対処法、活用できる支援サービス まで、わかりやすく解説していきます。
「少しでも気持ちがラクになった!」と思えるようなヒントを、ぜひ見つけてくださいね。
- 発達障害の子育てで感じるストレスの原因を理解する
- 具体的な対処法を知り、実践する
- 周囲のサポートや支援サービスを積極的に活用する
発達障害の子育てでストレスを感じる理由
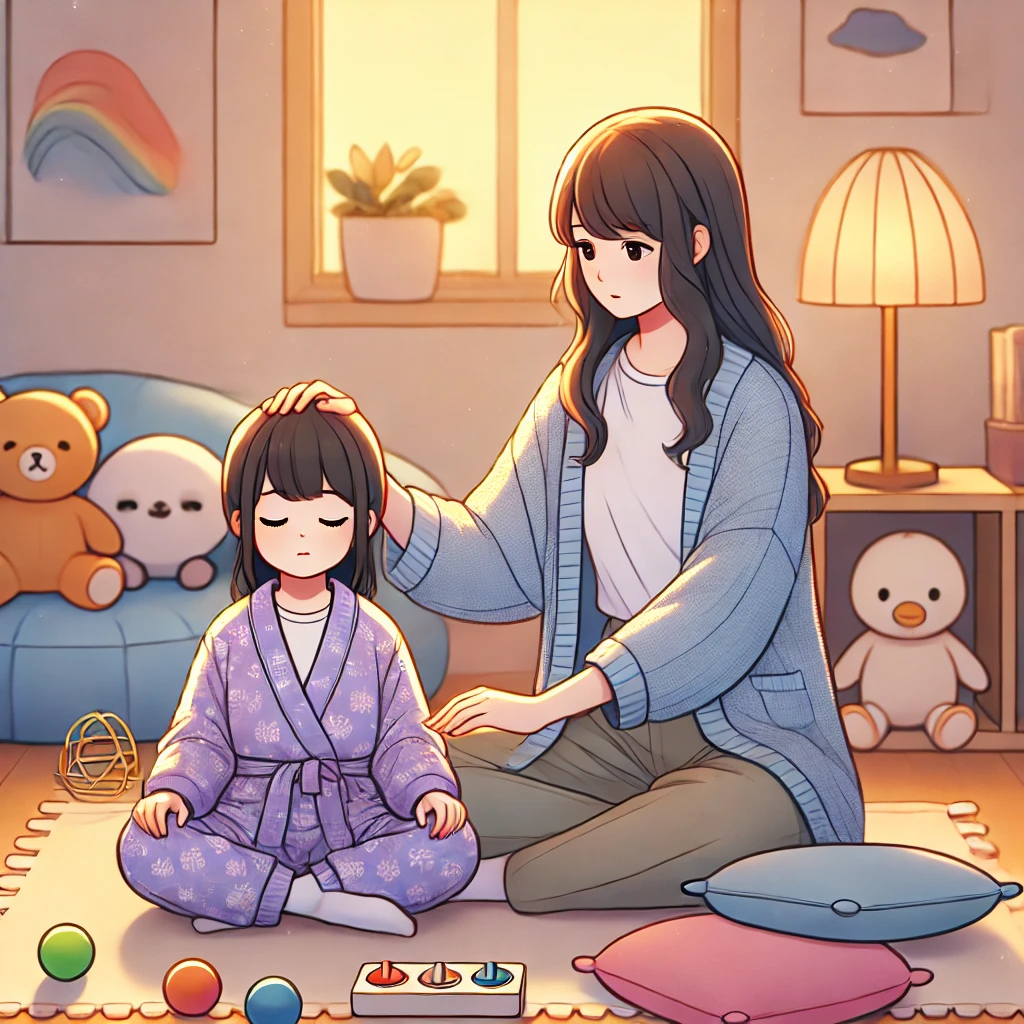
発達障害の子育てでは、さまざまなストレスを感じることが多いですよね。
「どうしてこんな行動をするの?」
「毎日、こんなに気を張っていたら疲れてしまう…」
そんな悩みを抱えている親御さんは少なくありません。
ストレスの原因を知ることで、適切な対策を考えやすくなります。
ここでは、発達障害の子育てでよくあるストレスの原因を整理していきますね。
1-1. 予測できない行動への対応
発達障害のお子さんは、突発的な行動を取ることが多いですよね。
例えば、急に走り出したり、大きな声を出したり、店の中で床に寝転んだり…。
「どうして今ここで?」と、親御さんが戸惑うことも多いのではないでしょうか?
特に、外出先や公共の場では、周囲の視線が気になり、よりストレスを感じやすくなります。
突然の行動に備えて「事前に予測できることはないか?」を考え、環境を整えることが大切です。
例えば、外出前にルールを決める、手を繋ぐなどの安全策を取る、視覚的なサポートを活用するなど、できる対策を試してみましょう。

1-2. 感情のコントロールが難しい場面
発達障害の特性として、感情のコントロールが難しいことが挙げられます。
例えば、遊びをやめたくない、おもちゃを取られた、思い通りにならない、などの理由で突然怒り出したり、大泣きしたり…。
些細なきっかけでパニック状態になり、なかなか落ち着かないこともありますよね。
感情の起伏が激しいと、親御さんも気が休まる時間がなく、ストレスが溜まってしまいます。
また、外出先や学校などの場面では、「この状況をどうすれば落ち着かせられるのか?」と焦ってしまい、よりストレスを感じることも…。
対策として、お子さんが落ち着ける環境を整えることが大切です。
例えば、お気に入りのアイテムを持たせる、静かな場所に移動する、感情を言葉で表現する練習をするなどの方法を試してみましょう。



1-3. 周囲からの理解不足
発達障害の特性は、外見からは分かりにくいため、周囲に理解されにくいことが多いです。
例えば、お店や電車の中で子どもが泣き叫んでいると、周囲から「しつけがなっていない」と思われることも…。
親としては、「ちゃんと対応しているのに…」「分かってくれない…」と辛い気持ちになりますよね。
また、学校や幼稚園・保育園での対応について、先生や他の保護者との意見の違いに悩むこともあります。
「普通の子と同じようにできるはず」と期待されると、親としてはプレッシャーを感じてしまいますよね。
そんなときは、発達障害について周囲に伝える工夫をしてみましょう。
例えば、先生や親しい人に、お子さんの特性を具体的に説明する、発達障害の理解を深める資料を活用するなどが有効です。



2. ストレスがたまる具体的なシーン


発達障害のお子さんを育てる中で、特にストレスがたまりやすい場面はどんなときでしょうか?
「朝の準備が全然進まない…」
「学校でトラブルが多くて、先生から毎日のように連絡が来る…」
「兄弟げんかが絶えなくて、毎日仲裁に入るのが大変…」
親御さんにとって負担の大きい場面を詳しく見ていきましょう。
2-1. 生活習慣のこだわりが強くて困る
発達障害のお子さんは、「いつもと同じでないと嫌!」という ルーティンへのこだわり が強いことがあります。
例えば…
✅ 「この服じゃないと着たくない!」
✅ 「朝食の順番が違うと食べたくない!」
✅ 「学校に行く前のルーティンが崩れるとパニックになる!」
毎朝、こうしたこだわりに対応しながら準備を進めるのは、とても大変ですよね。
対策として…
前日のうちに準備をする、
視覚支援(スケジュール表やピクトグラム)を活用する、
「こだわりの一部を残しつつ、少しずつ変化に慣れる練習をする」 などが効果的です。



2-2. 学校や集団生活でのトラブル
発達障害のお子さんは、学校や幼稚園・保育園などの集団生活でトラブルを抱えやすい傾向があります。
例えば…
✅ 指示を聞いても行動に移せない → 先生に叱られてしまう
✅ 順番を待つのが苦手 → 友達とトラブルになる
✅ 感覚過敏の影響で教室にいられない → 授業に参加できない
✅ 興味のあることに没頭しすぎて、周りが見えなくなる → 友達から「わがまま」と思われてしまう
こうしたことが原因で、「先生から呼び出しが頻繁にある」「クラスの友達とうまく関係が築けない」などの悩みを抱えている親御さんも多いのではないでしょうか?
対策として…
先生と連携し、本人の特性に合った対応をお願いする、
特性に合った学習環境(席の配置や支援員のサポート)を考える ことが重要です。
また、学校だけでなく 放課後デイサービス などの 発達支援の場を活用する のも一つの方法ですよ!



2-3. 兄弟・姉妹との関係
発達障害のお子さんがいる家庭では、 兄弟・姉妹との関係 に悩むケースも多いですよね。
例えば…
✅ 兄弟げんかが頻繁に起こる → 「お兄ちゃんばっかり!」「妹ばっかり!」と不満が出る
✅ 発達障害の子に手がかかりすぎて、他の子に構えない → 兄弟が「自分は大事にされていない」と感じてしまう
✅ 周囲との違いに気づいて「なんでうちの家はこうなの?」と聞かれる → どう説明すればいいか悩む
こうした兄弟間の問題は、親御さんの精神的な負担が大きいですよね。
「どちらも平等に育てたいのに、どうしてもうまくいかない…」と感じてしまうことも。
対策として…
兄弟一人ひとりと向き合う時間を作る、
「家族みんなで一緒にできること」を増やす、
発達障害について兄弟にもわかりやすく説明する などの方法を試してみてください。



3. ストレスを減らす考え方のコツ
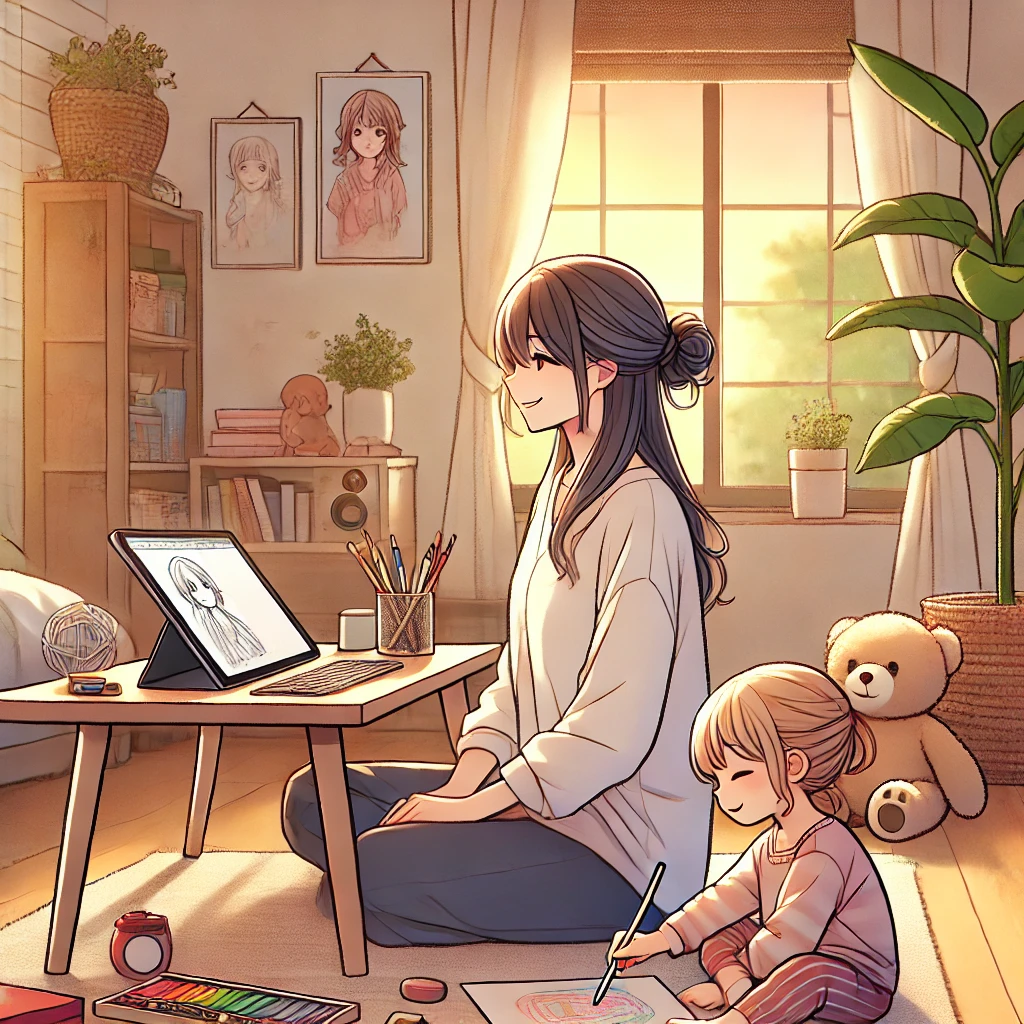
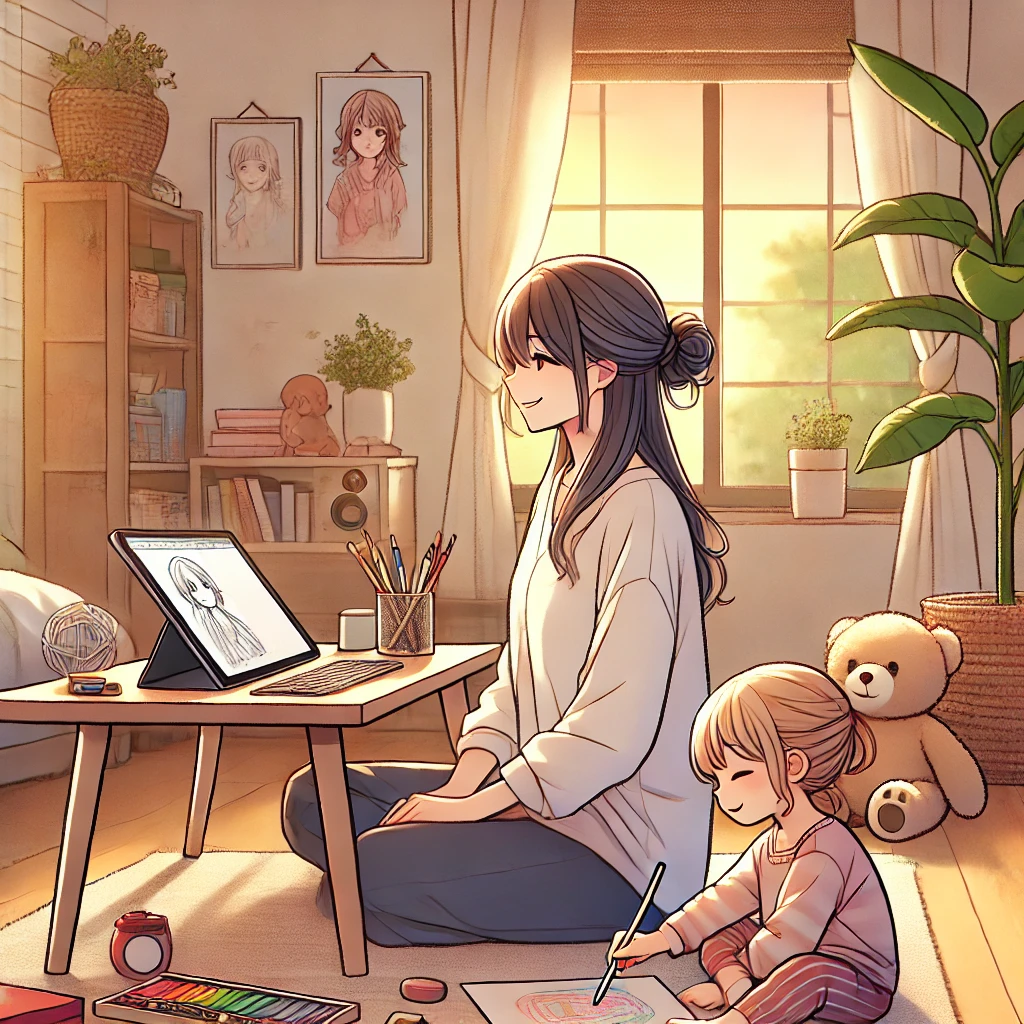
発達障害の子育てでは、「こうあるべき」 という考えにとらわれすぎると、ストレスがどんどん溜まってしまいますよね。
「普通の子と同じようにできないとダメ?」
「ちゃんと育てないと、将来困るんじゃ…?」
そんな不安が、親御さんをさらに追い詰めてしまうこともあります。
でも、大丈夫です!
少し考え方を変えるだけで、子育てのストレスをグッと減らせることもありますよ。
ここでは、発達障害の子育てをラクにする3つの考え方のコツ を紹介しますね。
3-1. 「できること」にフォーカスする
発達障害のお子さんは、苦手なことも多いですが、「得意なこと」や「できること」 もたくさんあります。
でも、つい 「他の子と比べて、できないことばかり目についてしまう」 ことってありませんか?
例えば…
✅ お友達と一緒に遊ぶのは苦手だけど、一人で集中して遊ぶのは得意
✅ 言葉での表現は苦手だけど、絵を描くのが上手
✅ 勉強は苦手でも、好きなことには驚くほどの集中力を発揮する
こうした 「できること」に目を向ける」 ことで、親御さん自身の気持ちがラクになります。
また、お子さんの 「得意なことを伸ばす」 ことで、自信にもつながりますよ!



3-2. 「普通」を求めすぎない
「普通の子どもと同じように育てなきゃ!」と思うほど、ストレスは増えてしまいます。
でも、「普通」って何でしょう?
実は、どの子にも「その子なりのペース」があるんですよね。
✅ みんなができることを同じようにできる必要はない
✅ その子なりの成長を大切にする
✅ 周りのペースではなく、子どものペースを意識する
「うちの子には、うちの子のペースがある」と考えることで、親御さんの心もラクになりますよ。



3-3. 親が完璧を目指さない
発達障害のお子さんを育てていると、「ちゃんと対応しなきゃ!」「もっと良い親にならなきゃ!」と、自分を追い詰めてしまうことがありますよね。
でも、親だって 「完璧」 でなくて大丈夫!
疲れたら休んでいいし、うまくいかないときがあってもいいんです。
✅ すべてを完璧にやろうとしない
✅ 無理なときは「助けを求める」
✅ 「まあ、いっか」と思うことも大事
発達障害の子育ては、「親の心の余裕」 もとても大切です。
自分を追い詰めすぎず、たまには手を抜きながらやっていきましょう!



4. 具体的なストレス対処法
発達障害のお子さんを育てる中で 「ストレスを軽減する工夫」 はとても大切です
「これ以上、毎日イライラしたくない…」
「少しでも楽に子育てできる方法はないの?」
そう感じることも多いですよね
ここでは ストレスを減らすための実践的な対処法 をご紹介します
4-1. 環境を整える(視覚支援・スケジュール化)
発達障害のお子さんは 「見て理解する情報」 のほうが得意なことが多いです
そのため 「視覚支援」や「スケジュール化」 を活用することで、ストレスを大幅に減らせます
例えば…
- 朝の準備 チェックリストやピクトグラムを活用する
- スケジュール 一日の流れを見える形で示す
- ルール作り 何度も言葉で説明するより、イラストや写真で伝える
視覚的に伝えることで 子ども自身が行動しやすくなり、親の負担も軽減 されますよ!



4-2. 行動パターンを理解して予測する
発達障害のお子さんは 「いつも同じパターンが安心する」 ことが多いです
逆に、急な予定変更や想定外のことが起こると パニックになりやすい ですよね
例えば…
- お出かけ 事前に「どこに行くのか」を伝える
- 予定変更 変更がある場合は早めに知らせる
- 苦手なこと 繰り返し練習することで安心感を持たせる
「次に何が起こるかわかる状態」 を作ることで、余計なストレスを減らせます



4-3. 親のリフレッシュ時間を確保する
発達障害のお子さんを育てるには 「親が元気でいること」 もとても大切です
「子ども優先だから、自分のことは後回し…」
そう思っていると、気づかないうちに 親の心が疲れ切ってしまう ことも
✅ 1日10分でも「自分の時間」を作る
✅ たまには家族や支援サービスを頼る
✅ 「自分を大切にすることは、子どもを大切にすること」と考える
例えば、子どもが寝た後の時間を、自分の好きなことに使う
レスパイトサービス(短期預かり)を活用する なども、親の心を守るためには大事なことですよ!



5. 周囲の協力を得る方法
発達障害の子育ては、「親だけで抱え込まないこと」 がとても大切です。
「一人で頑張らなきゃ…」と無理をすると、親の負担が大きくなりすぎてしまいますよね。
家族や学校、支援機関と連携することで、子育てのストレスを軽減できますよ!
ここでは 周囲の協力を得るための3つの方法 をご紹介します。
5-1. 家族に発達障害を理解してもらう
発達障害のお子さんを育てる中で 「家族の理解がない」 ことに悩む方も多いですよね。
例えば…
✅ 祖父母が「しつけの問題」と誤解している
✅ パートナーが育児に協力的でない
✅ 兄弟姉妹が「なんであの子ばっかり?」と不満を持っている
こうした誤解やすれ違いを防ぐためには、発達障害の特性について、家族と共有することが大切 です。
対策として…
- 家族向けの発達障害の本や資料を見せる 発達障害の基本を学んでもらう
- お子さんの特性について具体的に説明する 「〇〇が苦手だから、こう対応してほしい」と伝える
- 成功した対応法を共有する 「こうすると落ち着くよ!」とポジティブな方法を伝える
家族が理解してくれると、子育ての負担がぐっと軽くなりますよ!



5-2. 学校や支援機関との連携
発達障害のお子さんにとって、「学校の環境」 はとても重要です。
でも、先生や学校が発達障害の特性を理解してくれないと、子どもにとっても親にとっても大きなストレスになりますよね。
例えば…
✅ 授業中にじっと座っていられず、先生に叱られてしまう
✅ 友達とのコミュニケーションがうまくいかず、孤立してしまう
✅ 感覚過敏があるのに、配慮のない環境で過ごしている
こうした問題を減らすためには 「学校と協力しながら環境を整えていく」 ことが大切です!
対策として…
- 先生と定期的に情報共有をする 連絡帳や面談を活用し、子どもの特性を伝える
- 支援が必要なことを学校に相談する 通級や特別支援学級の活用を検討する
- 外部の支援機関とつながる 児童発達支援センターや放課後デイサービスを活用する
学校や支援機関と連携することで、親の負担を減らしながら、子どもに合った環境を作る ことができますよ!



5-3. 同じ悩みを持つ親とのつながりを作る
発達障害の子育ては、「周りに相談できる人がいない…」 という孤独感が大きなストレスになりますよね。
「誰にもこの気持ちを分かってもらえない…」と感じると、心が疲れてしまいます。
でも、「同じ悩みを持つ親同士」で話をすると、驚くほど気持ちが楽になることも!
対策として…
- 発達障害の親の会に参加する 地域の交流会や支援グループを探してみる
- オンラインコミュニティを活用する SNSや掲示板で同じ悩みを持つ親とつながる
- カウンセリングを受けてみる 専門家に相談しながら、心の負担を軽減する
発達障害の子育ては「一人で頑張るものではなく、みんなで支え合うもの」です。
親同士で情報交換したり、励まし合うことで、気持ちがぐっと楽になりますよ!



6. 発達障害の子育てに役立つ支援サービス
発達障害の子育ては、「親だけで頑張りすぎないこと」 がとても大切です。
「もっと助けてくれる場所があればいいのに…」
「少しでも負担を軽くしたい…」
そんなときは、支援サービスを積極的に活用する のがおすすめです!
ここでは 発達障害の子育てに役立つ3つの支援サービス をご紹介します。
6-1. 児童発達支援・放課後デイサービス
発達障害のお子さん向けの支援施設として、「児童発達支援」や「放課後デイサービス」 があります。
✅ 児童発達支援(未就学児向け) → 発達に合わせた療育や集団活動ができる
✅ 放課後デイサービス(小学生~高校生向け) → 学校の放課後や休日に利用できる支援施設
メリットとして…
- 発達支援が受けられる 専門スタッフが子どもの特性に合った支援をしてくれる
- 親の負担が軽減する 送迎付きの施設もあり、親の時間を確保できる
- 子どもが安心して過ごせる場所になる 家や学校以外の「居場所」ができる
「うちの子にも合うかな?」と思ったら、地域の支援センターに相談してみるのがおすすめ ですよ!



6-2. ペアレントトレーニング
「ペアレントトレーニング」とは、発達障害の子育てに役立つ親向けのプログラム です。
「子どもへの対応が分からなくて、毎日疲れてしまう…」
「もっと子どもとの関わり方を学びたい!」
そんな方にぴったりの支援サービスですよ!
ペアレントトレーニングでは…
✅ 発達障害の特性を学ぶ → 「なぜこの行動をするのか?」が分かる
✅ 子どもに合った対応方法を学ぶ → 具体的な声かけや接し方の工夫を知る
✅ 悩みを共有できる → 他の親と交流しながら学べる
自治体や発達支援センターで開催されていることが多いので、ぜひチェックしてみてくださいね!



6-3. 一時預かり(レスパイトケア)
発達障害のお子さんを育てていると、「少しの間でもいいから、一人の時間が欲しい…」と感じることもありますよね。
そんなときにおすすめなのが 「レスパイトケア(短期預かり)」 です。
✅ 一時的に子どもを預かってもらえる
✅ 親がリフレッシュできる時間を確保できる
✅ 預かり中に専門的な支援を受けられることもある
「親が休むのは悪いこと…?」なんて思わなくて大丈夫!
「親が元気でいること」が、子どもにとっても一番大切 なんです。
レスパイトケアは、市区町村の福祉サービスや、発達障害支援センターなどで実施されています。
気になる方は、地域の福祉課や支援センターに相談してみましょう!



7. 親自身のケアも大切!ストレス解消のポイント
発達障害の子育てでは、「親自身の心と体のケア」 もとても大切です。
「子どもが最優先だから、自分のことは後回し…」
「でも、もう限界かもしれない…」
そんなふうに感じることはありませんか?
親が心身ともに元気でいることが、子どものためにもなります!
ここでは、親自身のストレスを減らし、元気に子育てを続けるための 3つのポイント を紹介します。
7-1. 1人の時間を確保する
発達障害の子育てでは、常に気を張り続けてしまう ことが多いですよね。
子どもが安心して過ごせるようにと頑張るあまり、親自身が休む時間がなくなってしまうことも…。
でも、「少しでも1人の時間を持つこと」 が、ストレスを減らす大きなポイントになります!
- 子どもが寝た後の時間を、自分の好きなことに使う
- パートナーや家族にお願いして、短時間でも1人で外出する
- 自治体の一時預かりサービスを活用する
「たった10分でもいいから1人の時間を作る」
それだけで、気持ちがグッと楽になりますよ!



7-2. カウンセリングやセルフケアを取り入れる
発達障害の子育てでは、「誰にも相談できない…」と孤独を感じることもありますよね。
そんなときは、専門家のカウンセリングやセルフケアを取り入れること で、気持ちがラクになることもあります。
- 発達障害専門のカウンセラーに相談する → 悩みを整理し、具体的なアドバイスをもらえる
- オンラインカウンセリングを活用する → 自宅にいながら気軽に相談できる
- ヨガや瞑想などのリラックス法を試す → 日常のストレスを軽減できる
「話すだけでスッキリした!」
そんなことも多いので、ぜひ試してみてくださいね!



7-3. 無理しない子育てを心がける
発達障害のお子さんを育てていると、「もっと頑張らなきゃ!」と自分を追い詰めてしまいがちですよね。
でも、大事なのは 「無理しすぎないこと」 です!
- できることだけを頑張る → 100%完璧を目指さなくても大丈夫!
- 「まあ、いっか」と思うことも大切 → 多少うまくいかなくてもOK!
- 周りの助けを遠慮なく借りる → 支援サービスや家族の協力を活用する
「親だって人間だから、疲れるのは当たり前」
そう思うことで、気持ちが少し軽くなりますよ!



8. まとめ
発達障害の子育ては、親の負担が大きくなりやすい ですが、適切な対処法を取り入れることで ストレスを軽減することができます。
ここまでの記事を振り返り、重要なポイントを3つ にまとめました!
- ストレスの原因を知り、適切な対策を考える
- 周囲の協力を得て、一人で抱え込まない
- 親自身のケアを大切にしながら、無理しない子育てを心がける
発達障害の子育ては、決して一人で頑張るものではありません。
支援サービスを活用したり、家族や学校と連携したりしながら、無理なく続けられる子育ての形を見つけていきましょう!
「うまくできなくても大丈夫!」
「無理しすぎないことが、結果的に子どもにとっても良い環境になる!」
そんな気持ちで、少しずつ前に進んでいけたらいいですね。



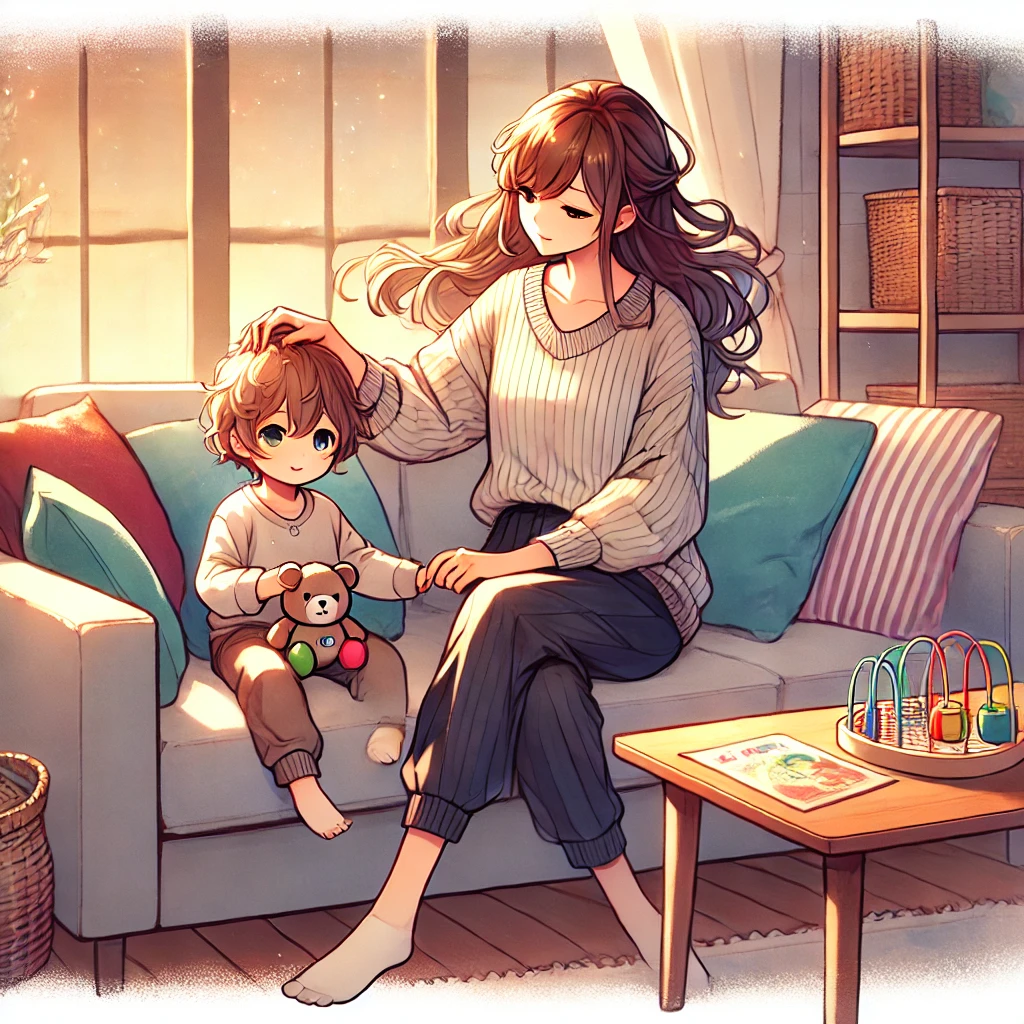



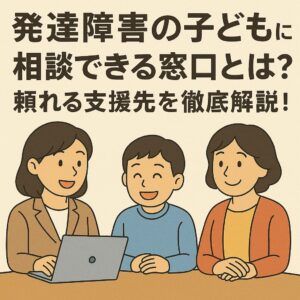



コメント