発達障害のあるお子さんを育てる中で、こんなふうに感じたことはありませんか?
「この子は言葉での表現が苦手だけど、絵を描くのが好きみたい」
「他の習い事は合わなかったけれど、アートなら集中できるんです」
アート活動は、そんな発達障害のある子どもたちにとって、無理のない自己表現の手段としてとても有効なんです。
難しい技術やルールに縛られず、自分の気持ちを自由に表現できるアートには、可能性がたくさん詰まっていますよ。
今回は、家庭でできる取り組みから、教室・社会とのつながりまで、発達障害の子どもに合ったアート活動の始め方と広げ方をご紹介します。
ぜひ一緒に、お子さんの「好き」を伸ばすヒントを見つけていきましょう!
- 発達障害の子にアート活動が向いている理由
- 家庭や教室でのアート活動の進め方
- アートを通じて広がる社会とのつながり
1. 発達障害の子にとってのアート活動とは?

発達障害のある子どもたちは、言葉でのやりとりや集団行動が苦手なことがありますよね。
でも、そんな子どもたちにも、自分らしく表現する力や、心の中に広がるイメージはたくさんあるんです。
そこで注目されているのが、アート活動。
お絵かきだけでなく、工作や粘土、写真やデジタルアートまで含めた広い意味での「アート」は、子どもの個性や感性をそのまま活かせる素晴らしい場になります。
アート活動は、子どもが「自分らしくいられる時間」を作ってくれるんです。
ここではまず、「アートって何?」「発達障害の子どもとどんなふうに関係があるの?」という基本から解説していきますね。
1-1. アート活動の基本と広がり
アート活動と聞くと、絵を描くことだけをイメージしがちですが、実はとっても幅広いんです。
たとえば…
- 絵画クレヨン・絵の具・色鉛筆などを使って描く
- 工作紙・段ボール・自然素材などで自由に形づくる
- 粘土・立体手先を使って形を作る活動
- デジタルアートタブレットやパソコンを使った表現
- 音・光とのコラボ音楽や照明を使った創作も
「作品を完成させること」よりも、「表現して楽しむこと」が大事なアート。
発達障害の子どもにとって、その自由さはとても大きな魅力になりますよね。

1-2. 発達障害の子とアートの相性
発達障害の子どもたちは、言語や対人コミュニケーションが苦手だったり、感覚がとても敏感だったりします。
その一方で、「色へのこだわり」や「細部への集中力」「独自の視点」など、アートに向いた特性を持っていることが多いんです。
アートは、そうした子どもたちの個性をそのまま活かせる表現手段として、とても相性がいいんですよ。
たとえば、
・視覚優位で細かいところに気づく → 緻密な描写が得意
・空想力が豊か → 独創的な表現ができる
・手を動かすのが好き → 工作や粘土が楽しめる
など、お子さんの得意な部分が自然と作品にあらわれてくることも。
「苦手を補う」のではなく「得意を活かす」関わりができるのが、アートの良さなんです。



1-3. 表現する力は誰にでもある
「うちの子、絵が上手じゃないから…」
そう思ってしまうお母さんもいらっしゃるかもしれません。
でも、アートに“上手・下手”は関係ありません。
大切なのは、その子なりの感情や思いを、自分のやり方で外に出してみること。
それが絵の具の色の選び方だったり、紙の破り方だったり、線の描き方だったり…
どんな表現も「その子らしさ」が詰まっているんです。
親としても「すごい!」と評価するより、「こんなふうに描いたんだね」「この色好きなんだね」と気づいて寄り添う姿勢が大切ですね。
表現する楽しさを知った子どもは、自然とアートに夢中になっていきますよ。



2. アート活動が発達障害の子に与える良い影響


発達障害のある子どもたちは、学校や集団生活で「うまくいかない体験」を積み重ねやすいものです。
でも、アート活動はそんな子どもたちにとって、自分らしくいられる「安心できる居場所」になります。
アートを通して得られる達成感や自己表現の喜びは、子どもの心を豊かに育ててくれるんですよ。
ここでは、アート活動が子どもにどんな良い影響を与えてくれるのか、3つの視点から詳しくご紹介します。
2-1. 自己肯定感が高まる
発達障害のある子は、「失敗体験」が多くなりがちです。
周囲と比べられてしまったり、自信をなくしてしまうこともありますよね。
でもアートには「間違い」も「正解」もありません。
「こんなふうに描きたい」「この色が好き」
その気持ちだけで、立派な作品が生まれるんです。
できた作品を大切に扱ってあげるだけで、子どもは「認めてもらえた」「わたしの絵って価値がある」と感じられます。
この体験が、自己肯定感をじわじわと高めていくんです。
毎日の中で「できたね」「素敵だね」と声をかけるだけでも、子どもの表情が変わっていきますよ。



2-2. 感情表現の手段が広がる
発達障害の子どもたちの中には、自分の気持ちを言葉で表すのが苦手な子も多いですよね。
「何がイヤなのか説明できない」
「怒っているけど黙りこんでしまう」
そんなときに役立つのがアートなんです。
絵や工作は、子どもにとって「もう一つのことば」になります。
・ぐるぐる線を描いているときは怒ってるのかも
・やさしい色合いなら落ち着いているのかな
このように、作品から子どもの気持ちを感じ取るヒントがたくさん得られます。
表現の幅が広がることで、子ども自身のストレスもぐっと軽くなるんですね。



2-3. 集中力・継続力の向上にもつながる
「集中できない」「すぐ飽きる」
これは多くの親御さんが悩むポイントですよね。
でも、アート活動では不思議と集中できる子が多いんです。
「この色を塗りたい」「ここに模様を入れたい」
そんな気持ちが原動力になって、30分、1時間と夢中になることも。
「これだけ集中できるなら、ほかの場面でも力を発揮できそう」と思えるかもしれません。
また、完成したときの達成感が「またやりたい!」という気持ちにつながり、自然と継続する力も育っていきます。
アートは、集中と継続の力を“楽しみながら育てられる”貴重な機会なんですね。



3. 家庭でできるアート活動のはじめ方


「アート活動って、特別な道具がないと始められないのかな?」
「絵が苦手な私でも、子どもと一緒に楽しめる?」
そんな風に思っている方も、けっこう多いんですよね。
でも大丈夫。
アートは、身の回りのもので気軽に始められるんです。
ここでは、おうちでできるアート活動のはじめ方を3つのポイントに分けてご紹介します。
「やってみたい」と思ったときが、始めどき。
難しく考えず、まずはお子さんと一緒にやってみることから始めてみましょう。
3-1. 用意するものは?まずは身近な道具でOK
家庭でのアート活動は、高価な画材をそろえる必要はありません。
まずは、家にあるもので十分です。
- 紙類コピー用紙、新聞紙、段ボール、チラシの裏など
- 描く道具クレヨン、色鉛筆、水性ペン、ボールペン
- 貼る・切るのり、はさみ、テープ、折り紙
- 飾るマスキングテープ、シール、スタンプ
慣れてきたら、100円ショップの「おえかきセット」などを使ってみるのも楽しいですよ。
また、タブレットやスマホを使ったお絵描きアプリも最近は充実しているので、デジタルアートに興味がある子にもおすすめです。



3-2. 子どもの反応を観察しながら進めよう
アート活動を始めたとき、最初に大切なのは「上手にやらせよう」と思わないこと。
自由に描いたり、思いつくままに手を動かすことがアートの楽しさなんです。
・ぐちゃぐちゃに塗ってもOK
・途中でやめてもOK
・作品を完成させなくてもOK
この「OK」をたくさん出してあげることが、子どもにとっては安心なんですよね。
また、お子さんが夢中になるタイミングや、すぐに飽きてしまう様子などをよく観察することも大切です。
その子に合ったペースやスタイルを一緒に見つけていく感覚で、関わってみましょう。
親が構えず「一緒に楽しむ」気持ちでいると、自然と良い雰囲気が生まれますよ。



3-3. アート活動を日常に取り入れるコツ
特別な時間を作らなくても、アートは日常の中でちょこちょこ取り入れられます。
たとえば…
- お絵かきタイムを朝10分だけ設ける習慣にしてみると、リズムができて安心感に
- 食後の余った時間に工作牛乳パックや紙皿を活用するのも楽しい!
- 作品を壁に貼ってギャラリー化家族で見せ合いっこすることで、自己肯定感UP
また、「今日はどんな気持ち?」と声をかけて、お絵かきで表してもらうのもいいですね。
アートが「特別なもの」ではなく、「いつものこと」になると、子どもも自然と取り組みやすくなります。
毎日のちょっとした工夫が、表現の幅を広げていくんです。



4. アート活動を支えるおすすめの習い事や教室
おうちでのアート活動をきっかけに、「もっと本格的にやらせてみたいな」と感じたら、ぜひ検討してほしいのがアート教室です。
最近では、発達障害の子どもたちを対象にした、専門性の高いアートスクールや支援プログラムも増えてきました。
先生の関わり方や環境が整っている教室なら、安心して参加できますし、子ども自身も自分の「好き」を伸ばしていけるんですよ。
ここでは、教室の選び方や注目のスタイルについて、3つの視点でご紹介しますね。
4-1. 発達障害に理解のあるアート教室とは?
アート教室と一口に言っても、カリキュラムや先生の方針はさまざまです。
発達障害のある子どもにとって大事なのは、「理解のある環境」であること。
具体的には、以下のような特徴があると安心です。
- 少人数または個別対応子どものペースに合わせてゆったり進められる
- 発達障害への理解がある講師無理のない声かけや対応ができる
- 成功体験を重視する作品づくりの過程を大切にしてくれる
また、地域の「放課後等デイサービス」でアートプログラムを取り入れているところもあります。
見学や体験レッスンで雰囲気をつかむのも大切ですよ。



4-2. 教室選びのチェックポイント
実際に通える教室を探すときは、次のようなポイントに注目してみてください。
| 体験レッスンの有無 | 事前に子どもとの相性や教室の雰囲気を確認できる |
| 通いやすさ | 送迎の負担が少なく、長く続けられる距離かどうか |
| 作品への関わり方 | 完成度よりも楽しさ・達成感を重視しているかどうか |
教室のHPや口コミも参考になりますが、最終的には「子どもが楽しそうにできるかどうか」が一番のポイント。
親の目線だけでなく、子どもの「やってみたい」「楽しかった」を大事にしてあげたいですね。



4-3. オンラインで学べるアート活動も
最近は、対面だけでなくオンラインで学べるアート教室も人気です。
「外出が苦手」「感染症が心配」「近くに教室がない」そんなご家庭にもぴったりなんですよ。
オンライン教室のメリットはこんな感じです。
- 自宅で受講できるリラックスした環境で集中しやすい
- 時間が柔軟録画視聴や短時間のクラスも選べる
- 親子で一緒に参加できるサポートしながら取り組めるので安心
YouTube、Zoom、教材付きのプログラムなど、形式もいろいろあります。
最初は無料コンテンツから始めて、「この子に合ってるかも」と感じたら有料クラスに進むのもおすすめです。



5. アート活動を通じた親子コミュニケーションの広がり
アート活動は、子ども自身の表現力を育てるだけではありません。
親子の心をつなぐコミュニケーションのツールにもなるんですよ。
「作品を一緒に作る」「話を聞く」「共感する」そんな小さなやりとりの中に、たくさんの気づきや成長が生まれていきます。
ここでは、アートを通じて親子の関係がより豊かになる3つの視点をお届けしますね。
5-1. 一緒に楽しむことの価値
アート活動の中で、ぜひ大切にしてほしいのが「親も一緒に楽しむこと」。
「見てるだけ」ではなく、「一緒に描く」「一緒に作る」ことで、子どもは驚くほど生き生きとしてきます。
「ママもやってる」「一緒にできる」って、子どもにとってはすごく嬉しいんですよね。
しかも、作品づくりは言葉よりも自由で感覚的なやりとりなので、気持ちがストレートに伝わりやすいんです。
笑いあったり、驚いたり、ほめたり。
そんな感情のやりとりが、親子の心をぐっと近づけてくれます。
「忙しくてゆっくり話す時間がない…」というお母さんにも、アート活動はぴったりの時間づくりになりますよ。



5-2. 子どもの世界を理解するきっかけに
お子さんの描いた絵や、作った工作をじっくり見ると、「あれ?こんな感性持ってたんだ!」と驚くことってありませんか?
アートには、言葉では説明しきれない「その子の世界」がたくさん詰まっているんです。
・選ぶ色
・形や構図
・モチーフの意味づけ
・描く順番や勢い
そういった細かな部分から、今の気分や考えていることがふと見えてくることもあります。
「こんな見方をしてるんだね」と知ることは、子どもへの理解を深める大きな手がかりになります。
絵を見て「これはなに?」ではなく、「この色ステキだね」「どんな気持ちで描いたの?」と聞いてみるだけでも、子どもはうれしそうに語ってくれますよ。



5-3. 親も気づきを得られる時間に
アート活動を一緒にしていると、子どもだけでなく、お母さん自身にもさまざまな気づきが訪れます。
「こういう表現もあるんだな」
「自分の子どもって、思ってたより自由なんだな」
「小さなことに喜ぶって、いいなあ」
そんなふうに、子育てに対する見方がふっとやわらかくなる瞬間ってあるんですよね。
また、子どもの作品に触れながら、日々の悩みがちょっと軽くなったり、自分の感性にも気づけたりすることもあります。
何より、アートに「正解」がないからこそ、親もリラックスして関われるんです。
作品ができあがったときの「楽しかったね」の一言が、親子にとって特別な思い出になるはずです。



6. 支援機関や専門家とつながる方法
「うちの子に合う支援って、どこに相談すればいいの?」
「アート活動が好きなことは分かったけど、この先どう伸ばせば?」
そんなときは、専門家や支援機関とつながることを意識してみましょう。
地域には、発達障害の子どもやその家族を支える窓口や制度がたくさんあります。
また、アートに特化した支援団体やイベントも全国に広がっていますので、うまく活用すれば、お子さんの成長にぴったりの「次の一歩」が見つかるかもしれませんよ。
6-1. 地域のアート支援団体を活用しよう
実は全国には、発達障害や特別支援を必要とする子どもたちに向けたアート活動を支える団体がいくつも存在します。
・アートを通じた福祉活動をしているNPO法人
・障害児の創作を支援する地域ボランティア団体
・自治体と連携した無料のワークショップイベント
このような団体では、気軽に参加できるアートイベントや、子どもの創作活動を応援するプログラムが用意されているんです。
また、参加者同士の交流の場になることもあり、親同士が悩みを共有できる場としても貴重ですよ。
まずはお住まいの市町村名+「発達障害 アート 支援」などで検索してみてください。



6-2. 専門家と連携して広がる可能性
子どものアート活動を通して「この表現、意味があるかも?」と感じたときは、専門家のサポートを受けることも検討してみましょう。
たとえば…
- 発達支援センター子どもの特性に合った学びや支援方法をアドバイス
- 臨床心理士・作業療法士創作活動が感情表現や発達にどう関係しているかを見立て
- 支援付きアート教室の専門講師スモールステップでの指導に精通
お母さんだけで抱え込まず、誰かに相談できる場所があるだけで心が軽くなることもありますよね。



6-3. 相談窓口や助成制度の情報もチェック
実は自治体によっては、アート活動に関わる支援制度や助成金も用意されています。
・福祉施設の利用料補助
・創作活動に使える物品の支給
・親子アートイベントの参加費助成
など、内容はさまざまです。
また、「子育て支援センター」「発達障害支援センター」「地域包括支援センター」などにも、役立つ情報が集まっています。
知らないだけで、利用できる制度がたくさんある可能性もありますので、一度問い合わせてみる価値は大いにあります。
特に、アート活動が療育や発達支援の一環として認められている地域では、積極的な支援が期待できますよ。



7. 発達障害の子のアート作品を社会につなげる
「うちの子の作品、もっとたくさんの人に見てもらえたらいいのに」
そう思ったこと、ありませんか?
アート活動は、自宅や教室の中だけにとどまらず、社会とつながる手段にもなるんです。
誰かに見てもらえることで、子ども自身のモチベーションが高まり、自己肯定感も育ちます。
この章では、「発表の場」「発信の方法」「未来の可能性」など、アートを社会につなげる3つのステップをご紹介します。
7-1. 展示会・コンテストに参加してみよう
全国には、障害や特性のある子どもたちのアート作品を対象にした展示会やコンクールがたくさんあります。
たとえば…
- 市民ギャラリーや福祉施設での展示地域密着型で気軽に参加できる
- 発達支援団体主催の公募展作品を郵送するだけでOKのケースも
- 全国規模のキッズアートコンクール大きな励みにもなるイベント
「うちの子にはまだ早いかも…」と思う必要はありません。
見てもらえる・認めてもらえる経験は、子どもにとって大きな自信になります。
親としても「この子、こんなに頑張ってたんだ」と感動することもありますよ。



7-2. SNSで作品を発信するという選択
外に出て発表するのが難しいという方には、SNSを使った作品発信もおすすめです。
インスタグラムやX(旧Twitter)では、「#発達障害アート」「#こどもアート」などのタグでたくさんの作品が投稿されています。
たとえば…
- 親が作品だけを投稿する顔や名前を出さずに紹介できる
- 共感のコメントが励みに他の家庭との交流が生まれることも
- 親子の記録としても活用可能作品をアルバムのように残せる
ただし、プライバシーには十分注意してくださいね。
個人が特定される情報は控えるのが安心です。
“誰かに見てもらう喜び”を、家庭にいながら体験できるのがSNSの良さです。



7-3. アートを活かした未来の仕事のヒント
「絵が好き」「工作が得意」
それは、将来の「仕事」につながるヒントにもなるかもしれません。
もちろん今すぐではありませんが、「好き」が続いていくことで見えてくる未来もあります。
たとえば…
- イラストレーターやキャラクターデザインパソコンやタブレットで描くのが得意な子に
- 福祉施設での創作活動指導アートを通じた支援のお仕事も
- 雑貨販売やクラフト作家作品をネットで販売するという道も
「この子の世界観、すごく独特!」
そんな視点が将来の武器になる時代なんです。
まずは家庭で、表現する楽しさを育てていきましょう。



8. まとめ|アート活動で子どもの「好き」が花開く
発達障害のある子どもにとって、アート活動は単なる“お絵かき”ではなく、自己表現・成長・社会参加を支える大切な手段になります。
「話すのが苦手」
「集団がつらい」
「でも、描くことは大好き」
そんなお子さんの「好き」を活かせる場所が、アートの世界には広がっているんですよ。
親がそっと寄り添って、少し背中を押してあげるだけで、子どもたちはどんどん表現していけます。
おうちでの遊びからはじまって、教室やイベント、SNSや将来の仕事へ…
アートには、子どもの世界を広げる大きな力があります。
焦らず、比べず、子どもの「やりたい」を大切に育てていきましょう。
- アートは発達障害の子にとって自然な自己表現の手段
- 家庭・教室・支援機関など環境によって広がりやすい
- 作品を発表することで自信や将来の可能性が育つ

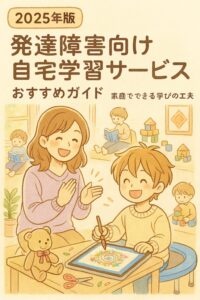
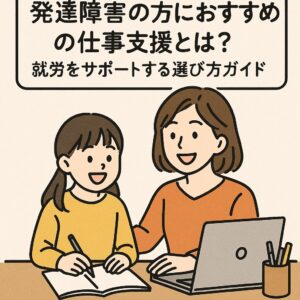






コメント