「うちの子、何が得意なんだろう…」
発達障害の子どもを育てる中で、こんなふうに感じたことはありませんか?
ついつい「他の子と比べてできないこと」ばかりに目がいきがちですが、実は発達障害のある子どもには、他の子にはない「尖った才能」が隠れていることも多いんですよね。
でも、その才能ってどうやって見つければいいの?
どこに注目すれば「この子の得意」が見えてくるの?
この記事では、発達障害の子どもに眠っている才能を見つける方法と、その伸ばし方について、やさしく・わかりやすく解説していきます。
どんなお子さんにも、きっと光るものがあります。
ママのまなざしで、その「原石」を一緒に見つけてあげましょう。
- 発達障害の子にも才能がある理由
- 才能を見つけるための具体的なヒント
- 家庭でできる才能の伸ばし方
1. 「才能がない子なんていない」って本当?
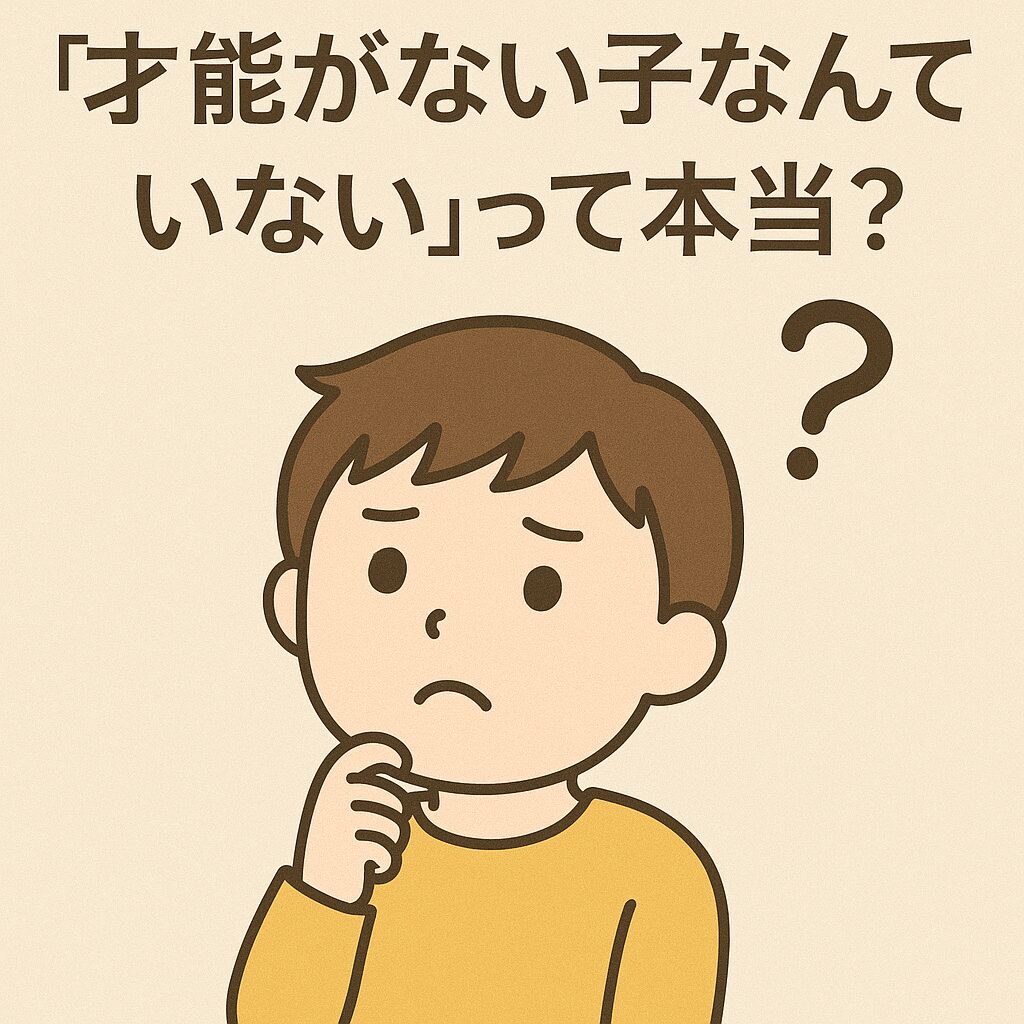
子どもに発達障害があると、「できないこと」「苦手なこと」にばかり目がいってしまいがちですよね。
でも、本当に「才能がない」のでしょうか?
答えはNOです。
発達障害の子どもは、得意なこと・苦手なことの差が大きい、いわゆる「凸凹(でこぼこ)」のある発達をしていることが多いんです。
つまり、苦手が目立つ一方で、実はとても尖った得意や個性を持っていることも多いということ。
「人と関わるのは苦手だけど、ずっと同じことに集中できる」
「会話は苦手だけど、絵や数字には強い」
そんな子どもたちの「好き」「得意」にこそ、隠れた才能が眠っているんです。
それを見つけるには、周囲の「気づき」と「理解」がとても大事になります。
そして、その役割を一番担っているのは、やっぱり毎日そばにいるママなんですよね。
では、どうやってその才能に気づいてあげられるのか?
次章から、具体的なヒントをご紹介していきます。
1-1. 発達障害の子にも必ず「強み」はある

「発達障害の子には才能がある」と言われても、ちょっとピンと来ないかもしれません。
でも実際には、多くの子どもたちが「好きなことへの没頭」や「独自の視点」を持っています。
例えば…
- 電車が好きすぎて時刻表を覚えてしまう集中力が高く、記憶力に優れている場合も
- 同じ絵ばかり描くけれど、それがどんどん上達していく
- パズルやブロックに夢中で、空間認識能力が高い傾向がある
こうした「ハマる力」や「とことん突き詰める集中力」は、立派な才能の土台です。
ただ、それが「学校の成績」や「日常生活」では目立たないこともあるので、気づきにくいだけなんですよね。
ママが「できていないこと」ではなく、「なぜか夢中になるもの」「自然と繰り返していること」に注目してあげると、お子さんの強みや才能のヒントが見えてくるかもしれませんよ。
1-2. 得意・不得意がハッキリしやすい特性



発達障害の子どもは、「できること」と「できないこと」の差が大きいという特徴を持っていることが多いです。
たとえば…
- 話すのは苦手だけど、文字を読むのはすごく早い
- 集団行動は難しいけれど、一人でコツコツ作業するのが得意
- 人の話は聞き逃すのに、自分の好きな音には敏感に反応する
これらは一見「偏り」に見えるかもしれませんが、見方を変えると「個性の強さ」でもありますよね。
ママとしては、不得意なところばかり気になってしまう気持ち、よくわかります。
でも、逆に「得意がわかりやすい」というメリットもあるんです。
日常での行動の偏りや、「やたらこだわるもの」「繰り返しやること」などに注目してみてください。
そこにこそ、その子の才能の芽が隠れていることがあるんです。
1-3. 他の子と比べるのではなく「その子らしさ」を



ついつい、「〇〇ちゃんはできてるのに、なんでうちの子は…」と比べてしまいがちですよね。
でも、それって本当に必要でしょうか?
発達障害の子どもにとっては、「みんなと同じ」になることよりも、「その子らしさ」を活かすことの方が、ずっと大事なんです。
周りと比べるよりも、次のような視点で見てみてください。
- 何に時間をかけているか?→集中して取り組んでいることは?
- 何を繰り返しているか?→飽きずにやっていることは?
- どんな場面で笑顔になるか?→心から楽しんでいる瞬間は?
それらの答えが、「その子だけの才能」につながっていくことがあるんですよ。
子どもが夢中になっていることを、そっと見守る。
それだけでも、才能への第一歩を支えてあげていることになります。
「比べる」のではなく、「気づく」。
ママのそのまなざしが、お子さんの未来の可能性を広げていくんです。
2. 才能の芽を見逃さないために大事なこと
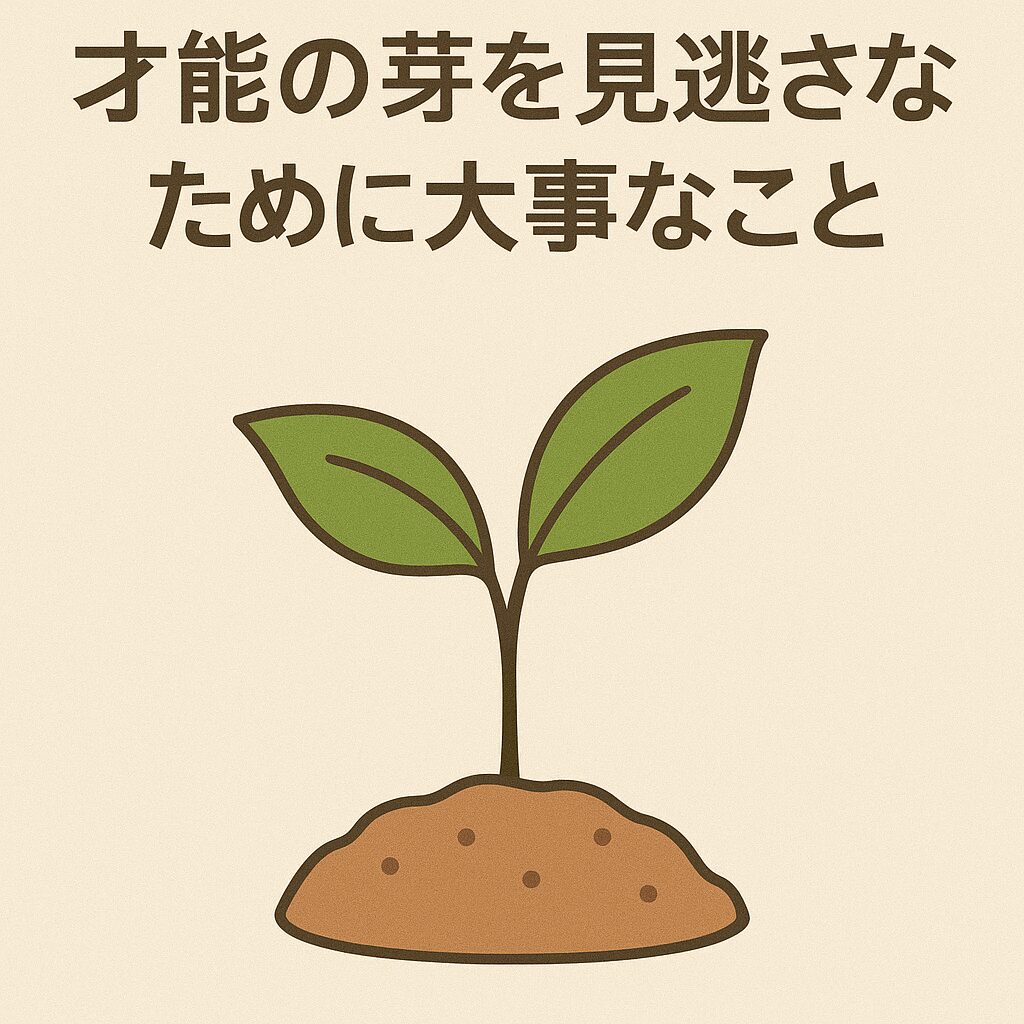
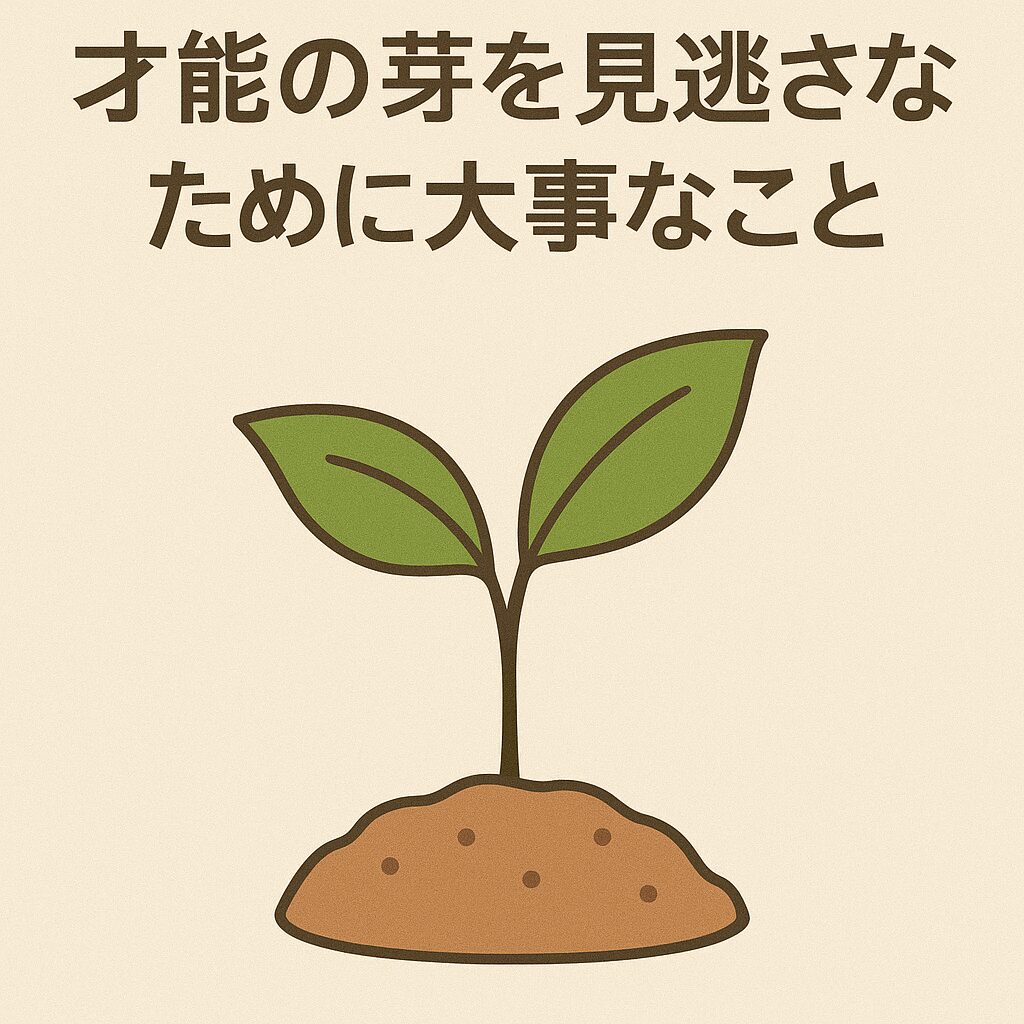
才能は「あるかないか」ではなく、気づけるかどうかが大きな分かれ道になります。
発達障害の子どもたちは、自分の得意や好きなことをうまく言葉で伝えられない場合も多いですよね。
だからこそ、ママのちょっとした観察力や気づきが、才能を開花させるカギになるんです。
日常の中の行動や反応を、少しだけ丁寧に見てみると、その子だけの「光る部分」が見えてくるかもしれませんよ。
2-1. 日常の中にヒントがある



才能って、何か大きな賞を取ったり、人より飛び抜けて上手にできることだけだと思っていませんか?
でも実際には、日々の「好き」「よくやっていること」にこそ、才能の種があるんです。
たとえば、こんな行動がヒントになることもあります。
- 家にあるものを並べるのが好き→秩序立てる力、観察眼が育っているかも
- 同じ音楽を何度も聴く→聴覚の感性が鋭い可能性あり
- ぬいぐるみで延々とごっこ遊びをする→ストーリーを組み立てる力が育っているかも
日常のふとした行動を「なんでこればっかりやるんだろう?」と思う前に、少しだけ角度を変えてみてください。
その「いつもやってること」が、お子さんならではの世界観かもしれません。
2-2. 好きなことに夢中になる時間を観察する



子どもが何かに夢中になっているときって、周りの声が耳に入っていなかったり、気づくと何時間もたっていたりしますよね。
そんなときは、才能が芽を出している瞬間かもしれません。
しかも、多くの場合、本人は「やらされている」のではなく、「自分からやっている」んです。
たとえば…
- レゴやブロックに何時間も没頭→空間把握や創造力が高いかも
- お気に入りの図鑑を繰り返し読む→知識欲や集中力がすごいかも
- 折り紙や塗り絵に集中→手先の器用さや感性が育っているかも
「もうちょっとバランスよく遊んでくれたら…」と思うこともあるかもしれません。
でも、夢中になる姿には、その子の持っている力が自然と表れていることが多いんですよ。
2-3. 親の「こうあってほしい」を手放す勇気



子育てをしていると、つい「こう育ってほしい」「これができるようになってほしい」と思ってしまうものですよね。
でも、その気持ちが、子どもの可能性の芽を見えにくくしてしまうこともあります。
子どもが本当に好きなことって、ママが望んでいたこととは全然違うかもしれません。
たとえば…
- 勉強は苦手だけど、空の観察が大好き→自然への興味がある
- 人と話すのは苦手だけど、動物となら心を開く→共感力が高いかも
- ゲームの構造に詳しくて、プログラミングに関心を持つ→論理的思考の芽がある
「〇〇できる子になってほしい」ではなく、「〇〇が好きな子なんだな」と見てあげると、その子の本来の個性や才能が見えてきます。
ママの意識を少し変えるだけで、子どもが自然と伸びていくきっかけになりますよ。
3. 才能を見つけるためのチェックポイント


「うちの子の才能って、いったいどこにあるんだろう?」
そう思って観察していても、なかなか見つけられないときってありますよね。
でも、焦らなくて大丈夫です。
才能って、パッと目に見えるものばかりではありません。
日常の中で、「あれ?なんでこれが得意なんだろう?」という小さなサインに気づくことで、少しずつ見えてくるものなんです。
この章では、才能を見つけるための「チェックポイント」を3つご紹介します。
ママの観察力で、お子さんの強みのヒントをキャッチしてみてくださいね。
3-1. 興味があるジャンルを探るコツ



子どもが「どんなことに関心を持ちやすいか」を知ることで、才能の方向性が見えてくることがあります。
たとえば、次のようなジャンルごとに反応を観察してみましょう。
| 感覚遊び | 砂遊び、水遊び、粘土、感触あそびなど。触覚や感性が育ちやすい。 |
| 視覚系 | 図鑑、絵本、パズル、絵描きなど。観察力や構造把握力が見える。 |
| 運動系 | 走る、ジャンプ、バランス遊びなど。身体の使い方に特徴がある場合も。 |
子どもが長く集中できるジャンルや、自分から始めるジャンルはありませんか?
それが「心が動く領域」=才能の入り口かもしれません。
3-2. 得意と感じる感覚特性を知る



発達障害の子どもたちは、五感(視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚)に敏感または鈍感な傾向があり、その感覚の「得意」が才能につながることもあるんです。
たとえば…
- 視覚優位の子→絵・図・パターン認識に優れる
- 聴覚優位の子→音楽、音声模写、語学に強みがあることも
- 触覚優位の子→細かな作業、手仕事、立体構築が得意
このように、感覚の「得意ポイント」を知ることで、その子が「どんな形で物事を吸収するのが得意か」も見えてきます。
感覚的に心地よいと感じる活動を、安心して繰り返せる環境を整えることが、才能を育てる一歩になりますよ。
3-3. 「褒められた経験」をたどってみよう



才能は「その子が輝いた瞬間」に現れていることが多いです。
特に、誰かに「すごいね」「上手だね」と褒められたことは、子ども自身の心にも強く残っているんです。
たとえば、こんな経験ありませんか?
- 家族に描いた絵を褒められてうれしそうにしていた
- 先生に「細かい作業が得意だね」と言われて得意げにしていた
- お友だちに教えてあげたとき、誇らしそうだった
その子の「自信が生まれた瞬間」こそが、才能を感じた証拠。
過去の写真や思い出話を振り返って、「あのときうれしそうだったなぁ」と感じたエピソードをたどってみると、新しい気づきがあるかもしれません。
4. 才能を見つけたらどう伸ばす?
「もしかして、これがこの子の得意かも?」
そんな発見があったら、すごくうれしい気持ちになりますよね。
でも、見つけただけでは終わりません。
才能は「育てる環境」があってこそ、花開くものなんです。
特別な教育や訓練が必要というわけではなく、日常の中の小さな工夫で、子どもの力をしっかり伸ばしていけます。
この章では、才能を育てるための3つのステップをご紹介します。
ママのちょっとした声かけやサポートが、大きな成長につながりますよ。
4-1. 小さな成功体験を積み重ねよう



どんな才能も、「自信」と一緒に育てることがとても大切です。
そのために効果的なのが、小さな成功体験の積み重ねなんです。
難しいことじゃなくて大丈夫。
日々のちょっとした「できたね」「やれたね」の経験が、自己肯定感の土台になります。
- 好きな絵を描ききった→「完成したね!すごい集中力だったね」と声かけ
- パズルをひとりで組み立てられた→できた瞬間を一緒に喜ぶ
- 前よりうまくブロックが積めた→「成長したね」と認めてあげる
こうした経験を通して、「自分はできる」「やってみよう」という気持ちが育ちます。
それが才能の根を強くするんですよね。
4-2. 専門的なサポートも取り入れる



「この子の好きなことを、もっと伸ばしてあげたい」
そう感じたら、専門の力を借りるのも大きな選択肢です。
最近では、発達障害の特性を理解した教室やサポートも増えてきています。
たとえば…
- クリエイティブ系が得意→絵画教室・アートスクール
- 集中して取り組むのが好き→プログラミングやパズル型教室
- 身体を動かすのが得意→スイミング・体操・運動療育
プロの指導を受けることで、新しい視点や方法が加わりますし、子ども自身の「やってみたい!」気持ちもさらに広がります。
「家庭では難しいかも」と感じた部分も、外部サポートを上手に活用することでグッと伸びやすくなることも多いんですよ。
4-3. 家庭での接し方も才能育成に直結



家庭は、子どもが一番安心して自分を出せる場所。
だからこそ、日々の関わりが才能の伸びに直結します。
とくに意識してほしいのが、ママの声かけやリアクション。
「ちゃんと見てくれてる」
「認めてもらえた」
そう感じることで、子どもはのびのび力を発揮できるようになります。
- 過程を褒める→「ここまでよく頑張ったね!」という視点
- 子どもが選んだことを尊重する→選択を信じることで自立心も育つ
- 失敗しても「大丈夫だよ」と伝える→挑戦することを応援する空気が大事
日常の何気ないやり取りの中にこそ、子どもの心を育てるヒントがあります。
「わが子の応援団長は私!」そんな気持ちで関われると、才能はぐんぐん伸びていきますよ。
5. 才能を伸ばすためにやってはいけないNG行動
せっかく見つけたお子さんの才能。
「伸ばしてあげたい!」というママの気持ちは、とても素晴らしいことですよね。
でも実はその“伸ばしたい気持ち”が、知らず知らずのうちに逆効果になってしまうこともあるんです。
才能は、「押しつけ」や「無理強い」では伸びません。
この章では、ありがちなNG行動を3つご紹介します。
ちょっとした意識の変化で、子どもがのびのびと力を発揮できるようになりますよ。
5-1. 他の子と比較する



ママ同士の会話やSNSで、ついついよその子と比べたくなること、ありますよね。
でも、「比べること」ほど才能をつぶしてしまう行動はないとも言われているんです。
発達障害の子どもは、成長のペースや得意の表れ方が「自分だけのリズム」で進むもの。
他の子と同じように見えなくても、焦る必要はありません。
こんな言葉がけは避けたいところです。
- 「〇〇くんはもうできるのに、なんであなたは…」
- 「妹の方がしっかりしてるんだから、見習って」
- 「みんなできてるよ?」というプレッシャー
才能は、「比べられる環境」よりも、「認められる環境」でこそ、ぐんぐん伸びていきます。
5-2. 興味があることを無理にやめさせる



子どもが何かに熱中していると、親として「もうそればっかりやめなさい!」と言いたくなること、ありますよね。
でも、その「ずっとやってること」が、実は才能の種だったということも少なくありません。
たとえば…
- 毎日同じ絵を描く→その中で技術が育っている可能性も
- 同じおもちゃで延々と遊ぶ→理解や構造への深い探究心かも
- 同じ動画ばかり見る→繰り返しから新しい気づきを得ていることも
「もういいでしょ」と止める前に、「この子はこれを通して何を感じているんだろう?」と少し立ち止まってみてください。
「好き」は、才能の最初の扉です。
むやみに閉じてしまわないようにしたいですね。
5-3. 苦手を無理に克服させようとする



「苦手を克服させたい」――親心として自然なことですが、それにこだわりすぎると、子どもの自信が失われてしまうこともあります。
発達障害の子どもには、「苦手はあって当たり前」という前提で向き合ってあげるのがとても大切です。
むしろ、苦手な部分を無理に直そうとせず、得意なことを伸ばす方が自然でラクなんですよ。
- 書くのが苦手→話す力で伝える練習を
- 人前で話せない→作品や絵で表現する方法も
- 整理整頓が苦手→片付けしやすい工夫でカバー
才能を伸ばすには、「苦手を減らす」よりも「得意を活かす」ことに目を向ける方がずっと効果的なんです。
6. 才能を育てる環境づくりのヒント
才能は、子どもの中に眠っているもの。
でも、それがぐんぐん育つかどうかは、どんな環境に身を置くかで大きく変わってくるんですよね。
無理に頑張らせるよりも、「自然とのびのび力を発揮できる場所」を用意してあげること。
それが、才能を育てるうえで何より大切なことなんです。
この章では、家庭でできるシンプルな環境づくりの工夫を3つご紹介します。
6-1. おうちを「安心基地」にする



どんな才能も、安心できる土台がなければ育ちません。
そのために必要なのが、子どもにとっての「安心基地」となる場所――つまり、家庭なんです。
安心基地づくりのポイントは、「否定されない」「自由に表現できる」空気感。
- うまくできなくても責められない→失敗を恐れず挑戦できるようになる
- 好きなことを自由にできる時間や空間をつくる→集中して取り組む力が育つ
- 「見守ってもらえている」安心感→心が安定し、自発性が出てくる
子どもにとって「失敗しても大丈夫」と思える場所があるだけで、思いきっていろんなことに挑戦できるようになりますよ。
6-2. スモールステップで挑戦の機会を作る



才能は、ちょっとずつの積み重ねで育っていきます。
だからこそ大切なのが、スモールステップでの挑戦なんです。
急に「もっとがんばって!」と言われても、子どもにとってはプレッシャーになってしまいますよね。
でも、「昨日より1つ多くできた!」「10分間だけ集中できた!」など、小さな成功を重ねることで、大きな自信へとつながっていきます。
- タイマーを使って短時間から挑戦→やり切る達成感を実感できる
- 「今日できたこと」を一緒に振り返る→自分の成長に気づける
- 1つだけチャレンジ課題を用意する→次の目標が明確になる
子どもにとって無理のないペースで、でも「ちょっと頑張る」場面を用意する。
その繰り返しが、自然と才能を育てていきます。
6-3. 家族で「応援する空気」を作る



子どもが何かに取り組むとき、一番の応援団は「家族」。
ママだけでなく、家族みんなで応援する空気を作ることが、子どもの心をぐっと強くしてくれます。
家族からの何気ない「すごいね」「がんばってるね」の一言が、子どもにとっては大きな励ましになるんです。
- お兄ちゃんが弟の作品を褒めてあげる→きょうだいの関係も良くなる
- パパが取り組みに関心を持って話を聞く→自信と安心につながる
- 家族みんなで成果を一緒に喜ぶ→自己肯定感がぐんと上がる
家庭の中に「応援される雰囲気」があるだけで、子どもはもっとチャレンジしてみたくなるものです。
その空気づくりこそが、才能育成のベースになるんですよね。
7. 実際に才能が見つかったママたちの体験談
「本当にうちの子にも才能なんてあるのかな?」
そう感じているママにこそ、知ってほしいのが他のご家庭の実例です。
発達障害のあるお子さんが、ある日ふとしたきっかけで才能を見せたという体験談は、たくさんあるんですよ。
この章では、3つのリアルなストーリーをご紹介します。
どれも「小さなきっかけ」から始まっていますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
7-1. 「ひたすら絵を描いていた子」が漫画家の卵に!



小学校低学年の頃から、同じキャラクターばかりを描いていたAくん。
周囲の子と違って集団遊びは苦手で、ひとりで黙々と絵を描く時間を過ごすことが多かったそうです。
最初は「偏りが強すぎるのでは?」と心配していたママですが、描く枚数の多さ・構図の工夫・色使いに気づいて応援するように。
やがて近所の絵画教室で表現力を褒められ、のちにイラストコンテストで入賞。
現在は、専門学校に通いながら漫画家を目指して活動中なんだとか。
ママはこう語ってくれました。
「他の子のやっていることじゃなくて、“この子が夢中になってるもの”を大事にしてよかったです。」
7-2. 「動きが止まらない子」が体操クラブで才能を発揮



落ち着きがなく、じっとしているのが苦手だったBくん。
学校の授業中に立ち歩いてしまうことも多く、ママは「どうにか落ち着いてほしい」と悩んでいました。
ある日、たまたま見学に行った体操クラブで、Bくんは驚くような柔軟性と身のこなしを見せたのです。
コーチに「運動神経、すごくいいですね!」と声をかけられたことをきっかけに、Bくんは一気に自信を持ち、自分から練習に行きたがるようになったそうです。
今では地区の大会で入賞するほどに成長し、教室の中でも落ち着いて過ごせるようになったとのこと。
「苦手をなくそうとするより、“活かせる場所”を探してあげる方が良かった」とママは話してくれました。
7-3. 「電車に詳しすぎる子」がガイド役で活躍中



Cくんは、幼い頃から電車が大好き。
ダイヤグラムや時刻表を丸暗記するほどの熱中ぶりに、周囲の大人はびっくりしていたそうです。
最初は「鉄道オタクって言われないかな…」と心配していたママ。
でも本人があまりに楽しそうに話すので、図鑑を増やしたり、博物館へ一緒に行くなどのサポートを続けていたそうです。
そのうち地元イベントの電車クイズに出場し、「解説のお兄さん」としてスタッフに声をかけられ、鉄道ガイド役を任されるように!
今では観光PRにも関わるなど、「好き」を活かした活動の幅がどんどん広がっているんです。
ママは「才能って、突き詰めていいんだって分かりました」と笑顔で話してくれました。
8. まとめ:才能は「探す」より「見つける環境づくり」から
発達障害の子どもにも、必ず才能はあります。
でもその才能は、「特別な力」ではなく、日常の中にひっそりと隠れていることが多いんですよね。
大切なのは、「この子の好きってなんだろう?」「何に夢中になるんだろう?」と、ママがやさしい目で見守ること。
そして、「すごいね」「楽しいね」「やってみよう」と、家庭の中で小さな応援団になってあげることです。
才能を探すというより、「気づいて、育てて、応援する」。
そんな関わり方が、子どもを大きく伸ばしていく第一歩になるんです。
無理をせず、比べずに、目の前のわが子を信じてあげてくださいね。



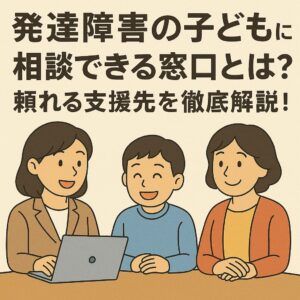


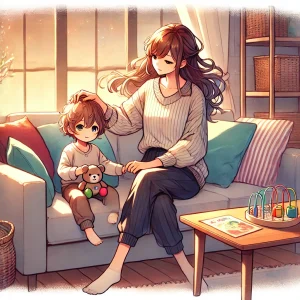

コメント