発達障害のある子どもは、「苦手」が注目されやすいですよね。
でも実は、その裏に「得意なこと」や「伸びる力」がしっかり隠れているんです。
親としては、「この子の得意なことってなんだろう?」「どうやって見つけたらいいの?」と悩むことも多いのではないでしょうか。
この記事では、発達障害のある子どもの「得意分野」に着目し、それを見つけて、伸ばすための親の関わり方を分かりやすく解説します。
- 子どもの「得意分野」の見つけ方
- 得意分野を伸ばすための親のサポート方法
- 日常生活で意識したい工夫と考え方
1. 発達障害の子どもにも「得意分野」があるって知ってた?

発達障害のある子どもは、どうしても「できないこと」「困りごと」が話題になりがちですよね。
でも、実は多くの子どもたちが「得意なこと」「夢中になれること」を持っているんです。
ちょっとした関わり方や視点の変化で、「こんなこともできるんだ!」という発見があるかもしれません。
ここでは、「得意分野って何?」「どんな風に見つかるの?」という基本的なことから一緒に見ていきましょう。
1-1. 発達障害と「得意」の関係とは?
発達障害のある子どもは、認知の特性や感覚の違いから「周囲とは違う視点」を持っていることが多いんです。
その結果、一般的な枠組みでは評価されにくくても、「独自の感性」や「突出した能力」を発揮することがあります。
「得意なこと」は苦手の陰に隠れてしまいやすいけれど、ちゃんと存在しています。
例えば、
- こだわりが強い=ひとつのことに集中できる力になる
- 音や色に敏感=芸術的な才能につながることがある
- 話すのが苦手=観察力が高く、文章や創作で表現できる
このように、「苦手」だと思っていた部分が、実は「得意」を育てるヒントになることもあるんですよね。

1-2. 「好きなこと」が得意を引き出すカギに
子どもにとっての「好き」は、得意を見つけるうえでとても大事なポイントです。
好きなことに取り組んでいるときの子どもは、とてもイキイキしていますよね。
その集中力や持続力、創造力こそが、「得意分野」の種なんです。
たとえば、電車が好きで時刻表を暗記してしまう子や、昆虫に夢中になって専門家のような知識を持っている子。
周りから見ると「オタクっぽい」と思われるかもしれませんが、こうした「好き」が突き抜けていくと、立派なスキルになります。



1-3. 「得意」を育てるには安心できる環境が大切
得意を伸ばすには、子どもが安心して過ごせる環境が欠かせません。
誰かに否定されたり、失敗を責められたりすると、「好きなこと」すら隠してしまうこともあるんです。
子どもが自由に試せて、失敗しても認められる環境こそが、得意を育てる土壌になります。
そのためには、親が子どもの行動をよく観察し、肯定的な声かけをしてあげることが大切です。
「またそれやってるの?」ではなく、「ほんとに好きなんだね」「すごい集中力だね」といった声かけが、子どもの自己肯定感を育てます。



2. 得意分野を見つける3つのヒント


「うちの子の得意なことってなんだろう?」と考えるお母さん、けっこう多いですよね。
でも、難しく考えなくても大丈夫。
日常の中での行動や反応を少し注意深く見てみると、「好き」「得意」のヒントがたくさん隠れているんです。
この章では、親が気づきやすい3つの視点から「得意分野の見つけ方」をご紹介します。
2-1. 子どもが夢中になる瞬間を見逃さない
「時間を忘れて集中しているとき」、それが得意分野のサインかもしれません。
たとえば、同じブロックで何時間も遊んでいたり、絵を描くときだけ静かだったり、そういう瞬間ってありませんか?
それって、無理にやらされてるんじゃなくて、「自分から夢中になってる証拠」ですよね。
その「集中力」は、子どもにとっての得意分野を見つける一番のヒントになります。
意識して見てみると、こんなポイントが見つかります。
- 時間を忘れて遊んでいるとき→没頭していることに注目
- 話が止まらなくなるテーマ→知識が深まりやすい分野
- 何度も繰り返しやる行動→安心感と達成感が得られている可能性



2-2. 褒められるときの行動をチェック
「先生に褒められた」「友達に教えてあげてた」そんなときの行動も、実は得意分野のヒントになるんです。
特に、まわりの大人や子どもが「すごいね!」と言ってくれるようなことには、何かしらの強みが隠れていることが多いです。
他人の反応は、客観的な「得意の証拠」になりやすいんですよね。
たとえばこんなパターンがあります。
- 図工で先生に褒められる→独自の発想や表現力がある
- 友達に説明するのがうまい→伝える力や共感力がある
- 細かい作業を正確にこなす→手先の器用さや集中力が高い



2-3. 苦手を避けたときの選択肢に注目
一見ネガティブに見える「逃げ」の行動の中にも、実は子どもなりの工夫や得意が潜んでいることがあるんですよ。
たとえば、体育が苦手で教室で絵を描いていたら、いつの間にかすごく上達していた……なんてこともありますよね。
「苦手を避けたあとに何を選んだか」そこに子どもの得意が見えることがあるんです。
こんなパターン、心当たりありませんか?
- 外遊びを避けて本ばかり読む→読解力や想像力がある
- 話すのが苦手で絵日記に集中→表現力や観察力に長けている
- グループ行動を嫌がって一人で作業→集中力や独立心の強さがある



3. 得意分野を伸ばすために親ができること


得意分野を見つけたら、それをどう育てていくかが次のステップですよね。
「せっかくの才能、どうやって伸ばせばいいの?」と悩むお母さんも多いと思います。
でも大丈夫。
日常の中でのちょっとした関わり方や声かけで、子どもの得意はグンと伸びていきますよ。
この章では、親としてどんなサポートができるかを、3つの視点からご紹介します。
3-1. 否定せずに「認める」ことから始めよう
まず大切なのは、「子どもの興味やこだわりを否定しないこと」です。
発達障害のある子は、時に大人から見て「偏っている」と思えるような強いこだわりを見せることがありますよね。
でも、そこにこそ得意分野が隠れていることが多いんです。
子どもの興味をまるごと認める姿勢が、伸ばすための第一歩です。
たとえば、同じ絵ばかり描いている子に「またそれ?」ではなく、「すごいね、よく覚えてるね!」と声をかけてみてください。
「お母さんが分かってくれてる」と感じられると、子どもは自信を持って挑戦を続けられるようになります。



3-2. 小さな成功体験を積ませよう
得意分野を伸ばすには、「自分はできるんだ」という成功体験を積み重ねることがとても大切です。
成功体験とは、何か特別な成果じゃなくていいんです。
・いつもより長く集中できた
・作品を完成させた
・誰かに褒められた
こうした小さな経験が、子どもにとっては大きな自信につながります。
子どもが「自分の力でできた!」と感じる機会を、意識してつくってあげましょう。
成功体験をつくるために意識したいポイントは…
- ちょっと頑張れば届く目標を設定→「できた!」を実感しやすい
- 結果よりも過程をほめる→努力や工夫を認めると次につながる
- 他人と比べない→「自分らしく」でいいと伝える



3-3. 一緒に楽しむ姿勢が子どもを後押しする
「すごいね!」「楽しいね!」と一緒に喜ぶことで、子どもは得意なことにもっと前向きになれます。
親が関心を持ってくれると、それだけで子どもは嬉しいものですよね。
得意を育てるうえで、親の“共感”と“応援”は最強のサポーターなんです。
子どもの好きなことに、ぜひお母さんも関わってみてください。
・一緒に図鑑を見る
・子どもの描いた絵にコメントする
・好きなテーマの博物館に行ってみる
これだけで、「好きなこと=家族と楽しい時間」というポジティブなイメージが生まれます。



4. 得意を活かす環境づくりが成長を支える
子どもが「得意!」と感じられる環境があると、それだけで表情が明るくなったり、行動が前向きになったりしますよね。
どんなに素晴らしい才能があっても、それを発揮できる場所がなければ、宝の持ち腐れになってしまいます。
この章では、家庭や学校、地域など、子どもの得意を活かすための「環境づくり」の工夫をお伝えします。
4-1. 家の中を「安心して挑戦できる場所」に
まず大切なのは、家庭が子どもにとって「安心してチャレンジできる場」であることです。
得意を伸ばすには、失敗しても「大丈夫」と思えることがとても重要なんですよね。
安心感があってこそ、子どもは自分らしさを発揮できます。
家でできる環境づくりの例として、こんな工夫があります。
- 子ども専用の作業スペースを用意→集中しやすくなり、達成感が生まれる
- 作品を飾るコーナーをつくる→自信につながる自己表現の場になる
- 「失敗OK」のルールを共有する→挑戦する気持ちを後押しできる



4-2. 学校との連携で「得意」を理解してもらう
家庭だけでなく、学校でも子どもの得意を理解してもらえると、子どもはますます安心して過ごせます。
発達障害のある子は、学校で苦手に直面することが多いので、「得意なことを知っていてくれる先生」がいるだけで、心の支えになるんですよね。
学校と家庭が協力して、子どもの得意を共有することが大きな力になります。
例えば、こんな工夫ができます。
- 家庭での様子を先生に伝える→学校でも得意を活かした指導がしやすくなる
- 先生からのフィードバックをもらう→新たな「得意」の発見にもつながる
- 連絡帳でのやりとりを活用→日常の中で情報共有しやすくなる



4-3. 地域の場や習い事で「得意」を社会につなげる
子どもの得意をもっと広く伸ばしていくためには、地域の活動や習い事もうまく活用していきたいですよね。
家庭や学校だけでは体験できない場面で、子どもが「自分はこれができるんだ」と実感できると、自信がぐっと深まります。
得意を社会の中で活かす経験が、将来の自立にもつながります。
たとえば、こんな場があります。
- 図工・音楽・プログラミングなどの教室→専門的なスキルを楽しく習得
- 図書館イベントや地域ワークショップ→人と関わりながら興味を広げられる
- ボランティア活動や体験学習→社会性や実践力を育むチャンスに



5. 得意と苦手のバランスを取ることが大切
得意分野を伸ばすことに注目しがちですが、それだけに偏りすぎると、日常生活で困りごとが増えてしまうこともあるんですよね。
「得意を伸ばしながら、苦手とも上手につきあう」ことが、発達障害の子どもにとってとても大切な視点になります。
この章では、得意と苦手のバランスを取るための親の工夫や関わり方についてお話します。
5-1. 得意だけに偏らないように注意しよう
「得意なことだけやっていればいい」という考えは、短期的には子どもが楽しく過ごせるかもしれません。
でも、学校生活や社会に出ると、「ある程度の苦手」とも向き合わないといけない場面が出てきますよね。
だからこそ、得意だけに偏らず、バランスよく育てていく意識が大切なんです。
たとえばこんな工夫があります。
- 得意を活かして苦手を補う→好きな絵で予定表を描いてスケジュール管理
- 苦手なことも少しずつ挑戦→無理なく進める工夫で「できた!」を実感
- サポートを組み合わせて無理をしない→特性に合ったツールや支援を活用



5-2. 苦手を責めず「工夫で乗り越える」考え方に
発達障害の子にとって、苦手なことは「がんばればできる」ものばかりではありません。
でも、「できない=ダメ」と思い込ませてしまうと、自己肯定感が下がってしまうんです。
苦手は責めるのではなく、「工夫で乗り越えようね」と伝えることが大切なんです。
たとえば…
- 音読が苦手→耳で聞く教材を使う→学び方を変えてストレスを減らす
- 片付けが苦手→片づけマップを作る→視覚的なサポートで行動しやすく
- 集団行動が苦手→事前に流れを説明→予測ができれば不安も軽減



5-3. 得意が自信につながると苦手にも向き合える
得意分野で「自分はできる!」という感覚を持っている子どもは、苦手なことにも前向きに挑戦しやすくなります。
逆に、自信がないと、少しの苦手で「もうムリ…」と諦めてしまいやすいんですよね。
得意をベースにした自己肯定感が、苦手を乗り越えるエネルギーになります。
こんな流れを意識してみてください。
- 得意なことで「できた!」を実感→成功体験で自信アップ
- 苦手なことも少しずつ挑戦→「できるかも」と感じやすくなる
- サポートと工夫で乗り越える→挑戦が「楽しい」に変わる



6. 年齢ごとに変わる「得意分野」の捉え方
子どもの成長とともに、「得意だな」と思えることも少しずつ変わっていきますよね。
ある時期に夢中だったことが、気づけば他のことに変わっていたりするのは、自然な成長の流れです。
この章では、年齢ごとにどのように得意分野が見えてくるか、そして親としてどんな関わりができるのかをお伝えします。
6-1. 幼児期は「遊び」から得意の芽が見えてくる
まだ言葉で「これが得意!」とは言えない幼児期こそ、行動や遊び方から得意のヒントを探していきたいですよね。
この時期の子どもは、好きな遊びにぐーっと集中することが多いです。
その集中している姿が、まさに「得意の芽」なんです。
例えばこんな様子、思い当たりませんか?
- 同じおもちゃで長時間遊ぶ→集中力や創造性が育っている
- 細かい作業を繰り返す→手先の器用さや観察力がある
- ごっこ遊びがリアル→想像力や社会性が芽生えている



6-2. 小学生期は「得意を表現する力」が育つ
小学生になると、言葉や行動で「これが得意!」と表現できるようになってきますよね。
学校生活の中で、自分の得意を自覚し始めたり、周囲に認められて自信につながったりする時期です。
自分の得意を「見せる」「伝える」経験が大きな力になります。
この時期に意識したいことは…
- 図工や音楽などの表現活動に参加→得意を形にして見せる機会になる
- 自由研究や課外活動に挑戦→興味が広がるチャンスになる
- 作品を褒めて飾る→自信を育てる何よりの方法



6-3. 中高生は「得意」を自分で活かす時期へ
中学生・高校生になると、「自分はこれが得意なんだ」と本人が気づき始めるようになります。
この時期は、親がサポートしすぎず、でも見守る姿勢が大切ですよね。
子どもが自分の得意を活かして「自分らしさ」を考え始める時期です。
関わり方のポイントは以下の通りです。
- 将来につながる情報を一緒に探す→得意が進路や仕事選びのヒントに
- 否定せず話を聞く→自己肯定感を守る関わりが大切
- 専門的な学びの場にトライ→得意を深掘りする絶好のチャンス



7. 「得意分野」が将来の可能性を広げる
発達障害のある子どもたちが自分の得意を知り、それを活かせるようになると、それは「武器」にも「自信」にもなりますよね。
そして、その得意が将来の進路や仕事、社会との関わりにもつながっていく可能性があるんです。
この章では、子どもの「得意」がどのように未来に広がっていくか、そして今できることは何かを一緒に考えてみましょう。
7-1. 得意をきっかけに夢や目標が生まれる
「これが好き」「これが得意」と子どもが実感できることは、そのまま夢や目標の種になります。
発達障害のある子どもたちは、特定の分野でぐんと力を発揮することがあるので、その力を活かせる未来があると知ってほしいですよね。
「得意=自分らしさ」として育てることで、夢や希望につながります。
たとえば…
- プログラミングが得意→ITエンジニアに→得意が仕事になる時代
- イラストが好き→デザインや創作の道へ→個性を活かす働き方も増えている
- こだわりや記憶力→研究職や資料整理など→強みを必要とする場がある



7-2. 得意を活かせる進路や支援を知っておこう
将来に向けては、子どもが「自分の得意を活かせる進路」を選べるように情報を集めておくことも大切です。
特に発達障害のある子どもには、支援付きの進学・就労ルートや、個別に配慮された環境が用意されている場合もあります。
得意を活かすためには、子どもに合った進路・支援を親が知っておくことがカギなんです。
たとえばこんな選択肢があります。
- 通信制・専門学校→興味のある分野に特化した学びができる
- 就労移行支援や職業訓練→実践を通して得意を仕事に活かす準備ができる
- 大学の合理的配慮制度→発達障害に配慮した学習環境が整っている



7-3. 「得意」を信じて育てていく親の姿勢が未来を変える
どんなに小さな得意でも、それを認めて信じてくれる人がいれば、子どもはどんどん成長していきます。
だからこそ、親が「この子の得意はここだね」と気づき、それを信じて支えてあげることが一番の力になるんですよね。
子どもの未来をつくるのは、親の“まなざし”と“信じる力”です。
どんなことができるかというと…
- 子どもの強みを「見える化」する→メモや作品ファイルを残しておく
- 本人に「得意だね」と声をかける→自信と意欲につながる
- 日常で得意を使う場面をつくる→習慣的に得意を活かせる環境に



8. まとめ|子どもの「得意」は未来を照らす光になる
発達障害のある子どもにとって、「苦手」や「困りごと」が目立ちやすいのは確かです。
でもその一方で、他の誰にも真似できないような「得意」や「才能」が、ちゃんと心の中に眠っているんですよね。
その得意を親が見つけ、信じて、育てていくことで、子どもの自己肯定感が高まり、未来への希望が育ちます。
子ども自身が「これが得意」と思えるようになることこそ、人生を切り拓く力になるんじゃないでしょうか。
お母さんのあたたかいまなざしと支えがあれば、きっとお子さんの「得意」は大きく花開いていきますよ。
- 発達障害の子どもにも必ず「得意分野」がある
- 得意を見つけて伸ばすには、親の視点と関わりがカギ
- 得意を育てることが、将来の自立と可能性につながる



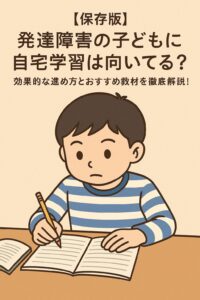



コメント