発達障害のあるお子さんにとって、学校や集団生活の中での学びがうまくいかないことってありますよね。
「勉強についていけない」「集中できない」「学校がつらそう」など、悩むお母さんも多いのではないでしょうか?
そんなときに注目されているのが「自宅学習」という選択肢です。
とはいえ、「どう始めたらいいの?」「教材はどれがいいの?」「親がどこまで関わるべき?」と、疑問や不安もつきものですよね。
この記事では、発達障害の特性に合った自宅学習の進め方や、実際におすすめの教材・サービスまで、分かりやすくご紹介します。
お子さんのペースを大切にしながら、学びの自信を育てていくヒントがきっと見つかりますよ。
- 発達障害に合う自宅学習の特徴がわかる
- 親ができる具体的なサポート方法が見える
- おすすめの教材や学習サービスがわかる
1. 発達障害の子どもにとっての「自宅学習」とは?
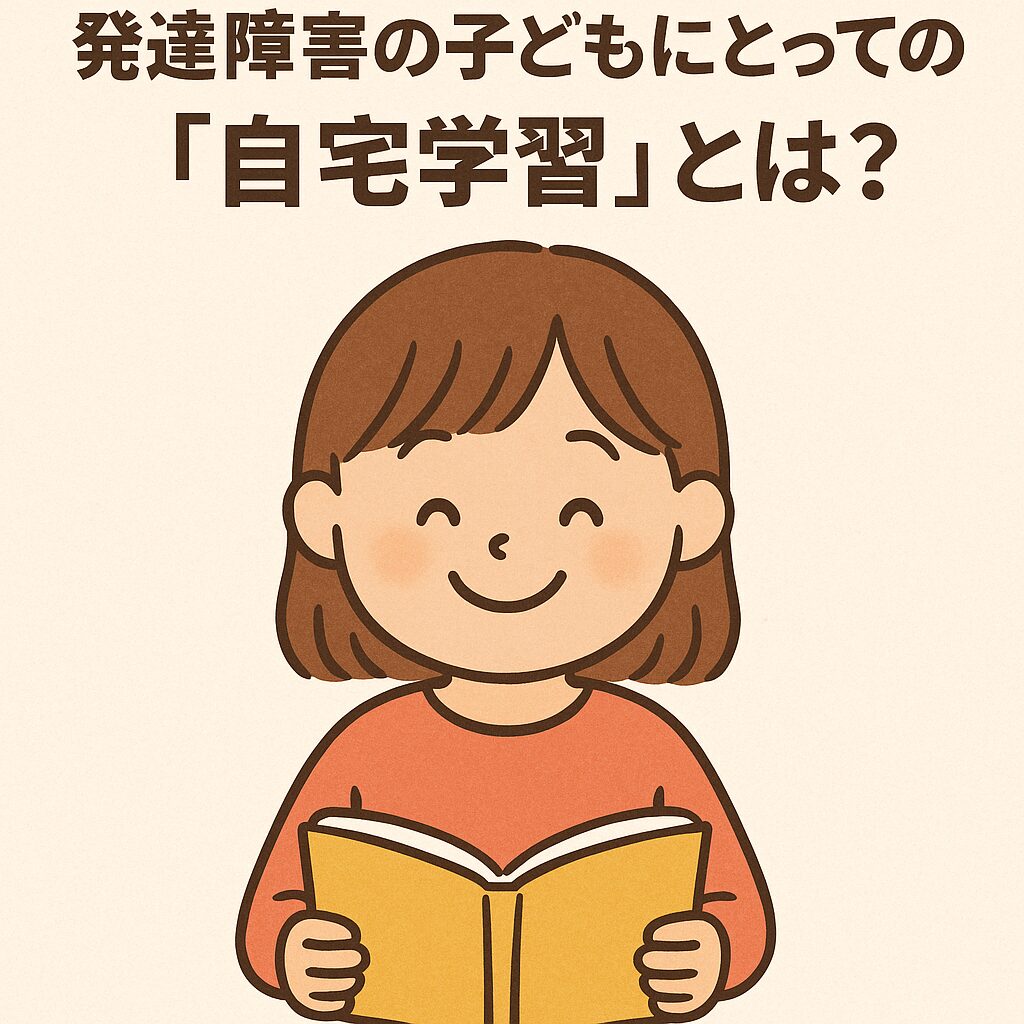
発達障害をもつお子さんにとって、自宅で学習するというスタイルは、実はとても相性がいい場合があります。
学校という環境ではストレスがかかってしまう子でも、自分のペースで取り組めるのが「自宅学習」の大きな魅力なんです。
ただし、自己管理が難しかったり、集中が続かなかったりという課題もあるので、家庭でのサポート体制がポイントになります。
「子どもの特性に合った環境づくり」が、自宅学習成功のカギになるんですよ。
1-1. 自宅学習のメリットとは?
自宅学習って、学校に行かない代わりに仕方なく…と思われがちですが、実はいいところもたくさんあるんです。
落ち着ける環境で学べることが、集中力や意欲につながるのは大きなポイントです。
- 自分のペースで進められる学校の時間割に縛られず、調子に合わせた学習が可能
- 安心できる空間慣れ親しんだ場所で、過敏さや不安を感じにくい
- 一人ひとりに合った教材選び特性に合わせた学習法を選びやすい

1-2. 自宅学習のデメリットや注意点
どんなに良さそうな方法でも、向き不向きはありますよね。
自宅学習にも注意点があるので、そこを知っておくことが大切です。
とくに「習慣づけ」と「親の関わり方」は気をつけたいポイントですよ。
- 自己管理の難しさ時間割や課題の進行など、自主的に取り組むのが難しい子も多い
- 社会性の発達の機会が減る外との関わりが少なくなりがちなので、意識的に経験を作る工夫が必要
- 親の負担が増えやすい学習支援だけでなく、感情面のケアも必要になる



1-3. 自宅学習が向いている子の特徴とは?
「うちの子、自宅学習って合ってるのかな?」と悩む方もいますよね。
実は、発達障害のあるお子さんのなかでも、自宅学習が特に向いているタイプにはいくつかの共通点があるんです。
お子さんの特性をよく観察することで、自宅学習が力になるかどうかが見えてきますよ。
- 集団のなかでストレスを感じやすい子学校で緊張してしまうタイプは、自宅の安心感が学習意欲につながる
- 自分の興味に集中する力がある子興味のあることなら驚くほど集中できる傾向がある
- 視覚優位や聴覚優位など、得意な感覚がはっきりしている子自宅なら、それに合った学び方を取り入れやすい



2. 自宅学習を始める前に準備しておきたいこと


「さあ、今日から自宅学習をはじめよう!」と思っても、準備が整っていないと、すぐに行き詰まってしまうこともありますよね。
特に発達障害のあるお子さんにとっては、「見通し」や「安心感」がとても大事です。
ですから、自宅学習を始める前には学習環境や関わり方の準備を整えることが何よりも大切なんです。
お子さんと親の両方にとって、ストレスなく始められる状態を作っておきましょう。
2-1. 学習する「環境」を整える
発達障害のあるお子さんは、周囲の音や光、物の多さに敏感なことがよくありますよね。
自宅学習では、集中できる環境づくりが成功の第一歩なんです。
テレビやスマホの音、机の周りの散らかりなど、気が散る要素はできるだけ少なくしてあげましょう。
お子さんが「落ち着くな」と思える場所に学習スペースを作ってあげると、それだけで勉強のスイッチが入りやすくなります。
- 専用の学習コーナーを用意するリビングの一角でもOK。いつも同じ場所だと安心感が生まれる
- 刺激を減らす工夫をするイヤーマフやカーテン、間仕切りなどで音や視線をコントロール
- 必要なものだけを置く物が多いと気が散りやすいので、机の上は最小限に



2-2. スケジュールとルールを一緒に考える
自宅学習って自由だからこそ、だらけてしまうこともありますよね。
でも、だからといって「◯時から勉強しなさい!」とガミガミ言っても逆効果だったり…。
大事なのは、お子さん自身に「決める」経験をしてもらうことなんです。
一緒にスケジュールを考えて、できたらしっかり褒めてあげる。それだけでも子どもの意識って変わってくるんですよ。
- 学習時間を短く・決まった時間に10分〜15分など、無理なくできる長さから始める
- タイマーやスケジュール表を活用時間の「見える化」で見通しがつきやすくなる
- できたらごほうびを用意するシールやスタンプ、ゲーム時間などの簡単なごほうびでモチベーションUP



2-3. 親の関わり方をあらかじめ考えておく
親がどこまで関わるかって、結構悩みますよね。
ずっと横についているのは大変だし、でも放っておくと進まない…。
そのバランスを取るには、最初に親子で「ルール」を話し合っておくことがとても大事なんです。
「わからないときだけ呼んでね」とか、「〇分だけ一緒にやるよ」と決めておくだけでも安心感につながりますよ。
- 付きっきりでなく「見守る」スタンスに子どもに主導権を持たせることで自信にもつながる
- 困ったときに声をかけられる関係をつくるすぐに答えを出すのではなく、「どうしようか一緒に考えようか」と寄り添う
- 親も無理しすぎないイライラしてしまう前に、お互いに休憩時間を取る工夫を



3. 自宅学習におすすめの教材やサービス
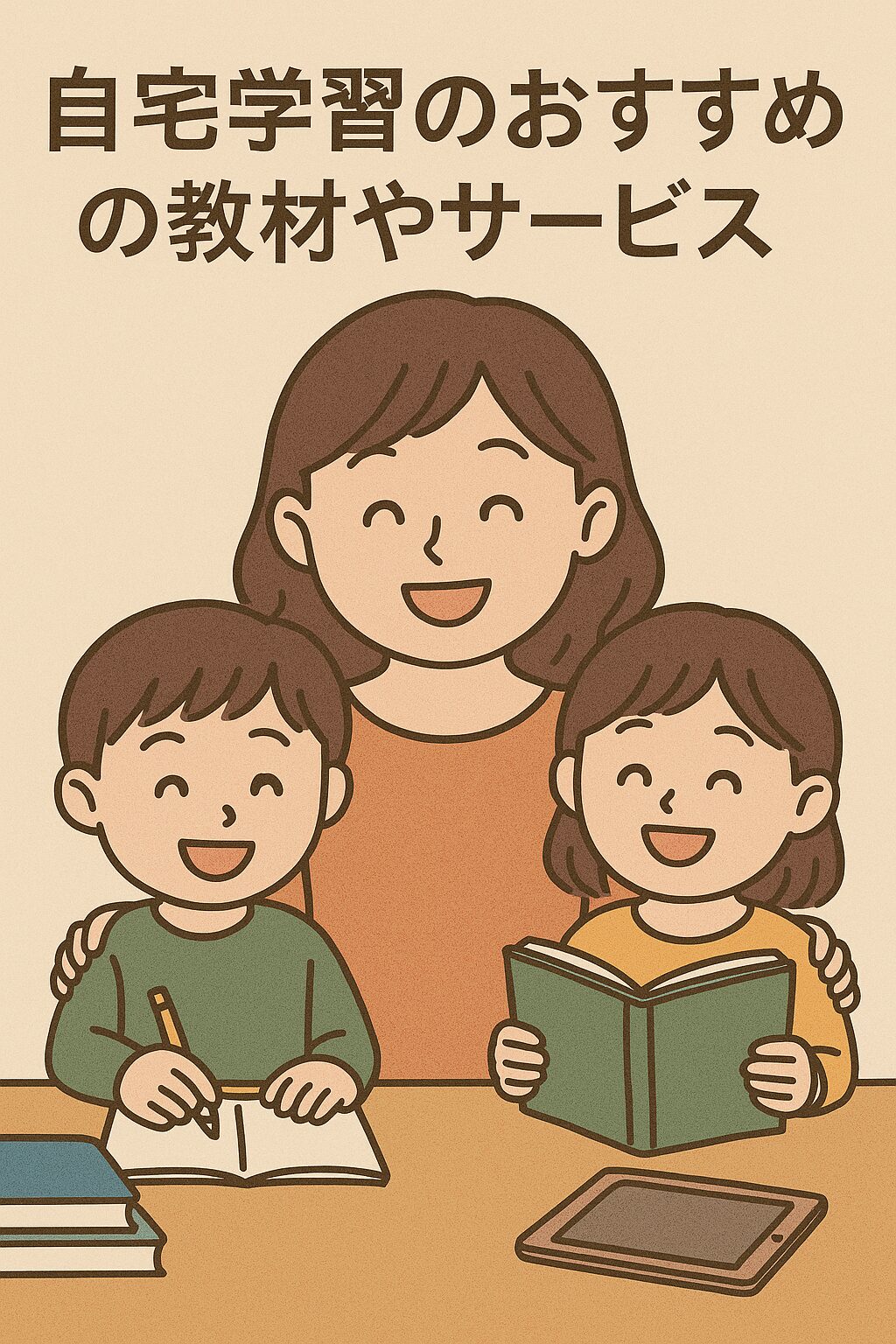
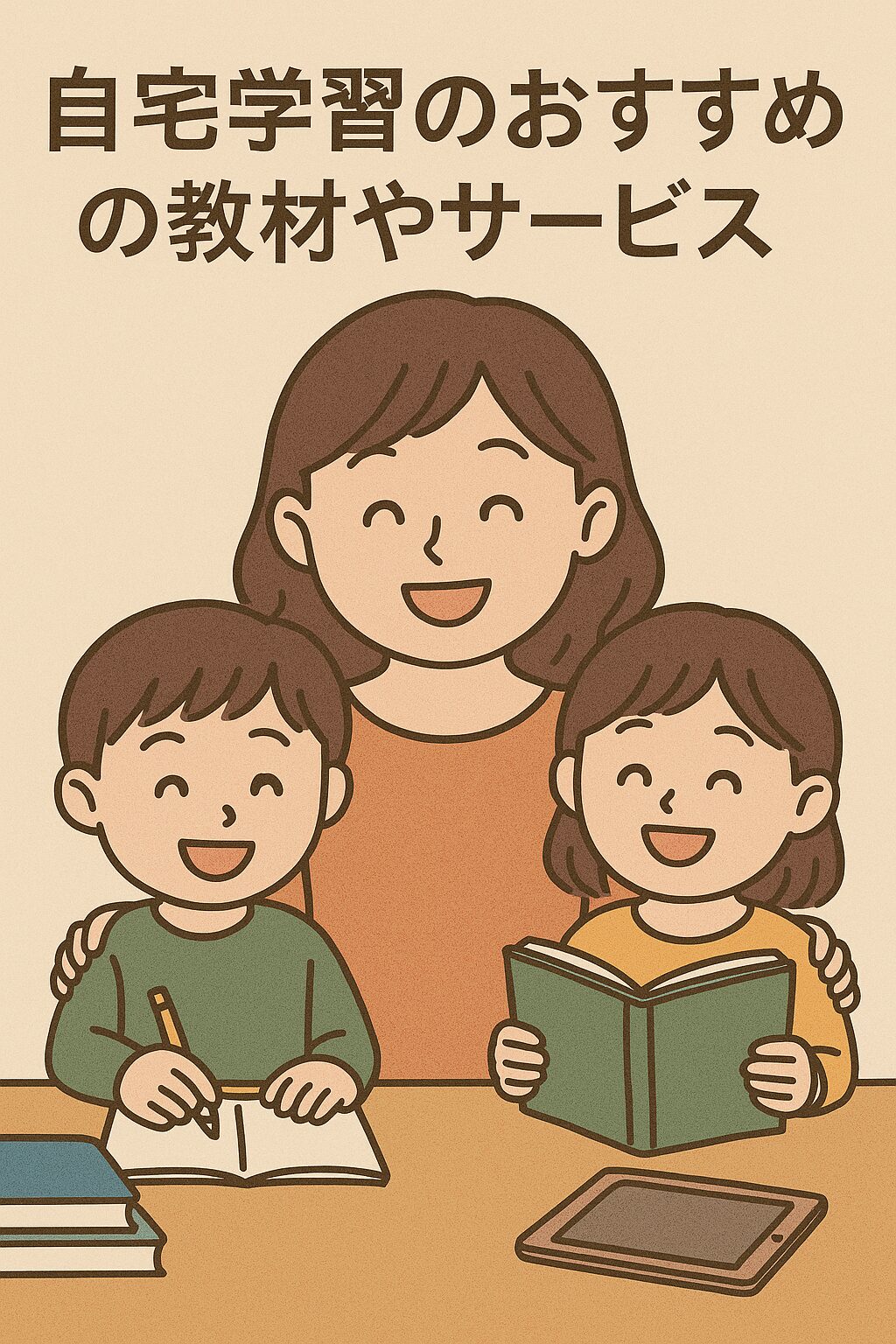
いざ自宅学習を始めようとしても、「どんな教材を選べばいいの?」「発達障害の子にはどんなものが合うの?」と迷ってしまいますよね。
市販のドリルやネットの動画など、選択肢はたくさんありますが、発達特性に合った教材選びがとても大切なんです。
今回は、実際に多くの親子に支持されている教材やオンラインサービスを中心に、自宅で使いやすい学習ツールをご紹介します。
3-1. 発達障害にやさしい市販教材
市販の教材でも、発達障害のあるお子さんに配慮されたものが増えてきましたよね。
特に「視覚的にわかりやすい」「テンポよく進められる」「成功体験を積みやすい」ものが人気です。
最近は「特別支援教材」として、一般書店でも購入できるものも多いので、ぜひチェックしてみてください。
- 学研『はっぴぃタイム』シリーズ短時間でできて、イラスト多め。就学前〜小学校低学年におすすめ
- くもんのドリル繰り返しと達成感重視。「できた!」を感じやすく自信アップに
- 発達支援の専門家監修教材発達障害児支援に特化したシリーズなども増加中



3-2. タブレット学習アプリ・オンライン教材
紙の教材が合わない子もいますよね。
そんなときにおすすめなのが、タブレットやPCを使ったデジタル教材。
動画・音声・アニメーションで学べるので、飽きやすい子や集中が続きにくい子にもピッタリなんです。
自宅でゲーム感覚で取り組めるのも魅力です。
- すらら発達障害対応機能あり。「つまずき分析」や個別指導チャット付き
- チャレンジタッチ(進研ゼミ)学年別に最適化された内容で、ゲーム要素も充実
- STUDY PARK(スタディパーク)特別支援教育の視点から設計されたオンライン学習



3-3. 家庭学習支援付きの通信サービス
「自宅学習をしたいけど、親が教えるのは難しい…」そんな声もよく聞きますよね。
そこで頼れるのが、発達障害に対応した家庭学習支援サービスです。
教材の提供だけでなく、親向けのサポートや、オンラインでの伴走支援があるのが特徴です。
ちょっとした質問や不安を相談できるだけでも、親の負担がグッと軽くなりますよ。
- LITALICOワンダーIT教材を使った個別サポート。発達特性に応じたカリキュラム
- 家庭学習サポート「manabo」オンラインで先生とつながれる。保護者向けガイダンスも充実
- 発達支援センターなどの自治体サービス無料や低価格で利用できることも。地域によって内容が異なる



4. 自宅学習でつまずきやすいポイントと対策
自宅学習を始めてみると、「思ったよりうまくいかないな…」と感じること、ありますよね。
発達障害のあるお子さんにとって、自宅学習は確かにメリットが多いですが、つまずきやすいポイントもあるんです。
でも安心してください。ちょっとした工夫や対応で、その壁を乗り越えることは十分に可能ですよ。
この章では、よくあるつまずきポイントと、その解決のヒントをご紹介していきます。
4-1. 集中が続かない
「最初はやる気があっても、すぐに飽きちゃう…」なんてこと、よくありますよね。
発達障害のあるお子さんは、注意の切り替えが難しいタイプの子も多いです。
でも、集中が続かないからといって「やる気がない」とは限りません。
集中力の波に合わせて、学習時間を設計することが大切なんです。
- 1回10分以内からスタート短時間で達成感を感じられる方が長く続きやすい
- 途中で動いてもOKな雰囲気をつくる軽く身体を動かすことで集中がリセットされる
- 集中しやすい時間帯を見つける朝の静かな時間など、子どもの調子が良いタイミングを見つける



4-2. モチベーションが続かない
最初はやる気満々だったのに、数日後には「やらない!」ってなってしまうこと…ありますよね。
この背景には、成功体験の不足や、目標が見えにくいことが関係している場合が多いんです。
ですから、小さな達成感を積み重ねて「やればできる」と実感してもらうことがとても大切なんですよ。
- すぐに終わる課題を用意する1ページ終える、1つ書けるなど「できた!」を味わえる工夫を
- シール帳やスタンプカードを使う「見える」成果があると、やる気につながりやすい
- 終わった後の楽しみをセットにするお気に入りのおやつ、好きな動画など小さなごほうびで笑顔に



4-3. 教えることに自信が持てない
「私が教えるなんて無理かも…」「学校の先生みたいにできないし…」って、不安になりますよね。
でも大丈夫。親は先生じゃなくていいんです。
大事なのは、“できたね”を一緒に喜んでくれる存在になることなんですよ。
教えることがプレッシャーになるなら、外部の力をうまく借りましょう。
- 完璧な指導を目指さない間違ってもOK。一緒に調べるスタイルで十分
- 「見守り」に徹する日があってもいい子どもが自分でやる力を引き出すチャンスに
- 外部教材や先生を活用する家庭学習支援サービスをうまく取り入れて、無理せず継続



5. 自宅学習を継続するコツ
自宅学習って、始めるのは簡単でも「続ける」ことが一番難しかったりしますよね。
最初はうまくいっていても、気づいたら「最近やってないな…」なんてこともよくある話です。
でも大丈夫。継続のコツをいくつか押さえておくだけで、自然と習慣になっていくんです。
無理なく、親子で「楽しく続けられる学び」を目指していきましょう。
5-1. 小さな目標を立てて達成感を積み重ねる
大きな目標って立派だけど、毎日続けるにはちょっと遠すぎることもありますよね。
だからこそ、「今日の目標」や「今週の目標」など小さなゴールを設定することが大切なんです。
成功体験を積み重ねることで、「またやってみよう」という気持ちが自然に生まれてくるんですよ。
- 1日1ページ、1問だけでもOKできた!という感覚を味わえることが継続のカギ
- 週単位・月単位の「ちいさなごほうび」を設定目標達成後に楽しみがあると続けやすい
- 目に見える達成記録をつけるカレンダーやチェック表に丸をつけるだけでも効果大



5-2. 「できた!」を一緒に喜ぶ時間を作る
「やったね!」って一言、思っている以上に子どもに響くんですよね。
勉強そのものよりも、「認めてもらえた体験」が継続のエネルギーになることって、すごく多いんです。
特に発達障害のある子は、「できなかったこと」に目がいきがちなので、できたことをしっかり言葉にして伝えてあげることが大切です。
- 終わった後は、笑顔で「よくがんばったね!」内容の正解不正解よりも、取り組んだ姿勢を褒める
- 成果を見える形で残すファイルにプリントをまとめる、写真に撮って記録するなど
- 家族で共有して一緒に喜ぶパパや兄弟にも「すごいね」と言ってもらえると自信倍増



5-3. 学習だけにこだわらない「柔軟さ」を持つ
毎日きちんと学習を…と思っていても、どうしても気が乗らない日ってありますよね。
そんな日は、「やらせなきゃ」と無理にさせるよりも、学びの形を柔軟に捉えることが大切です。
本を読む、工作をする、料理を手伝う。これらもすべて立派な学びなんですよ。
- 気分転換を学習に変える図鑑を眺めたり、好きなものを調べるのも知的活動の一環
- 生活の中の学びに注目する買い物で計算、料理で計量など、遊び感覚の中にも学びはある
- お休みの日をつくる「やらない日」があることで、気持ちがリフレッシュされる



6. 自宅学習に取り入れたい「遊び」と「体験学習」
「勉強=机に向かってやるもの」と思っていませんか?
でも、発達障害のあるお子さんにとっては、体を動かしたり、手を使って何かを作ったりする中での「体験型の学び」がとても効果的なんです。
遊びの中にも学びはたくさんあるので、無理に座らせなくても自然と知識やスキルが身につくんですよ。
この章では、楽しみながら学べる「遊び」や「体験学習」のアイデアをご紹介します。
6-1. 遊びながら学べる知育アイデア
「おもちゃで遊ぶ時間=勉強じゃない」と思いがちですが、それはもったいないんです。
特に発達障害のあるお子さんにとっては、感覚的に学べる遊びの中に、たくさんの発達支援要素が詰まっているんですよ。
遊びを通して「できた!」を増やすことが、自信とやる気につながっていきます。
- ブロック遊び空間認識力や指先の訓練に。発想力も育つ万能教材
- ボードゲームルールを守る力、順番を待つ力、思考力を自然に学べる
- 塗り絵やパズル集中力や色の認識、達成感を味わえるアート系教材



6-2. 身近な「体験」を学びに変える工夫
自宅学習って、必ずしも机に向かってやることだけじゃないんです。
実は、日常生活のなかにこそ、子どもが夢中になれる学びがあるんですよ。
お料理、買い物、お掃除…一緒にやってみると、思いがけない発見や興味が生まれることもあります。
- 料理を一緒にする計量カップで算数、野菜の切り方で理科的感覚が身につく
- お買い物ごっこ計算練習だけでなく、社会性や言葉のやりとりも学べる
- 図鑑や地図で調べる遊び「なんで?」「どこ?」の興味を深める学びにつながる



6-3. 興味のあることをとことん伸ばす
発達障害のある子って、「興味のあること」にはものすごく集中する力を持っていることが多いですよね。
それを「遊びすぎ」と思うか、「学びの入り口」と捉えるかで、大きく変わるんです。
好きなことは才能の種。親がそれを応援するだけで、学びはどんどん広がっていきます。
- 電車好きなら路線図や距離の計算へ興味から社会・算数へ発展できる
- 昆虫好きなら観察日記や図鑑学習自由研究につながることも
- ゲーム好きならプログラミング体験将来の可能性も広がる入り口に



7. 親が疲れないための工夫とサポート活用
「自宅学習、頑張ってるのは子どもだけじゃない」――ほんと、そうなんですよね。
毎日のことだからこそ、お母さん・お父さんが疲れてしまわない工夫もとても大切なんです。
無理をし続けると、親子ともにストレスがたまり、せっかくの学びが苦しいものになってしまいます。
この章では、自宅学習を無理なく続けるための「親のための工夫」と「頼れる外部サポート」についてご紹介します。
7-1. 完璧を求めすぎないことが大切
「ちゃんと毎日勉強させなきゃ」「私がしっかり見なきゃ」って、気を張っていませんか?
でも、それってすごくしんどいんですよね。
がんばりすぎない勇気も、長く続けるにはとっても大事なことなんです。
できる日と、できない日があってOK。親がリラックスしていると、子どもも不思議と落ち着くものですよ。
- 「できた日」を大事にする毎日じゃなくてもOK。続けられた日を一緒に喜ぶ
- サボる日も必要疲れた日は「今日は休もうね」と声かけを。休みも学びのうち
- 子どもに合わせたペースで親の理想ではなく、子どもの心に寄り添うことが優先



7-2. 家事や仕事との両立を考える
自宅学習のサポートって、時間も体力も使いますよね。
特に共働き家庭や、きょうだいがいる場合は、毎日同じように関われるとは限りません。
そこで大事なのが、“がんばらない工夫”と“手放す勇気”なんです。
「全部やらなきゃ」と思わずに、家事も勉強も「できることをやる」でいいんですよ。
- 学習タイムを固定しすぎない「この時間にやらなきゃ」と思わず、できる時間帯でOK
- お助け家電・冷凍食品も味方に家事を手抜きすることで気持ちの余裕が生まれる
- きょうだいも一緒に巻き込む「お姉ちゃん先生」などの設定で楽しく協力してもらう



7-3. 外部の支援や相談先を活用する
「一人でなんとかしなきゃ」って思っていませんか?
でも、自宅学習の悩みは、決してあなただけのものじゃありません。
実は、頼れるサポート先やサービスがたくさんあるんです。
困ったときは、遠慮せずに外の力を借りることが、親も子も安心して続けられるポイントになりますよ。
- 放課後等デイサービス学習支援・生活スキルの指導をしてくれる福祉サービス
- 自治体の相談窓口発達障害支援センターや教育相談などで無料相談が可能
- オンライン家庭教師・家庭学習支援発達特性に合わせた指導をしてくれる民間サービスも活用



8.まとめ:自宅学習は「その子らしさ」を大切にする学びのスタイル
発達障害のあるお子さんにとって、自宅学習は「我慢してやるもの」ではなく、自分のペースで学べるチャンスなんですよね。
学校でつまずくことがあっても、家ならリラックスして力を発揮できる子もたくさんいます。
親がすべてを抱え込む必要はありません。教材やサービス、支援の手を上手に活用して、親子にとって“心地いい学び”を見つけていきましょう。
そして、何よりも大切なのは「できたね!」を一緒に喜ぶこと。
それだけで、子どもの学びは前向きに変わっていきます。
- 発達障害の子には、自宅学習が合うケースが多い
- 無理のない環境づくりと親の見守りがカギ
- 学びは「遊び」や「体験」でも広げられる
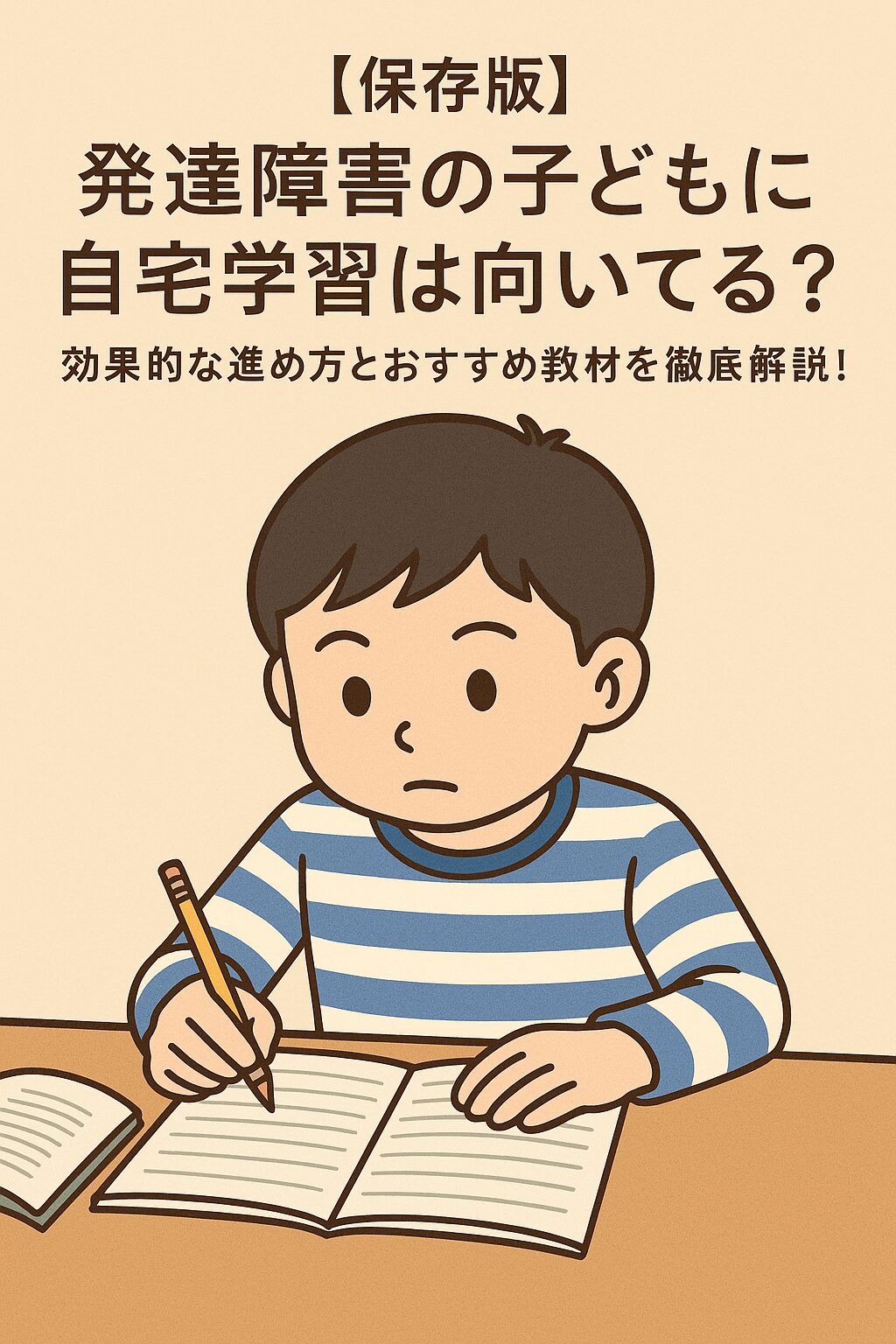






コメント