発達障害を持つお子さんの将来が心配になること、ありますよね。
「どんな仕事が向いているんだろう」「社会に出てちゃんと働けるのかな?」と不安になる気持ち、とてもよく分かります。
実は、発達障害の特性を活かせる職業はたくさんあるんです。
お子さんの強みを理解し、それに合った職業を見つけることで、楽しく働くことができますよ。
今回は、発達障害の特性を活かせる仕事や、親としてできるサポートについて詳しくお伝えします。
- 発達障害の特性を理解し、それに合った仕事を選ぶことが大切
- 親ができるサポートでお子さんの働きやすさが変わる
- 発達障害に特化した支援制度を活用すると安心
1. 発達障害とは?お子さんの特性を理解しよう

お子さんが社会に出る前に、発達障害の特性をしっかり理解しておくことが大切ですよね。
発達障害は、大きく3つのタイプに分けられます。お子さんがどのタイプに当てはまるのかを知ることで、職業選びのヒントになりますよ。

1-1. ASD(自閉スペクトラム症)のお子さんの特性
ASD(自閉スペクトラム症)のお子さんは、ルールを守ることが得意で、集中力が高い特徴があります。
一方で、コミュニケーションが苦手だったり、急な変化に適応しづらかったりすることもありますよね。
- 得意なこと 規則性のある仕事や、細かい作業が得意
- 苦手なこと 臨機応変な対応や、対人コミュニケーションが難しい
- 向いている職業 研究職、プログラマー、データ入力、アート関連の仕事
1-2. ADHD(注意欠如・多動症)のお子さんの特性



ADHDのお子さんは、好奇心が旺盛で、行動力に優れているのが特徴です。
ただし、注意が散漫になりやすかったり、計画性を持つのが苦手だったりすることもありますよね。
| 得意なこと | 変化のある環境での仕事、アイデアを出すことが得意 |
| 苦手なこと | 細かい事務作業や、長時間の集中が必要な業務 |
| 向いている職業 | 営業職、イベント企画、接客業、スポーツインストラクター |
1-3. LD(学習障害)のお子さんの特性
LD(学習障害)のお子さんは、視覚的な情報処理が得意なことが多いです。
一方で、読み書きや計算に困難を感じることもありますよね。
- 得意なこと クリエイティブな仕事や、体を使う仕事
- 苦手なこと 読み書きが必要な事務仕事や、計算を多く使う職業
- 向いている職業 料理人、美容師、職人、映像クリエイター
2. お子さんの強みを活かせる職業を見つけるコツ


お子さんの特性に合った仕事を見つけるには、まず得意なことや好きなことを知ることが大切ですよね。
無理に「一般的に良い仕事」を選ぶのではなく、お子さんが楽しく働ける仕事を見つけてあげましょう。



2-1. お子さんの得意・不得意を理解する
お子さんの得意なことを伸ばすことが、職業選びの第一歩です。
発達障害のお子さんは、「できること」と「苦手なこと」がはっきり分かれることが多いですよね。
例えば、以下のようなチェックをしてみると、お子さんの特性が分かりますよ。
- 長時間集中できることはある?(例:好きなゲームや読書なら何時間でも続けられる)
- 新しい環境に適応しやすい?(例:転校や習い事の変更にすぐ慣れられるか)
- コミュニケーションが得意?(例:友達と話すのが好きか、人見知りしやすいか)
このようにお子さんの特性を見極めることで、職業選びの方向性が見えてきますね。
2-2. 将来の働き方をイメージする



職業選びでは、単に仕事内容だけでなく、どんな働き方が合うのかも考えることが大切です。
例えば、お子さんに合った働き方をイメージするために、以下の点を考えてみましょう。
| 項目 | お子さんに合った働き方を見つけるためのヒント |
| 対人関係 | 人と接する仕事が好き? それとも1人でできる仕事が向いている? |
| 仕事のリズム | 決まったスケジュールが好き? それとも変化があるほうが楽しい? |
| 集中力 | 長時間の作業は得意? それとも短時間の作業を繰り返すほうが向いている? |
2-3. 興味のあることを仕事につなげる
お子さんの「好きなこと」や「興味のあること」を仕事にするのも大切ですね。
特に発達障害のあるお子さんは、「好きなことにはとことんハマる」タイプの子が多いですよね。



例えば、こんなふうに考えてみると、お子さんの得意を活かせる職業が見えてきますよ。
- ゲームが好き → ゲームプログラマー、ゲームデザイナー
- 動物が好き → ペットトレーナー、動物園スタッフ
- ものづくりが好き → 工芸職人、デザイナー
お子さんが「好きなことを仕事にできる」と思うと、将来の働くイメージが明るくなりますね。
3. 発達障害の子どもに向いている職業とは?


お子さんが将来、どんな仕事なら楽しく続けられるのか、気になりますよね。
発達障害の特性に合った仕事を選ぶことで、お子さんの強みを活かしながら働くことができます。



3-1. ASD(自閉スペクトラム症)のお子さんに向いている仕事
ASDのお子さんは、規則的な作業や専門的な分野で力を発揮しやすい傾向があります。
また、一つのことに集中できる力を活かせる仕事が向いています。
ASDのお子さんに向いている仕事の特徴
- ルールが明確な仕事 → マニュアルに沿って作業できる職業
- 一人で集中できる仕事 → 他者との会話が少なく、黙々と作業できる仕事
- 専門性が高い仕事 → 自分の興味を追求できる職業
例えば、次のような職業が向いています。
| 職業 | 特徴 |
| プログラマー | 論理的思考が活かせる。個人作業が多い |
| データ分析 | 細かい作業をコツコツ続けられる |
| イラストレーター | 視覚的な才能を活かせる |
| 研究職 | 興味のある分野を深く追求できる |
3-2. ADHD(注意欠如・多動症)のお子さんに向いている仕事



ADHDのお子さんは、変化のある仕事や、自分のアイデアを活かせる職業が向いています。
一方で、単調な作業や長時間の集中が必要な仕事は苦手なことが多いです。
ADHDのお子さんに向いている仕事の特徴
- 変化が多い仕事 → 毎日同じ作業ではなく、新しいことに挑戦できる
- アイデアを活かせる仕事 → 発想力を活かせる職業
- 行動力が求められる仕事 → 体を動かしたり、人と関わる仕事
例えば、次のような職業が向いています。
| 職業 | 特徴 |
| 営業職 | 人と話すのが得意なら、得意分野を活かせる |
| イベントプランナー | 企画力や行動力を活かして活躍できる |
| スポーツインストラクター | 体を動かすのが好きならぴったり |
| YouTuber・ライター | 自由な発想やクリエイティブな才能を活かせる |
3-3. LD(学習障害)のお子さんに向いている仕事



LDのお子さんは、読み書きや計算が苦手なことが多いですが、創造力や実践的なスキルを活かせる仕事に向いています。
また、職人的な仕事や感覚を活かす仕事でも能力を発揮しやすいです。
LDのお子さんに向いている仕事の特徴
- 手を動かす仕事 → 実践的なスキルを活かせる職業
- クリエイティブな仕事 → デザインや映像編集など
- 人と関わる仕事 → コミュニケーションを活かせる職業
例えば、次のような職業が向いています。
| 職業 | 特徴 |
| 美容師・ネイリスト | 手を動かす職人仕事でスキルを活かせる |
| 料理人 | レシピを覚えるのが苦手でも、経験を積めば技術でカバーできる |
| 映像クリエイター | 文章を書くより、視覚的な才能を活かせる |
| カメラマン | 観察力を活かして表現ができる |
4. 親ができるサポートとは?
お子さんが将来、向いている仕事に就けるように、親としてできることを考えてみましょう。
「うちの子はちゃんと働けるのかな?」と不安になることもあると思いますが、家庭でのサポート次第で、お子さんの可能性は大きく広がります。



4-1. お子さんの得意なことを伸ばす
お子さんの「得意なこと」に目を向けて、伸ばしてあげることが大切です。
「苦手なことを克服する」よりも、得意なことを伸ばすサポートをしてあげるほうが、将来の可能性が広がります。
- 好きなことを応援する → 興味のある分野の習い事をさせてみる
- 成功体験を積ませる → 小さな成功を積み重ね、自信をつける
- 将来の仕事に繋がる経験を増やす → 企業見学や職業体験をさせてみる
4-2. 自己理解を深めるサポートをする



お子さんが自分の特性を理解し、それを活かせる職業を選ぶためには、親のサポートがとても大切です。
まずは、お子さんが自分の得意なこと・苦手なことを把握できるように、話し合ってみましょう。
自己理解が深まると、自分に合った仕事を選びやすくなります。
| サポート方法 | 具体的な取り組み |
| 日常の会話で特性を伝える | 「○○が得意だね」「この作業は少し大変そうだね」と言葉にして伝える |
| 成功体験を積ませる | 小さな目標を設定し、達成感を味わわせる |
| 特性を活かせる体験をさせる | 職業体験やボランティア活動に参加させる |
4-3. 将来の選択肢を増やす



発達障害を持つお子さんにとって、働き方は一つではありません。
正社員だけでなく、フリーランス、在宅ワーク、障害者雇用など、さまざまな選択肢があります。
「この道しかない」と決めつけず、柔軟に考えることが大切です。
- 障害者雇用枠を活用する → 発達障害を理解した職場で働く
- 在宅ワークを検討する → 通勤が難しい場合、自宅で働く選択肢も
- フリーランスとして働く → 自分のペースで仕事を進められる
お子さんにとって、無理なく働ける方法を見つけることが大切ですね。
5. 発達障害の子どもが働く上で利用できる支援制度
お子さんが将来、仕事をするうえで、支援制度を利用することで安心して働くことができます。



5-1. 就労移行支援を活用する
就労移行支援とは、障害を持つ方が仕事をするためのトレーニングを受けられる支援サービスです。
就労移行支援を活用すると、職場でのスキルを身につけられます。
| 支援内容 | 具体的な内容 |
| 職業訓練 | 仕事のスキルを学べる |
| 職場実習 | 実際に企業で働く体験ができる |
| 就職サポート | 履歴書の書き方や面接の練習ができる |
5-2. 発達障害者支援センターの活用



発達障害者支援センターでは、就職に関する相談や、職場での困りごとをサポートしてくれます。
就職後のフォローもしてくれるので、安心して働けます。
5-3. 障害者雇用枠を活用する
発達障害がある方のために、企業が障害者雇用枠を設けています。



障害者雇用枠のメリット
- 無理のない働き方ができる → 休憩時間や仕事内容の配慮がある
- サポートが受けられる → 相談できる担当者がいる
- 長く働ける環境が整っている → 安定して働ける職場が多い
6. お子さんが働きやすい環境を整えるためのサポート
発達障害のあるお子さんが将来、無理なく働けるようにするためには、職場環境の選び方や準備が重要ですよね。
親としてできるサポートを知っておくことで、お子さんがスムーズに社会に出られるようになりますよ。



6-1. お子さんに合った職場環境を見つける
職場環境が合っているかどうかで、お子さんの働きやすさが変わります。
発達障害の特性によって、向いている職場環境は異なります。
例えば、以下のような環境が適しているかを考えてみましょう。
| 職場環境のポイント | お子さんに合った環境を選ぶための目安 |
| 静かな職場 | ASDの方は、音や光に敏感なため、静かで落ち着いた環境が向いている |
| 柔軟な勤務スタイル | ADHDの方は、時間に縛られない自由な働き方が向いている |
| 明確なルールがある | ルールや手順が明確な職場だと、ASDの方が働きやすい |
| サポートが充実している | 障害者雇用枠がある企業や、支援制度が整った職場を選ぶ |
お子さんが無理せず長く働ける環境を見つけることが大切ですね。
6-2. 仕事のペースを調整する工夫



発達障害のある方は、集中力の波や疲れやすさがあるため、仕事のペースを調整することが重要です。
お子さんが無理せず働けるように、ペースを考えてあげましょう。
- 適度に休憩を取る → 長時間集中が難しい場合、短時間の休憩を挟む
- 作業を分割する → 一度にたくさんの仕事をするのではなく、少しずつ進める
- ストレスを減らす工夫をする → 必要に応じてノイズキャンセリングイヤホンを使用
仕事の進め方に少し工夫をするだけで、働きやすさがぐんと変わりますね。
6-3. 職場での困りごとを減らすためのコミュニケーション



発達障害の特性によって、職場のコミュニケーションが苦手なお子さんもいますよね。
でも、少しの工夫で人間関係のストレスを減らすことができます。
シンプルな伝え方を意識することで、誤解を防げます。
- 報連相(報告・連絡・相談)を意識する → 上司や同僚にこまめに状況を伝える
- 簡潔に話す → 余計な情報を入れず、伝えたいことをシンプルに
- 苦手なことを相談する → できることとできないことを事前に伝える
職場でのトラブルを減らし、安心して働ける環境を作りましょう。
7. 親としてできるサポートのまとめ
お子さんが社会に出て働くためには、親のサポートがとても重要です。
できることを少しずつ増やしながら、お子さんが働きやすい環境を整えてあげましょう。



7-1. 親ができる具体的なサポート
お子さんが社会に出る準備を、少しずつ始めていきましょう。
- お子さんの特性を理解する → 得意なことと苦手なことを把握する
- 職場環境を見極める → 働きやすい環境を一緒に探す
- 支援制度を活用する → 就労支援や障害者雇用枠を検討する
親御さんのサポートがあれば、お子さんも安心して働くことができますね。
8. まとめ
発達障害のあるお子さんが将来、無理なく働くためには、職業選びや職場環境がとても重要です。
親としてできるサポートを知っておくことで、お子さんの可能性を広げることができますよ。
- お子さんの特性に合った職業を選ぶことが大切
- 職場環境の工夫や支援制度を活用すると安心
- 親のサポートが将来の働き方を大きく左右する

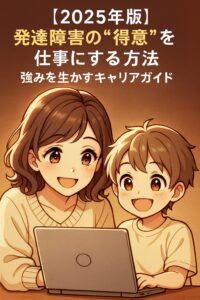


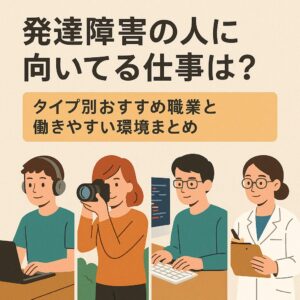
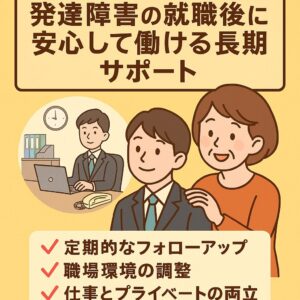
コメント