お子さんの教育について日々考えていらっしゃるお母さん方、今日は「STEM教育」と「発達障がい」についてお話ししたいと思います。
最近、耳にすることが増えた「STEM教育」ですが、発達障がいのある子どもたちにとって、どのような可能性が広がるのでしょうか。
ぜひ、一緒に考えてみましょう。
- STEM教育が発達障がいの子どもたちに与える影響
- 具体的な教材やプログラムの紹介
- 家庭で取り入れられる工夫やポイント
1. STEM教育とは?

最近、「STEM教育」という言葉を耳にする機会が増えましたよね。
STEMとは、Science(科学)、Technology(技術)、Engineering(工学)、Mathematics(数学) の頭文字を取ったもので、これらの分野を統合的に学ぶ教育のことを指します。
この教育方法は、論理的思考力や問題解決能力を育む ことを目的としており、特に 発達障がいのある子どもたちに適した学習法としても注目されています。
では、STEM教育の基本概念や、発達障がいの子どもたちにとってのメリットを見ていきましょう。
1-1. STEM教育の基本概念
STEM教育は単なる「理系の勉強」ではなく、子どもたちが創造力を働かせながら学ぶこと を重視した学習方法です。
例えば、プログラミングを学ぶ際には、
- キャラクターを動かすための手順を考え、試行錯誤を繰り返す
- 問題が発生した際に、どのように修正すればよいか論理的に考える
- 成功したときに達成感を得ることで、学習意欲が向上する
このように、STEM教育では**「試行錯誤しながら学ぶこと」**が重要視されており、決められた答えを覚えるだけの学習とは異なります。
また、視覚的・体験的に学べる という特徴もあり、言葉だけの説明では理解しにくい子どもにも適していると言われています。

1-2. 発達障がいの子どもたちに適した学習法
発達障がいのある子どもたちにとって、従来の学習方法では集中しにくかったり、興味が持ちにくかったりすることがありますよね。
ですが、STEM教育には、発達障がいの子どもたちに適した学習の特性がたくさんあります。
- 視覚的な学びが中心 … 文字だけでなく、動画やブロックなどを使った学習ができる
- 自分のペースで取り組める … 一斉授業ではなく、自分で考えながら学習を進められる
- 成功体験を積みやすい … 目に見える成果が得られるため、自己肯定感を育みやすい
また、STEM教育では、失敗することも大切な学びの一つとされているため、「間違えることが悪いことではない」という意識を持つことができる のも大きなメリットです。



2. STEM教育が発達障がいの子どもに与えるメリット


STEM教育は、発達障がいの子どもたちにとっても大きなメリットをもたらします。
従来の学習方法では集中が難しかったり、理解しにくかったりすることがあっても、STEM教育の特性を活かすことで、お子さんの強みを伸ばしながら学ぶことができる のです。
ここでは、特に大きなメリットとなる 「論理的思考力」「自己肯定感の向上」「感覚過敏や集中力の課題への適応」 について詳しく見ていきましょう。
2-1. 論理的思考力を育む効果
STEM教育の大きな特徴の一つが、論理的に考える力を養う ことです。
たとえば、プログラミング学習では、「こうすればこうなる」という 因果関係 を理解しながら進めるため、自然と論理的な考え方が身につきます。
- コードを組み立てながら、順序立てて考える力が育つ
- 試行錯誤を繰り返すことで、問題解決能力が向上する
- 自分の手で「動かす」「作る」体験ができるので、学びが定着しやすい
また、ロボットを動かすプログラミングなどでは、うまく動かないときに どこを直せば正しく動くのか? を考える必要があります。
このようなプロセスを繰り返すことで、問題が起こったときに解決策を考えられる力 が身についていきます。



2-2. 自己肯定感の向上につながる学習体験
発達障がいのある子どもたちの中には、学校の勉強でうまくいかず 「自分はできない」「勉強が苦手」 という気持ちを持ってしまう子もいますよね。
しかし、STEM教育では、「答えが1つではない学び方」 が多いため、お子さんの個性や得意なことを活かしながら取り組むことができます。
例えば、ロボットプログラミングの場合、
- 自分で考えたプログラムが成功すると、達成感を得られる
- 成果物が目に見える形で残るため、「できた!」という実感を持ちやすい
- 周りと比較せず、自分のペースで学べる
また、「失敗しても良い」 という学習環境が整っているのもSTEM教育の良いところ。
「失敗=学びの一部」という意識を持つことで、チャレンジする気持ちを育むことができます。



2-3. 感覚過敏や集中力の課題に適した学習方法
発達障がいのある子どもたちの中には、感覚過敏や注意の持続が難しいといった特性を持つ子 もいますよね。
STEM教育は、そんなお子さんにも適した学習方法が取り入れられています。
- 手を動かしながら学ぶので、飽きにくい
- タブレットやロボットを使うことで、視覚的にわかりやすい
- 「黙って聞く」授業ではなく、自分で試すスタイルなので集中しやすい
特に、タブレットを使ったプログラミング学習などは、音や光を活用した視覚的なフィードバック があり、感覚過敏の子でも取り組みやすい設計になっています。
また、一定のリズムで動くロボットやアニメーションなどは、予測しやすい動きがあるため、安心して学習を進められる という点も大きなメリットです。



3. 発達障がいの子ども向けのSTEM教材とプログラム
STEM教育のメリットが分かったところで、次に 実際にどのような教材やプログラムがあるのか を紹介していきますね。
発達障がいの子どもたちに適したSTEM教材は、視覚的に分かりやすく、試行錯誤しながら学べるものが多い です。
また、放課後等デイサービスや特別支援教育の現場でも、STEMプログラムが導入されることが増えてきています。
ここでは、具体的な教材やプログラムをいくつかご紹介しますね。
3-1. 実際に活用されているSTEM教材の紹介
最近では、発達障がいの子どもたちにも使いやすいSTEM教材が増えてきました。
特におすすめの教材をいくつか紹介しますね。
- ビスケット(Viscuit) … 直感的にプログラミングができるビジュアルプログラミングツール
- レゴ® エデュケーション SPIKE™ … レゴブロックを組み立てながらプログラミングを学べる
- Ozobot(オゾボット) … 色を使ってプログラムを組む、小さなロボット教材
例えば 「ビスケット(Viscuit)」 は、文字を使わずに 絵を描くだけでプログラミングができる ため、発達障がいの子どもたちにも分かりやすいと評判です。
また、レゴを使った教材は、手を動かしながら学ぶことができるため、触覚を刺激しながら学習できる というメリットもあります。



3-2. 放課後等デイサービスでのSTEM教育の取り組み
最近では、発達障がいの子どもたちを支援する 「放課後等デイサービス」 でも、STEM教育を取り入れるところが増えてきています。
特に、プログラミングを取り入れた療育が注目されており、以下のような施設があります。
- 「すてむぼっくす」 … 発達障がい児向けに開発されたSTEM教材を提供
- 「チャーム」 … プログラミング学習を取り入れたデイサービス
- 「LITALICOワンダー」 … 一人ひとりに合わせたSTEM教育プログラムを提供
例えば、「LITALICOワンダー」では、子ども一人ひとりの特性に合わせて、自由にSTEM学習ができる のが特徴です。
「チャーム」では、発達障がいの子どもたちの「好き」を「可能性」に変える ことを目的に、プログラミング学習を支援しています。



4. 家庭でできるSTEM教育の工夫
STEM教育は、学校やデイサービスだけでなく 家庭でも取り入れることができます。
特に発達障がいのあるお子さんの場合、親子で楽しみながら学ぶことが大切 ですよね。
ここでは、家庭でできる 簡単なSTEMアクティビティ や 親子で楽しめるプログラミング学習 についてご紹介します!
4-1. 日常生活でできる簡単なSTEMアクティビティ
「STEM教育」と聞くと、特別な教材が必要だと思われがちですが、実は 家庭でも簡単にできる学びがたくさんある んです!
- 料理で科学を学ぶ … 計量や化学変化を体験しながら、楽しく学ぶ
- ブロック遊びでエンジニアリング … 創造力を働かせながら構造の理解を深める
- 磁石や電池を使った実験 … 簡単な実験で物理の原理を学ぶ
例えば、料理をしながら 「この材料を混ぜると、どう変化するのかな?」 とお子さんに問いかけることで、化学の知識につながります。
また、ブロック遊びをする際に、「この形にすると倒れにくいね」 など、建築や重心の概念を伝えることもできます!



4-2. 親子で楽しめるプログラミング学習
最近は、自宅で手軽にできる オンラインプログラミング教材 も充実しています。
発達障がいのお子さんが楽しめるプログラミング教材として、以下のようなものがあります。
- Scratch(スクラッチ) … 直感的に学べる子ども向けプログラミング
- Code.org … 無料でできるゲーム感覚のプログラミング学習
- micro:bit(マイクロビット) … 実際に光ったり動いたりする教材で楽しく学べる
「Scratch」は、キャラクターを動かしながらプログラムを組むことができるので、絵や色を使って直感的に学べる のが特徴です。
また、「micro:bit」は ボタンを押すとLEDが光る などの実験ができ、手を動かしながら楽しく学べます。



5. STEM教育を活かした将来の可能性
STEM教育を受けることで、子どもたちの将来の選択肢は大きく広がります。
特に、発達障がいのあるお子さんにとって、自分の得意なことを活かせる職業や働き方を見つけるきっかけになる ことも多いんです。
ここでは、STEM教育がどのように将来の職業につながるのか、またITやエンジニアリング分野での活躍の可能性 についてお話ししますね!
5-1. 発達障がいの子どもの職業選択とSTEMスキル
STEM教育を通じて身につくスキルは、将来の職業にも役立ちます。
特に、発達障がいのある子どもたちは 「得意なことに没頭する力」「細かい作業が得意」「ルールに沿って考えるのが好き」 などの特徴を持つことがあり、STEM分野で活躍しやすい傾向にあります。
例えば、STEM教育で育まれるスキルを活かせる職業として、以下のようなものがあります。
- プログラマー・エンジニア … コードを書く作業は、論理的に考えるのが得意な子に向いている
- データアナリスト … 数字や統計に強い子が活躍できる分野
- ロボット開発・AI関連 … 自動化や機械学習の分野での活躍が期待される
また、STEMスキルは、これらの専門職だけでなく 一般的な仕事でも役立つ力 になります。
例えば、「問題が起きたときにどう解決するかを考える力」「新しい技術を学ぶ習慣」 などは、どんな仕事でも求められるスキルですよね。



5-2. IT・エンジニアリング分野での活躍の可能性
近年、ITやエンジニアリングの分野は、人材不足が続いており、今後ますます需要が高まる と言われています。
特に、発達障がいのある方が活躍しやすい分野として、以下のような職種が注目されています。
| 職種 | 特徴 |
| ソフトウェアエンジニア | 論理的思考力を活かして、プログラムを作成する仕事 |
| データサイエンティスト | データ分析を通じて、課題を解決する仕事 |
| ロボットエンジニア | 機械やロボットの開発に携わる仕事 |
特に リモートワークやフリーランスで働ける職業が増えている ため、自分のペースで仕事ができる環境も整ってきています。
また、海外では発達障がいの特性を活かして、プログラマーやデータアナリストとして活躍する人が増えており、日本でもその動きが広がりつつあります。



6. STEM教育を取り入れる際の注意点
STEM教育は発達障がいのあるお子さんにとって大きなメリットがありますが、取り入れ方を間違えると逆効果になることもある ので注意が必要です。
お子さんの特性に合った学習環境を整え、負担をかけすぎないように進めることが大切ですよね。
ここでは、STEM教育を取り入れる際の注意点 を解説します。
6-1. 子どもの特性に合った学習環境の作り方
STEM教育を効果的に取り入れるためには、お子さんの特性に合わせた環境を作ること が大切です。
例えば、発達障がいのあるお子さんの中には、以下のような特性を持つ子もいますよね。
- 感覚過敏がある … 音や光の刺激が強すぎると集中できない
- 長時間の学習が苦手 … 集中が続かず、途中で疲れてしまう
- 計画的に進めるのが難しい … やりたいことに夢中になりすぎる
これらを踏まえ、STEM学習をする際には 学習環境を整える工夫 が必要です。
例えば、
✅ 音や光の刺激を調整できる環境を用意する(静かな部屋・青色光を避けるなど)
✅ 短時間で区切って学習する(タイマーを活用する)
✅ 進める手順を明確にしておく(見通しを立てやすくする)
といった方法があります。



6-2. 過度な負担をかけない学習の進め方
お子さんが楽しく学べるようにするためには、無理のないペースで進めること も重要です。
特に、発達障がいのあるお子さんは、「自分のペースで学ぶこと」 がとても大切ですよね。
焦って進めてしまうと、逆に 「できない」「難しい」と感じてしまい、学習意欲が低下することもある ので、以下のポイントに注意しましょう!
- 興味を持てることから始める … 最初は好きなことを中心に取り入れる
- 結果ではなくプロセスを大切にする … 「できたかどうか」より「考えたこと」を褒める
- 失敗をポジティブに捉える … 失敗も学びの一部として受け入れる
例えば、プログラミングで 「うまく動かなかった!」 という経験をしたとき、
「なんで動かなかったのか、考えてみよう!」と声をかけると、失敗も学びの機会として活かせる んです。
また、「もっとやりたい!」と子どもが思えるように、楽しく進められる工夫をする ことも大切ですね。



7. まとめ
STEM教育は、発達障がいのあるお子さんにとって、自分のペースで学びながら、得意なことを活かせる学習方法 です。
視覚的・体験的な学びを通じて、論理的思考力を育み、自己肯定感を高めることができるのが大きな魅力ですね!
また、将来的には、IT・エンジニアリング分野での活躍の可能性も広がるため、「好き」を伸ばしながら、未来の選択肢を増やす ことができます。
では、今回の記事のポイントを振り返ってみましょう!
- STEM教育は、発達障がいの子どもたちの可能性を広げる学習法
- 家庭でも取り入れられる工夫があり、楽しく学べる
- 将来の職業にもつながる可能性があり、長期的な視点で学びを進めることが重要
お子さんの「好き」を大切にしながら、楽しくSTEM教育を取り入れてみてくださいね!
無理なく、楽しみながら学べる環境を作ることで、お子さんの未来がもっと輝くはずです。

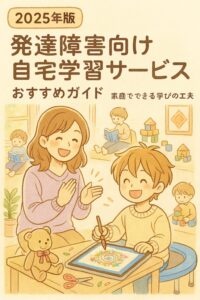
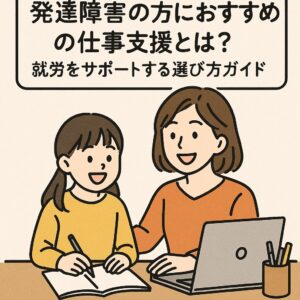


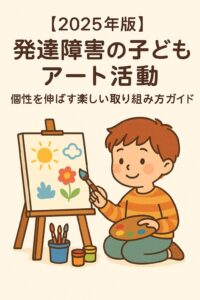



コメント