発達障害のある子どもは、苦手な部分ばかりが目立ってしまいがちですが、実は人一倍すぐれた「得意」や「強み」を持っていることが多いんですよね。
例えば、細かい作業に集中できる子、想像力が豊かでアイデアを出すのが得意な子、人との会話を楽しめる子など…。
こうした特性は、大人になってから「仕事」として大きな武器になる可能性があります。
ただ、「どうやって得意を見つければいいの?」「本当に仕事につながるの?」と不安になるお母さんも多いと思います。
そこで本記事では、発達障害の子どもの得意を見つける方法から、それを将来のキャリアにつなげる工夫までをわかりやすく解説していきます。
最後まで読んでいただくことで、お子さんの未来を明るくイメージできるようになりますよ。
- 発達障害の子どもの得意を伸ばす大切さ
- 得意を将来の仕事につなげる具体的な視点
- お母さんが日常でできるサポート方法
1. 発達障害の子どもが“得意”を仕事につなげられる理由

発達障害の子どもたちは、特性の中に「キラリと光る得意分野」を持っていることが多いです。
苦手を無理に克服するよりも、得意を伸ばすことで自己肯定感が高まり、将来のキャリアにも直結しやすくなります。
社会全体でも「多様な人材の活躍」が求められている今、子どもの特性は立派な強みになっていくんですよね。
1-1. 「得意」を伸ばすことが将来の自信につながる
発達障害の子どもは、学校生活の中で苦手を指摘されることが多く、自己肯定感を持ちにくいといわれます。
でも、得意分野を見つけて伸ばしていけば、「自分にはできることがある」という自信につながります。
例えば、絵を描くのが得意な子が作品を褒められることで、「もっと挑戦したい」という意欲が生まれますよね。
得意を伸ばすことは、子どもが自分を認められる大切なきっかけになります。

1-2. 苦手を補うより得意を強みにするほうが活躍しやすい
発達障害の子どもにとって、苦手を克服することはエネルギーをたくさん消耗します。
一方で、得意なことに集中すると驚くほどの力を発揮できることが多いです。
たとえば、細かい作業が好きな子はデータ入力や整理の仕事に向いていたり、話すのが好きな子は接客や説明の仕事で輝けたりします。
つまり、社会に出てからも「苦手を直す」のではなく「得意を活かす」ほうが、結果として活躍の場を広げられるんです。



得意を伸ばすほうがずっと自然です。
1-3. 社会が求めている多様なスキルに合いやすい
現代社会では、多様な人材の活躍が求められています。
AIやデジタル技術の発展により、これまでになかった仕事も増えてきました。
発達障害の子どもが持つ「こだわりの強さ」や「集中力の高さ」は、プログラミングやデザインなどの分野で大きな強みとなります。
社会が多様性を重視する今こそ、発達障害の子の特性が武器になる時代なんです。



2. 発達障害の特性と“得意”の見つけ方


発達障害といっても、子どもによって特性や得意分野はまったく違いますよね。
「うちの子は何が得意なのかな?」と悩むお母さんも多いと思います。
そこで代表的な発達障害のタイプごとに見られやすい“得意”の傾向を紹介していきます。
もちろんすべての子に当てはまるわけではありませんが、特徴を知ることでお子さんの強みを見つけやすくなりますよ。
2-1. ASD(自閉スペクトラム症)に多い得意分野
ASDのお子さんは、強いこだわりや集中力を発揮することが多いです。
例えば、数字や規則性に敏感だったり、興味のある分野にとことん没頭できたりします。
そのため、研究職やプログラミング、データ分析などで力を発揮するケースがあります。
また、細部に目が行き届くことから、イラストや設計の分野で才能を伸ばす子もいます。
こだわりや集中力は、将来“専門性のある仕事”につながる大きな強みになるんです。



2-2. ADHD(注意欠如・多動症)に多い得意分野
ADHDのお子さんは、発想力や行動力にあふれていることが特徴です。
思いついたことをすぐ行動に移せたり、人前で話すのを楽しめたりする子もいます。
こうした特性は、営業や接客、イベント企画などで生きてきます。
また、新しいことにどんどん挑戦できる積極性は、ベンチャー企業やクリエイティブな仕事にも向いています。
「好奇心旺盛でエネルギッシュ」な面は、社会で大きな魅力になるんです。



2-3. LD(学習障害)に多い得意分野
LDのお子さんは、読み書きや計算に困難があっても、芸術やスポーツなどで高い能力を発揮することがあります。
たとえば、音楽のリズム感や絵を描く表現力、体を動かすセンスに優れている子も少なくありません。
こうした得意分野は、アーティストやスポーツ関連の仕事に発展する可能性があります。
また、実体験を通して学ぶ力が強い子も多いため、実習や現場で力を伸ばせる環境が合いやすいです。
「学び方の多様性」が、その子ならではの強みを引き出すヒントになるんです。



3. 子どもの得意を見つける家庭での工夫


得意を見つけるには、特別な検査や指導だけではなく、日常生活の中での観察や声かけがとても大切なんです。
お母さんが一番近くで見ているからこそ気づけることがたくさんありますよね。
ここでは家庭でできる工夫を3つご紹介します。
3-1. 日常生活の中で興味を観察する
お子さんが日々どんなことに夢中になっているかを、まずはじっくり観察してみましょう。
遊びの中で長い時間集中していることはありませんか。
たとえばブロック遊びをコツコツ続けていたり、同じ絵本を何度も読んでいたりするのも立派な「得意のサイン」です。
お母さんが「この子はここに興味があるんだな」と気づくことが、将来の得意を伸ばす第一歩になるんですよね。
得意は特別な場所ではなく、日常の中に隠れていることが多いんです。



3-2. 小さな成功体験を積み重ねる
得意を見つけるためには、「できた!」という小さな達成感を繰り返し味わうことも大切です。
例えば、お手伝いで食器を並べるのが上手にできたときに「ありがとう、すごく助かったよ」と声をかける。
宿題の一部を自分でやり切れたら「よく頑張ったね」と認めてあげる。
こうした積み重ねが「自分はこれができる」という自信につながり、得意を見つけるきっかけになります。
お母さんのちょっとした一言が、子どもにとって大きな励みになるんです。



3-3. お母さんの声かけで自信を引き出す
発達障害の子どもは、苦手なことを指摘されることが多く、自信をなくしがちです。
だからこそ、お母さんの声かけで「得意」を意識させてあげることが大切なんです。
「絵を描くのが本当に上手だね」「集中してできるのはすごい力だよ」など、具体的に褒めることで「自分の強み」に気づきやすくなります。
その積み重ねが「得意を育てるサイクル」になっていくんですよね。
お母さんの言葉は、子どもにとって自分の可能性を広げる魔法のような力になります。



4. 得意を仕事につなげるための学び方
子どもの得意を「趣味」で終わらせず、将来の仕事につなげていくには、学び方を工夫することが大切です。
ただ楽しむだけでなく、「学びの場」「体験の機会」「スキルの積み重ね」を意識することで、子どもの得意はより実践的な力へと育っていきますよ。
ここでは、家庭でも取り入れやすい学び方を3つご紹介します。
4-1. 習い事や教室でスキルを伸ばす
得意をさらに磨くには、専門的な環境に触れることが効果的です。
たとえばプログラミング教室、アートスクール、音楽教室などは「好き」を「スキル」に変える場になります。
同じ興味を持つ仲間と一緒に学べるので、子ども自身のモチベーションも高まりますよね。
また、先生からの客観的な評価やアドバイスは、お母さんだけでは気づけなかった可能性を広げてくれることもあります。
得意を伸ばすには、家庭の外で専門的なサポートを受けることも大きな一歩です。



4-2. 自宅学習やオンラインサービスを活用する
近年は、家庭でも本格的に学べるオンライン教材やアプリが充実しています。
プログラミングや英会話、デザインなど、興味を持った分野をすぐに試せるのが魅力です。
自宅学習のメリットは、子どものペースに合わせて取り組めること。
苦手な部分でつまずいても、焦らず繰り返せますし、得意な部分はどんどん進められます。
また、親子で一緒に取り組むことで「楽しい学びの時間」として習慣化しやすくなるのも良い点です。



4-3. インターンや体験活動で実践力を養う
学んだ得意を「体験の場」で活かすことも大切です。
地域のワークショップやボランティア活動、学生向けのインターンなどは、得意を社会で試せる絶好の機会になります。
実際に体験してみることで「自分の得意は人の役に立つんだ」と実感でき、自己肯定感がさらに高まります。
また、失敗も含めて経験することで「仕事にする力」へとつながっていくんですよね。
得意を社会の中で活かす経験こそ、未来のキャリアにつながる最強の学びです。



5. 発達障害の子に向いている職業ジャンル
発達障害の子どもが持つ「得意」を生かせる職業は、実はたくさんあるんです。
「この子の特性って、どんな仕事に合うのかな?」と考えると、不安よりもワクワクが広がりますよね。
ここでは、代表的な3つの職業ジャンルをご紹介します。
5-1. IT・プログラミング系
集中力が高い子や、規則性や論理的な思考が得意な子には、ITやプログラミングの仕事が向いています。
コードを書く作業は、一見難しく見えますが、パターンやルールを覚えて繰り返すのが得意な子にはとてもマッチする分野なんです。
また、システム開発やデータ分析といった仕事では「細かい部分に気づける力」が評価されるため、ASD傾向のある子にとっては大きな強みになります。
IT分野は今後ますます需要が高まるため、子どもの得意を武器にできる可能性が広がっています。



5-2. デザイン・クリエイティブ系
絵を描くのが好き、色や形にこだわりがある、アイデアを考えるのが得意。
そんなお子さんには、デザインやクリエイティブの分野が合っています。
グラフィックデザイン、イラスト制作、動画編集、Webデザインなどは、自分のセンスを直接仕事にできる世界です。
「好きだからこそ続けられる」気持ちが、スキル向上にもつながります。
さらに今は、オンラインで学べる教材や副業のチャンスも多いので、将来のキャリア選択肢が広がっている分野でもありますよ。



5-3. 接客・コミュニケーションを活かす仕事
人と話すのが好き、初めて会う人ともすぐ打ち解けられる。
そんなタイプのお子さんには、接客やコミュニケーションを活かせる仕事が向いています。
例えば、販売やサービス業、カウンセラーやサポート職などです。
ADHDの子に多い「エネルギッシュさ」「行動力の速さ」も、こうした仕事で大きな魅力として輝きます。
人と関わる力もまた、大切な“得意”であり、社会に必要とされる強みなんです。



6. 得意を仕事にするためのサポート体制
子どもの得意を仕事に結びつけるには、家庭だけでなく学校や社会のサポートも欠かせません。
「お母さんが応援している」だけでは限界があることもありますよね。
学校、支援機関、家族がそれぞれの立場で協力し合うことで、子どもの強みをのびのびと育てられる環境が整っていきます。
6-1. 学校や先生と連携する
まず大切なのは、学校の先生や支援員との連携です。
学校での様子は家庭では気づけない部分が多く、先生から得られる情報はとても貴重です。
例えば「授業中は集中が難しいけど、図工や音楽では意欲的に取り組んでいる」といった声は、子どもの得意を把握するヒントになります。
先生と話し合いながら、「得意を活かせる場面を増やす工夫」を学校生活に取り入れることで、子ども自身も自信を持ちやすくなります。
学校と家庭が同じ方向を向いてサポートすることが、子どもの成長を大きく後押しします。



6-2. 就労移行支援や職業訓練を活用する
大人に近づくにつれて頼りになるのが、就労移行支援や職業訓練の制度です。
発達障害のある方が安心して働けるよう、職業スキルを学んだり、実習で経験を積んだりできる場所なんです。
専門スタッフが一人ひとりに合った仕事探しをサポートしてくれるため、「得意をどう仕事に結びつけるか」が具体的に見えてきます。
また、面接練習や職場適応のサポートも行ってくれるので、お母さんも安心して子どもの社会参加を見守れるようになります。



6-3. 家族の理解と協力がカギになる
最終的に子どもを支える一番の存在は、やっぱり家族です。
お母さんだけでなく、お父さんやきょうだいが「得意を応援する姿勢」を持つことで、子どもは安心して挑戦できます。
家庭の中で「失敗しても大丈夫」「できることに集中していいんだよ」と伝え続けることが、得意を仕事につなげる力になります。
家族の理解と協力は、子どもが自分らしいキャリアを築くための一番の土台です。



7. お母さんにできること
子どもの得意を仕事につなげていく上で、一番身近でサポートできるのはやっぱりお母さんですよね。
日常の声かけや見守り方ひとつで、子どもの自信ややる気は大きく変わります。
ここでは、お母さんが意識できる3つの関わり方をご紹介します。
7-1. 子どもの得意を認めて褒める
子どもの得意を見つけたら、ぜひその瞬間に認めてあげましょう。
「すごいね」「こんなに集中できるなんて立派だよ」と、具体的に褒めることで子どもは「自分の得意」を意識できます。
得意を褒めてもらえる経験は、将来「自分の強みを仕事にする」という自信の源になります。
特に発達障害のある子どもは、苦手を指摘されることが多いため、「得意を褒められる体験」が心の支えになるんです。
お母さんの言葉ひとつで、子どもの自己肯定感は大きく育っていきます。



7-2. 挑戦を見守りつつ支える
子どもが新しいことに挑戦するとき、お母さんは「失敗しても大丈夫」と安心感を与えてあげることが大切です。
発達障害の子は、環境の変化や初めての経験に不安を感じやすいですが、「そばにいてくれる人がいる」という安心があれば、挑戦する勇気を持てます。
もちろん、すぐに手を出して助けるのではなく、必要なときにだけ支える姿勢が理想です。
そのバランスが、子どもの自立や将来のキャリア形成につながっていくんですよね。



7-3. 苦手よりも“できること”に目を向ける
子育ての中ではつい「どうしてできないの?」と苦手に注目してしまいがちです。
でも、発達障害の子にとって大切なのは「できないこと」ではなく「できること」に光を当てることなんです。
お母さんが「あなたのここが素敵だよ」「これは得意だね」と伝えるたびに、子どもは自分の可能性を信じられるようになります。
苦手を補うよりも、得意を伸ばす意識が、将来「得意を仕事に」する道を切り開いていきます。
“できることに目を向ける”という姿勢が、子どもの未来を広げる最大のポイントです。



8. まとめ|発達障害の子どもの得意を未来の仕事に
発達障害のある子どもは、苦手よりも「得意」に注目することで大きな可能性を発揮できます。
日常のちょっとした行動の中に、将来のキャリアにつながるヒントは隠れています。
お母さんが「得意を認めて、褒めて、応援する」ことで、子どもは自信を持ち、未来の仕事へとつなげられるんです。
社会でも多様性が求められている今だからこそ、子どもの得意は立派な武器になります。
家庭・学校・支援機関が協力して環境を整えながら、お母さんの温かいサポートで、子どもの強みを大切に育てていきましょう。
- 発達障害の子どもは“得意”を伸ばすことで自信と将来の可能性が広がる
- 得意を仕事につなげるには家庭・学校・支援機関の協力が大切
- お母さんの声かけと応援が、子どものキャリア形成の大きな力になる



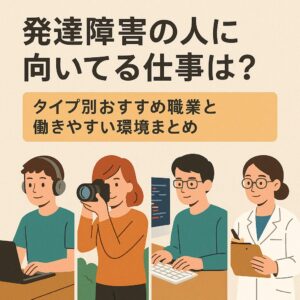
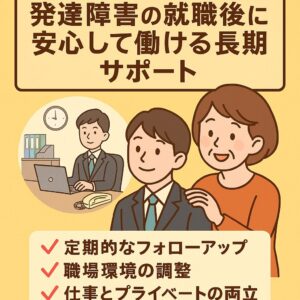

コメント